年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する法令・契約関連
【完全ガイド】店舗賃貸借契約書とは?出店前に必ず押さえるべきポイント総まとめ

- 目次

事業を始める際、物件選びと同様に重要なのが賃貸借契約書の理解です。特に店舗物件は住宅とは異なる要素が多く、事前の把握が不可欠です。本記事では「店舗の賃貸借契約書」に関する基本知識から注意点までを解説します。これから出店を考えている事業者や、賃貸人側の関係者にも有益な内容です。
契約書のポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎましょう。
店舗の賃貸借契約とは?
店舗の賃貸借契約とは、事業用として建物を貸し借りする契約のことです。住居用とは異なり、営業目的に特化した契約内容が含まれる点が特徴です。たとえば、「賃料には消費税が課される」「造作の扱い」「契約解除条件」が異なります。
契約対象の物件には、路面店、テナント、居抜き物件、スケルトン物件などがあります。また、契約の種類には「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」があります。普通契約では自動更新があり、定期契約では再契約が必要であることに注意が必要です。
事業用としての契約は、営業利益や設備、工事などに直結するため、内容に曖昧さがあると営業停止や損害賠償リスクにもつながります。
店舗賃貸借契約書の必要性と役割
民法上は口頭契約にも法的効力が認められますが、実務上はトラブル防止の観点から書面による契約締結が一般的です。
契約書がなければ、賃料・契約期間・解除条件などで揉めるリスクが高まります。また、契約書は許認可取得や融資申請の際に提出を求められるケースがほとんどです。銀行融資や助成金申請時に求められる場合も多く、信頼性を担保する資料としても重要です。契約書は賃貸人と賃借人双方の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐ重要な書類です。
特に原状回復や中途解約、保証金返還などの場面では契約書の文言が根拠となります。
関連コラム:賃貸借契約書とは?確認すべき項目と法人が契約する時の注意点
契約書に記載すべき項目と注意点
店舗賃貸借契約書の主な記載事項と注意点を説明します。
店舗や事務所など事業用の賃貸借契約書のテンプレートは、以下の機関から入手することができます
1. 物件の特定
所在地、家屋番号、構造、専有面積などを正確に記載します。登記簿謄本との整合性や床面積の測定方法も確認しておきましょう。建物全体のどの部分か(例:1階の一部、2階全体など)も明確にすることが望ましいです。
2. 使用目的
「飲食店」「オフィス」「美容室」など、用途を具体的に明記します。法令や用途地域の制限、必要な許認可との整合性も確認が必要です。想定外の業種での使用は契約違反とされるリスクがあるため、用途の記載は非常に重要です。
3. 契約期間と更新
「契約開始日〜終了日」までを明記し、更新の有無も記載します。定期借家契約の場合、再契約が必要であり、再契約の合意がないと継続できません。普通借家契約では自動更新される場合もありますが、更新料の設定も確認が必要です。
4. 賃料・敷金・保証金・礼金
賃料の金額、支払期日、支払方法(振込先)などを正確に記載します。保証金や敷金の返還条件、礼金の性質(償却されるか)なども明示します。一時金の償却については、契約書に明確に記載され、賃借人に説明されていない場合には、消費者契約法等により無効と判断される可能性があります。
5. 原状回復と設備
原状回復や設備の取り扱いに関する契約内容は、スケルトン物件か居抜き物件かによって大きく異なるため、契約時に明確に定めておくことが重要です。照明や什器、エアコンなど設備の所有者や撤去・譲渡条件を明確にしましょう。原状回復義務の範囲が不明確だと、退去時に高額な請求を受ける恐れもあります。
関連コラム: 原状回復工事とは?範囲・費用・スケジュールに関する注意点を解説
6. 解約・解除条項
中途解約する場合の通知期間(例:3か月前)や違約金の有無を確認します。債務不履行時の解除条件も明記しておくと安心です。賃料滞納が何回続いたら解除できるのかなど、具体的な基準も明示しておきましょう。
7. 連帯保証人
個人がテナント契約する際には、連帯保証人を求められることがあります。保証人の責任範囲や代替として保証会社の利用条件なども記載されます。保証人が第三者である場合は、保証意思確認書の取り交わしが求められることもあります。
8. 特約事項
契約書には記載されない特別な条件を盛り込む欄です。営業時間、看板設置のルール、造作買取の有無、禁煙・騒音対策などが含まれます。火災保険の加入義務や、共用部の利用条件など、細かな条件も特約として明記されます。
9. 賃貸人・賃借人の義務
賃借人は営業継続の責任、賃貸人は設備維持の責任など、お互いの義務を記載します。共用部の使い方やゴミ出しのルール、騒音・臭気への配慮なども明記しておくと良いでしょう。
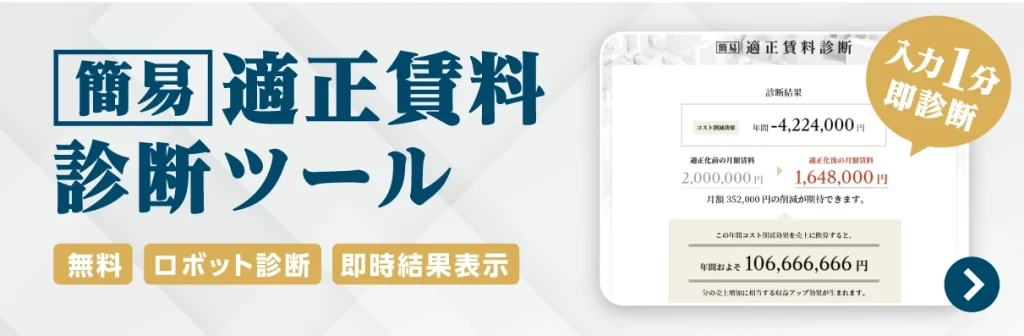
テナント契約時のポイント
店舗物件を契約する際には、事業の安定運営に直結する重要なポイントを事前に確認しておく必要があります。契約内容の理解不足や曖昧な条件設定は、営業停止や高額な原状回復費用などのトラブルにつながる可能性があります。以下では、契約時に特に注意すべき項目を具体的に解説します。
1. 契約形態の確認
テナント契約には主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。普通借家契約は自動更新が可能で、借主都合による途中解約も認められるケースが多い一方、定期借家契約は契約期間満了で終了し、原則として途中解約ができません。契約形態によって更新手続きや解約条件が大きく異なるため、自社の事業計画に合った契約形態を選択することが重要です。
2. 使用目的の明記と用途制限の確認
契約書には店舗の使用目的(例:飲食店、美容室、オフィスなど)を明記する必要があります。用途地域の制限や必要な許認可との整合性も確認しましょう。契約後に業態変更を行う場合は、必ず貸主に申告し、合意を得ることが求められます。用途変更の申告漏れは契約違反とみなされ、契約解除や損害賠償のリスクを招く可能性があります。
3. 原状回復の範囲と設備の取り扱い
退去時の原状回復義務については、契約書に具体的な範囲を明記しておくことが不可欠です。スケルトン物件か居抜き物件かによって、回復内容や設備の撤去・譲渡条件が異なります。照明・什器・エアコンなどの所有権や撤去義務を事前に確認し、写真などで現況を記録しておくと、トラブル防止に役立ちます。
4. 解約・解除条項の明確化
中途解約を行う場合の通知期間(例:3か月前)や違約金の有無、債務不履行時の解除条件などは、契約書に明記しておく必要があります。賃料滞納が何回続いたら解除可能かなど、具体的な基準を設定することで、貸主・借主双方のリスクを軽減できます。
5. 契約金・初期費用の内訳と支払先の確認
契約時には、保証金(敷金)、礼金、前家賃、仲介手数料、火災保険料など、複数の費用が発生します。支払先が貸主・不動産会社・保険会社などに分かれるため、支払期日や金額、振込先を明確にしておくことが重要です。特に人気物件では保証金が家賃の10〜15か月分に及ぶこともあるため、事前の資金計画が欠かせません。
テナント契約する際の注意点
テナント契約は、店舗運営の成否を左右する重要なステップです。契約内容の理解不足や確認漏れが原因で、退去時に予期せぬ費用負担や営業停止といったトラブルに発展するケースも少なくありません。ここでは、契約時に特に注意すべきポイントを、事業者目線でわかりやすく解説します。
1. 原状回復の範囲を明確にする
退去時の原状回復工事は、契約時の認識のズレが原因でトラブルになりやすい項目です。特に、居抜き物件やスケルトン物件では、どこまで復旧すべきかの判断が難しく、賃貸人と賃借人の間で意見が食い違うことがあります。
契約書に記載された範囲だけでなく、写真や図面などで現状を記録し、賃貸人と復旧範囲の認識を一致させておくことが重要です。賃貸人が変更になる可能性がある場合は、引き継ぎの際にも確認を怠らないようにしましょう。
2. 用途変更は必ず事前に相談する
契約時に定めた使用目的(例:雑貨店、オフィス、美容室など)を変更する場合は、必ず賃貸人に事前相談が必要です。無断で飲食店などに業態変更した場合、契約違反とみなされ、契約解除や損害賠償の対象になることもあります。
特に、マンション管理組合が存在する物件では、業種によっては営業自体が認められないケースもあるため、事前確認は必須です。
3. 契約形態(普通借家契約・定期借家契約)を理解する
テナント契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、それぞれ契約期間や更新の有無、途中解約の可否が異なります。
- 普通借家契約:自動更新が可能で、賃借人都合による途中解約も認められる。
- 定期借家契約:契約期間満了で終了し、原則として途中解約は不可。
長期的な店舗運営を考えている場合は、契約形態の違いを理解したうえで、事業計画に合った契約を選択することが大切です。
4. インフラ設備の状態を契約前に確認する
給排水、電気、ガスなどのインフラ設備は、特に飲食店や美容室では営業に直結する重要な要素です。契約書だけで判断せず、必ず現地で設備の有無や位置、稼働状況を確認しましょう。
「好立地で賃料が安い」と即決した結果、必要な設備が整っておらず、追加工事で予算オーバーになるケースもあります。
5. 契約書・重要事項説明書は細部まで確認する
契約書や重要事項説明書には、賃料、保証金、礼金、更新料、解約通知期間、違約金など、店舗運営に関わる重要な条件が記載されています。専門用語が多く読みづらい部分もありますが、疑問点は必ず不動産会社や管理会社に確認しましょう。
また、申込金の返還条件なども明記されているか確認し、トラブルを未然に防ぐための書面管理も徹底しましょう。
契約締結までの流れと準備
物件の内見後、申込書を提出し、審査を経て契約に進むのが一般的な流れです。契約書は賃貸人と賃借人で2通(場合によっては3通)作成し、記名押印を行います。書面契約が基本ですが、電子契約も可能な時代となっており、印紙税の扱いに注意が必要です。
店舗賃貸借契約書印紙代は契約金額によって異なるため、税務面でも確認が必要です。
トラブル事例と回避策

1. 賃料滞納
賃料滞納が発生した際、催告の要否や契約解除の条件が契約書に記載されていないと、対応が遅れトラブルに発展します。「何回滞納で解除可能か」「催告の方法」などを事前に定めておくことで、紛争を回避できます。
2. 原状回復
原状回復の範囲を明確にしないまま契約すると、退去時に壁紙や床材の補修をめぐってトラブルになりがちです。設備や内装の現況は写真で残し、契約書にも復旧義務の範囲を具体的に記載しておくことが大切です。
3. 中途解約
中途解約の際、いつまでに通知すれば良いのか、違約金が発生するのかといった条件が不明確だと、賃貸人・賃借人間でトラブルに発展します。通知期限や違約金の金額・発生条件を契約書に明示しておきましょう。
4. 用途制限
店舗物件の使用目的が契約内容と異なっていたり、臭気や騒音が発生する業態を制限している場合、クレームや契約解除の原因になります。契約前に用途制限の内容を確認し、明記しておくことが必要です。
5. 保証人関連
連帯保証人を設定する場合、責任の範囲を明文化しないと、支払い義務の認識で揉める恐れがあります。また、火災・地震等による不可抗力で営業不能になった場合の契約解除や減額条件も、特約として定めましょう。
居抜き・スケルトン物件の注意点
1. 居抜き物件
造作・設備の所有権、譲渡契約の有無、設備の状態確認を徹底します。譲渡価格や名義変更の手続き、営業許可の引継ぎの可否なども確認しましょう。
2. スケルトン物件
内装工事の仕様、施工許可、費用負担、原状回復範囲を確認しましょう。工事業者の指定、営業時間外の工事制限なども契約に盛り込まれることがあります。いずれも「現況渡し」の条件を契約書に明記することが重要です。
【居抜き・スケルトンの基礎知識】はこちら▼
オフィスとしての利用時の注意点
オフィス利用の場合、OA機器の電源容量や配線条件を事前に確認しましょう。用途制限がある場合、業種によっては利用できない可能性があります。静穏性やセキュリティ、ネットワークの整備状況なども評価ポイントになります。
契約書には「事務所使用に限る」と明記されることが多く、来客頻度の多い業態は注意が必要です。
契約更新・解約の手続き
更新手続きの条件(自動更新か否か、更新料の有無)を確認しましょう。定期借家契約は、原則として再契約が必要で、賃貸人の合意がないと継続できません。解約時には、通知期間、書面での通知義務、明渡し期限などを明記しておきましょう。
特に繁忙期の解約は、後継テナントとの引継ぎや造作譲渡にも影響するため、スケジュールを前倒しで調整する必要があります。
契約不適合責任について
契約時と異なる内容(例:雨漏り、エアコンの故障など)が発覚した場合、賃貸人に責任が生じます。賃借人は通知義務を果たすことで、修補や契約解除、損害賠償を請求できることがあります。
契約書に『現況有姿で引き渡す』と記載されていても、隠れた瑕疵(重大な雨漏り、構造的欠陥など)があれば、賃貸人は契約不適合責任を負う場合があります。
貸主が店舗賃貸借契約で注意すべき点
テナント契約を円滑に進めるためには、借主自身が貸主の立場や契約上の責任を理解しておくことが重要です。貸主がどのような点に注意して契約を進めているかを知ることで、借主側も適切な準備や確認ができ、契約後のトラブルを未然に防ぐことができます。
1. 使用目的と法令遵守の確認
貸主は、物件がどのような用途で使用されるかを契約書に明記し、法令に違反しないかを確認する義務があります。例えば、飲食店として使用する場合、排水設備や消防法の基準を満たしているかを事前に確認する必要があります。借主としても、希望する業態が物件の用途制限に適合しているかを事前に確認し、貸主との認識を一致させておくことが大切です。
2. 原状回復の範囲を明確にする
貸主は、退去時にどの範囲まで原状回復を求めるかを契約書に明記する責任があります。曖昧な記載は、借主との認識のズレを生み、費用負担をめぐるトラブルにつながります。借主としては、契約書の記載内容だけでなく、口頭での説明や現況写真なども活用し、原状回復の範囲を具体的に把握しておくことが重要です。
3. 中途解約・契約解除の条件設定
貸主は、借主が途中で退去する場合の通知期間や違約金の有無を契約書に定めることで、空室リスクを軽減しようとします。借主側も、事業計画の変更や撤退の可能性を踏まえ、契約解除に関する条項を事前に確認しておくことで、予期せぬ費用負担を避けることができます。
4. 設備・造作の所有権と管理責任
貸主は、物件内の設備や造作物の所有権を明確にし、管理責任の所在を契約書に記載する必要があります。借主としては、居抜き物件などで設備を引き継ぐ場合、どの設備が貸主所有で、どれが前借主の残置物かを確認し、撤去義務や修繕責任の有無を把握しておくことが重要です。
5. 契約更新・終了の条件の明文化
貸主は、契約期間満了後の更新条件や、更新料の有無、通知期限などを契約書に明記することで、借主との認識の齟齬を防ぎます。借主側も、更新のタイミングや条件を把握しておくことで、事業継続の計画を立てやすくなります。特に定期借家契約の場合は、契約終了の通知が必要なため、注意が必要です。
まとめ
店舗賃貸借契約書は、安心して事業を始めるための「設計図」ともいえる存在です。契約書の項目を一つひとつ丁寧に確認し、トラブルの芽を事前に摘むことが大切です。
契約前には専門家に相談し、不安な部分を解消してから締結することをおすすめします。賃貸人・賃借人双方が納得できる契約を結び、長期的な信頼関係を築いていきましょう。また、物件や事業内容に応じた柔軟な契約内容の設計も重要です。
店舗契約や賃料に関するお悩みは、専門家に相談するという選択肢も
店舗の賃貸借契約は、契約条件の確認や原状回復の範囲、賃料交渉など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。特に「賃料が高い気がするが、貸主との関係性が気になって交渉できない」「契約更新時に賃料増額を提示されて困っている」といった悩みは、店舗経営者にとって大きな負担となりがちです。
そうした課題に対して、ビズキューブコンサルティングでは、賃料適正化の専門家が無料で物件診断を行い、交渉から契約更新までをサポートするサービスを提供しています。診断結果に基づく客観的なデータをもとに、貸主との関係性を損なわずに賃料減額を実現するノウハウが蓄積されており、減額成功率は64.6%、平均減額率は16.2%という実績もあります。
「契約内容に不安がある」「賃料を見直したい」と感じたら、まずは無料診断から始めてみるのも一つの選択肢です。
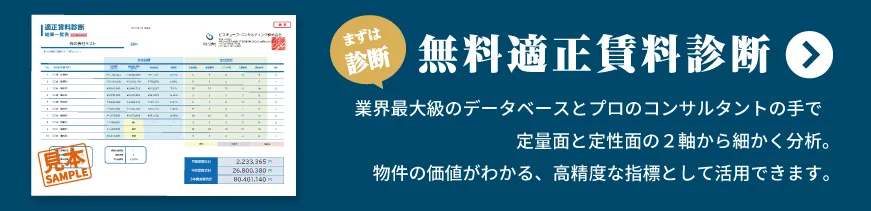
今の賃料が「安い」「適正」「高い」でハッキリわかる
【無料】実態分析賃料データ15万件分を駆使した高精度な賃料適正診断
店舗・事務所・オフィスなど、幅広くご対応いたします。
クライアント企業 全3,593社うち上場企業400社以上
累計削減件数 35,000件以上
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。




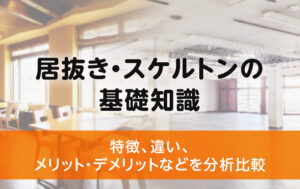






 人気記事ランキング
人気記事ランキング

