年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
オフィス賃料が高すぎる?見直しのタイミングとコスト削減の実践ポイント
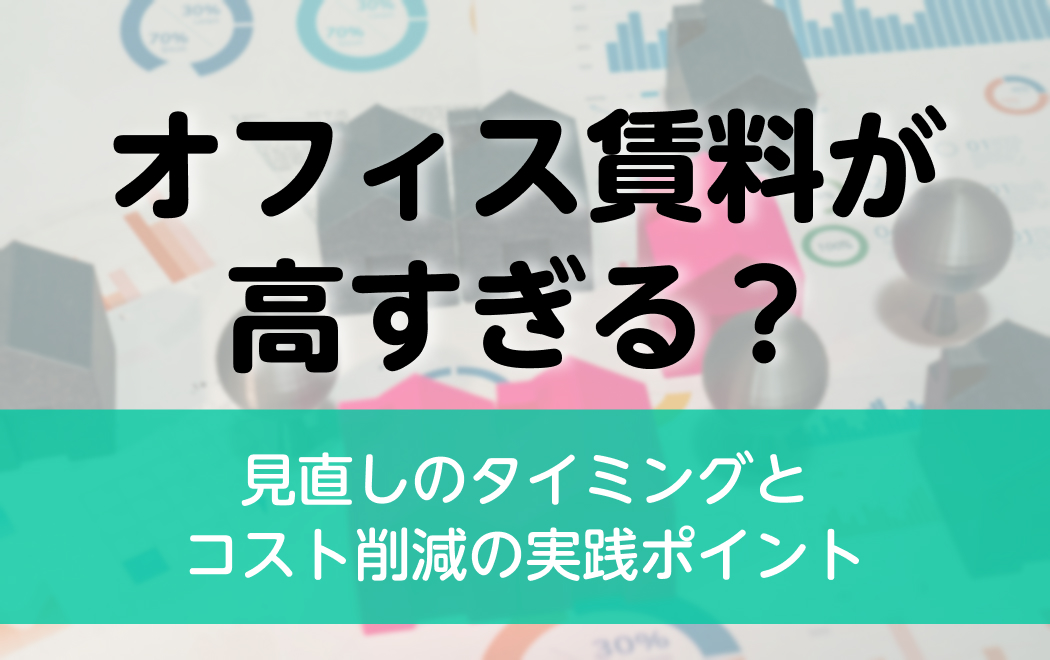

テレワークやハイブリッドワークが浸透する中、オフィス賃料の見直しを検討する企業が増えています。「広すぎる」「稼働率が低い」といった声は、もはや一部の話ではありません。
本記事では、オフィス賃料が高いと感じたときの見直しポイントを実務目線で詳しく解説します。都心の空室率が高止まりしている今こそ、最適な見直しのタイミングです。
オフィス賃料の適正を見極めるチェックリスト
3分でわかる!見直しすべきサインとは?
オフィス賃料の見直しは、感覚的な判断だけでは不十分です。
以下の5つのポイントに3つ以上該当する場合は、見直しのタイミングかもしれません。
- 同じエリアの相場より坪単価が高い
- 契約更新のタイミングが近づいている
- テレワーク導入後も広いスペースを維持している
- 会議室や執務室の稼働率が50%未満
- 共益費や原状回復費が高すぎる
例えば、2025年1月末時点での東京都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の平均募集賃料は28,953円/坪となっており、前年同月比で777円/坪上昇しています。
参考:いよいよ本格回復局面へ オフィスマーケット最新動向Ⅰ(野村不動産ソリューションズ)
①<2025年1月末>東京主要7区 大型オフィスビル空室率・平均募集賃料の動向
②【2025年1月末時点】東京主要7区 オフィスビル空室率・平均募集賃料調査
(三菱地所リアルエステートサービス)
オフィス賃料の目安や相場を解説した記事はこちら!
このような状況では、適正価格から乖離している可能性があります。オフィス賃料は「固定費」として見直しづらい項目ですが、実は削減余地が大きいコストの一つです。
賃料の内訳と仕組みを理解する
契約書に書かれた金額の“正体”を分解してみましょう。オフィス賃料は「坪単価 × 坪数」で計算されるイメージがありますが、実際にはそれだけではありません。
契約に含まれる費用の内訳を正確に把握することが、見直しの第一歩になります。
以下の表で、一般的な賃料構造とチェックポイントを確認してみましょう。
◆ 賃料の主な内訳項目と内容
| 項目 | 説明 | チェックポイント |
| 基準賃料(坪単価) | 面積あたりの基本賃料。契約書に明記される。 | 同エリア相場より高くないか? |
| 共益費・管理費 | 共用部(トイレ・廊下・エレベーターなど)の維持費 | 坪単価と合わせて比較する必要あり |
| 敷金・保証金 | 契約時に預ける担保金。退去時に一部返還される。 | 何か月分か?返還条件は明確か? |
| 更新料 | 契約更新時に支払う費用。旧来の慣習によるもの。 | 支払いが必須か?何年ごとか? |
| 原状回復費 | 退去時にかかる内装・設備の復旧費用。 | 「原状回復の定義」が契約に明記されているか? |
実際の負担額は「トータル」で考えることが大切
月額賃料だけでなく、共益費・更新料・原状回復費などを含めた「トータル賃料」を考えることが重要です。特に原状回復費は想定以上に高額になりやすく、トラブルや交渉の原因にもなります。
たとえば、同じ月額賃料でも「共益費が高い」「更新料が数年ごとに発生する」など、見落としがちなコスト項目が存在する場合もありますこれらの内訳を整理し、数値として見せることで、賃借人は賃料交渉に説得力を持たせることができます。
また、移転先を比較検討する際にも、「基準賃料だけで判断しない」姿勢が重要です。
ビズキューブ・コンサルティングでは工事会社40年の実績を基に、原状回復費の削減コンサルティングを実施しています。不要な工事が見積もりに含まれていないかチェックして、適正な工事費にすべく支援いたします。
無料の工事費診断も実施していますので、削減余地があるのかご相談ください。
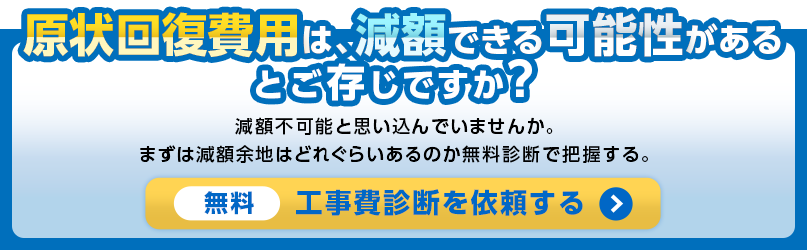
賃料削減を実現するための5つのアプローチ
今すぐ実行できる、実務に基づく実践的な手法とは?
オフィス賃料の削減は、単に「値下げをお願いする」ことではありません。
ポイントは、“論理的な根拠と複数の施策を組み合わせること”です。
以下に紹介する5つのアプローチは、すぐに取り組めて、交渉材料としても有効な手段ばかりです。
① 相場調査の徹底
まず最初に着手すべきなのが「相場調査」です。同エリア・同規模・同等スペックの物件の坪単価を調査することで、自社の賃料が適正かどうかの基準が明確になります。
相場情報は、不動産ポータルサイトや市況レポートなどで収集可能です。同じ駅圏内でも「築年数」「フロアスペック」「設備の有無」により大きく賃料は変動します。さらに、面積帯によって単価が異なるため、同じ100坪前後で比較することが重要です。
これらをリスト化し、「自社の賃料は坪単価で12%上回っている」など、定量的な材料に落とし込むことが交渉成功のカギとなります。
② 契約条件の精査と再交渉
賃料そのものだけでなく、契約書に記載された周辺コストにも削減の余地があります。
以下のような項目は見落とされがちですが、総コストに大きな影響を及ぼします。
- 原状回復費用の範囲と内容(天井や壁紙も含むか?)
- 更新料の有無・支払い頻度(2年ごと/4年ごとなど)
- 共益費や管理費が実態に合っているか(定額か按分か)
過去の契約では、明確化の余地がある条項が含まれている場合があり、よくわからないまま従ってきた」というケースが非常に多くあります。
更新前のタイミングを活かし、これらの条件について賃借人は「再交渉」の意思表示をすることで、単価の見直しにつながる可能性もあります。
また、交渉材料として“他の事務所物件の契約条件”を引き合いに出すと、話が進みやすくなります。
③ 稼働率・利用状況の見える化
広すぎるオフィスを使い続けていませんか?一部の企業では、日中の稼働率が50%未満のフロアを維持しているケースも見受けられます
ここで有効なのが、「利用実態の見える化」です。
具体的には以下のような方法があります。
- フリーアドレス化により実使用率をモニタリング
- 会議室やラウンジの予約ログ・使用実績データの集計
- 社内アンケートや行動観察をもとに使われていないゾーンを特定
これにより、「実際に使用しているのはこの●●坪だけ」といった定量的データが得られ、オフィスの縮小(面積ダウン)やレイアウト再設計の判断材料になります。
さらに、賃借人はこれを根拠に賃貸人と交渉することで、面積の再設定や一部区画返還の提案も現実味を帯びてきます。
④ フリーレント・インセンティブの活用
「賃料交渉は難しい」と感じる賃借人にとって有効なのが、“フリーレント(賃料無料期間)”の導入です。
これは、特に移転や再契約時に賃貸人側が提案してくることも多く、契約初月〜3か月分の賃料が無料になるケースがあります。
都心部の空室率が高い状況では、賃借人は「長期契約する代わりにフリーレントを要求する」交渉がしやすくなっているのが現状です。
また、賃貸人側が「フリーレントはできない」と回答する場合も、「内装費負担」「原状回復義務の軽減」「契約金の分割払い」などの代替インセンティブを提案してくる可能性があります。
要は、“価格以外で得られるメリット”を交渉材料にするのがこのアプローチのポイントです。
⑤ 移転・サブリース・ゾーニングの再構築
もし、今のオフィスでの交渉が難航している場合、思い切って移転を検討することも選択肢になります。
特に以下のような条件に当てはまる場合、移転によるコスト改善効果は高いです:
- 現在の立地が駅近ハイグレードで割高
- スペースを持て余している(稼働率50%以下)
- 原状回復や更新料が高額に設定されている
移転には一定の初期コストがかかりますが、「損益分岐点(何年で回収できるか)」をシミュレーションすることで判断が可能です。また、オフィス全体を移すのではなく、一部を他企業に貸し出す「サブリース」やシェア型の導入も有効です。
さらに、レイアウトのゾーニング設計を見直すことで、縮小移転をせずに“実質的なコストダウン”を実現することも可能です。
オフィス賃料交渉を成功させる3つのコツ
準備・根拠・タイミングが交渉成否を分けるカギになる
オフィス賃料は、実は交渉によって見直しが可能な“変動コスト”です。
しかし、交渉の場で何をどう伝えるか、どのタイミングで動くかによって、結果は大きく変わります。
ここでは、実際に多くの企業で成果を上げている賃料交渉の成功パターンを、3つの視点からご紹介します。
タイミングは「契約更新の6か月前」から逆算する
交渉の成功率を大きく左右するのが「いつ動くか」です。一般的にオフィス賃貸契約は2年または3年ごとの更新契約となっており、その直前になると賃貸人側も準備を進めています。したがって、最も効果的なのは「更新の6か月前」から動き出すことです。
この時期であれば、移転を含めた選択肢も現実的に残されており、賃貸人も譲歩するインセンティブが働きやすくなります。また、移転や契約見直しには時間がかかるため、スケジュールの余裕が交渉材料にもなります。
「相場+実態データ」でロジックのある交渉を行う
「高いから下げてください」という主張は、感情論にしかなりません。交渉では“根拠あるデータ”の提示が最重要ポイントです。
具体的には、以下のような材料を揃えて交渉に臨みましょう:
- 同一エリアの坪単価相場一覧(3〜5件)
- 現在のオフィス利用実態(稼働率・レイアウトなど)
- 将来的な利用計画(人数・面積変化など)
これらを「見える化」して提示することで、賃貸人側にとっても合理的な判断材料となり、話し合いの土台が整います。
加えて、移転候補物件の見積や条件表をあえて提示することで、「今のままでは維持が難しい」というメッセージを自然に伝えることができます。
具体的な代替案を持って交渉に臨む
最後のポイントは、賃貸人側に“本気度”を伝えることです。多くの賃貸人や管理会社は、「この会社はどうせ出ていかない」と感じており、表面的な交渉には応じにくくなっています。
そこで効果的なのが、「移転やサブリースも検討中」といった代替案を持って交渉に臨むことです。
実際にすぐ出て行く必要はありませんが、本気で他の物件と比較している姿勢を見せることが、賃料見直しの強力な後押しになります。
また、「移転しない代わりに、原状回復の範囲を縮小してほしい」「更新料を減額してもらえれば長期契約する」など、金額以外の譲歩条件で交渉余地を広げることも可能です。
【補足】賃借人が賃料交渉に失敗しやすいNGパターン(表形式)
| NG例 | なぜ効果がないのか |
| ただ「高いから下げて」と主張 | 根拠がないため、感情論に見られてしまう。交渉の土台にならない。 |
| 契約満了の直前に交渉を始める | 移転や他の選択肢を取る余地がなく、賃貸人に優位な交渉状況になる。 |
| 移転も視野に入れていない | 「どうせ出ていかない」と見透かされ、譲歩を引き出しにくい。 |
| 相場や利用実態の調査をせずに交渉 | 数値的根拠がなく、説得力が乏しくなる。 |
| 金額交渉だけに終始する | 更新料・原状回復など他の条件に目を向けないと、総コストは下がらない。 |
まとめ|オフィス賃料の見直しは今がチャンス
オフィス賃料は「固定費だから動かせない」と思われがちです。しかし実際には、相場調査や稼働率の見直し、交渉次第で大幅な改善が可能です。
特に2025年時点では、都心のオフィス空室率が高水準で推移しており、賃貸人側も柔軟な対応を求められている時期です。
自社の働き方とスペースの最適なバランスを見直すことで、コスト削減だけでなく、従業員満足度や生産性向上にもつながります。
ぜひこの機会に、オフィス賃料の見直しを経営戦略の一環として捉えてみてください。
ビズキューブ・コンサルティングでは、賃料適正化のパイオニア企業として、20年間積み重ねた経験に裏付けられたノウハウとデータベースを基に、お客様の現在の賃料が市場価格と比較して適正かどうかを診断します。診断サービスは無料で提供しておりますので、自社の賃料適正化を検討する際には、ぜひ利用してみてください。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。




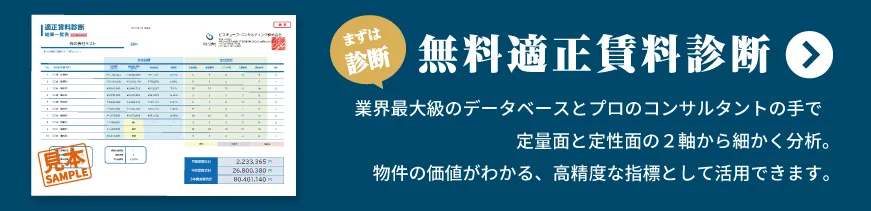






 人気記事ランキング
人気記事ランキング

