年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
賃料増額の通知が届いたら?企業がとるべき対応フローと判断ポイント
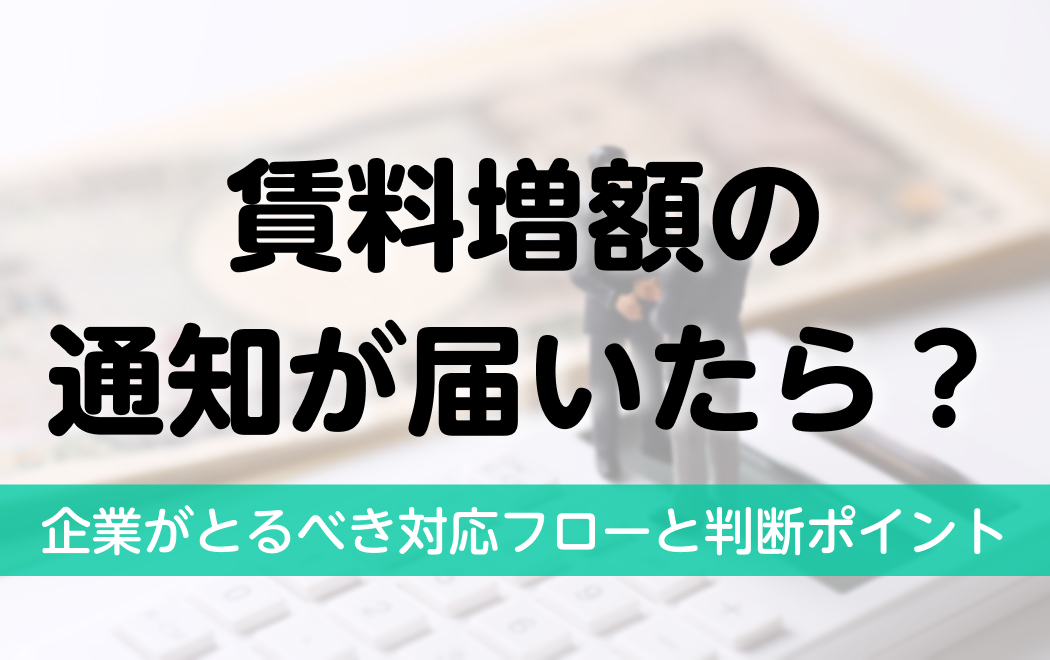
- 目次
賃料増額の通知はなぜ届く?背景と基本理解
賃料改定通知とは?貸主が増額を求める正式なプロセス
賃料改定通知とは、貸主が契約中の借主に対して「現行の家賃を引き上げたい」と申し出る正式な通知です。多くの場合、書面で通知され、改定希望日・新たな賃料額・増額理由が記載されています。この通知は一方的な値上げの決定ではなく、「賃料交渉の始まり」としての意味合いを持ちます。借地借家法に基づき、周辺相場や経済情勢の変化を背景に行われるもので、借主には協議や異議申立ての余地が認められています。通知を受けた時点で、冷静に対応を検討することが重要です。
借地借家法32条とは?賃料増額請求権の法的根拠
借地借家法第32条は、賃貸借契約期間中であっても「地代または家賃が経済事情や近隣相場と比べて不相当となった場合」に、貸主または借主が増額または減額を請求できる権利を定めた条文です。 この請求は、契約内容を一方的に変更するものではなく、相手方との協議や裁判手続きによって賃料の妥当性を判断してもらう仕組みです。正当な理由がある場合に限られ、過去の判例では「相場変動」「税負担の増加」「地域の商業価値の上昇」などが認められた例があります。
借地借家法の基礎知識や、店舗やオフィスの賃貸借契約にかかわる重要なポイントをわかりやすく解説しているこちらの記事もチェックしてみてください。
賃料増額に同意しなくても契約更新は可能?
普通借家契約の場合、賃料増額に同意しないことを理由に、契約更新を拒否されることは原則として認められていません。借地借家法では、賃料交渉と契約更新は別の判断軸であり、賃借人の保護が優先されます。
ただし、契約更新時に賃料改定を条件とする交渉が行われることはあり、「正当事由」がない限り、更新拒否は認められにくいとされています。契約書の更新条項や改定条項の記載内容を確認し、法的根拠に基づいた対応が必要です。
貸主が賃料増額を求める主な理由とは?
賃料改定通知は、貸主が「現行の賃料では不相当である」と判断した場合に発せられるものです。借地借家法第32条第1項では、契約期間中であっても、経済事情や近隣相場との比較により賃料が不相当となった場合、貸主・借主のいずれからでも賃料の増減を請求できると定められています。
ここでは、貸主が賃料増額を申し出る際に、実務上よく挙げられる背景について解説します。
1. 周辺相場との乖離
もっとも重視されるのが、同一エリア・同種物件との賃料相場と比較して、現在の賃料が明らかに低い場合です。たとえば、近隣物件の坪単価が大幅に上昇しているのに、契約賃料だけが据え置かれている場合などが該当します。実際の裁判でも、周辺相場のデータが証拠資料として重視されます。
2. 経済情勢・物価の変動
インフレによる物価上昇や、不動産価格・固定資産税の上昇といった経済的背景の変化も賃料改定の根拠となります。特に長期契約においては、契約当初の金額が現在の経済状況に合致していない場合に、改定の必要性が認められることがあります。
3. 建物・土地にかかる管理コストの上昇
共用部の修繕費用や管理人件費の増加など、物件を維持するためのコストが大幅に上がった場合も、賃料改定の理由となり得ます。実際には、修繕履歴や管理費明細が提出されるケースが多く見られます。
4. 賃借人の利用状況や支払能力
賃借人が長期にわたって契約を継続しており、安定した収益を上げている場合など、貸主が「契約条件の見直し」を求める背景となることがあります。ただし、賃借人の支払能力の高さだけでは、賃料増額の妥当性を裏付ける十分な根拠とは言えません。周辺相場や経済事情など、他の要素と合わせて総合的に判断される必要があります。
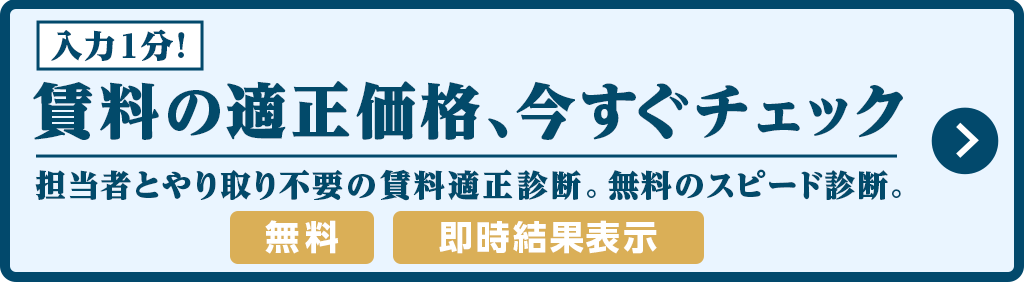
増額請求された企業側の判断ポイント
賃料の増額通知を受け取った際、企業として最初にすべきことは「すぐに応じるか否かの判断」ではなく、事実関係と法的根拠の確認、そして社内検討の準備です。感情的に反応したり、放置したりすることは、将来的な不利益や誤解を招く可能性があるため、慎重な対応が求められます。ここでは、通知に対して企業が行うべき具体的な確認・判断ステップを解説します。
賃貸借契約書の確認|定期借家契約か普通借家契約か
まず確認すべきは、現在の契約形態です。
最初に確認すべきなのは、現在締結している賃貸借契約が「普通借家契約」か「定期借家契約」かという点です。
| 契約形態 | 詳細 |
| 普通借家契約 | 原則として更新が前提の契約であり、契約期間中でも「正当な理由」があれば賃貸人は賃料の増額請求が可能です。ただし、相場や経済情勢などの合理的根拠が必要です。 |
| 定期借家契約 | 契約期間満了による終了が原則の契約で、途中の賃料改定は通常できません。ただし、契約条項に「賃料改定可能」や「再協議条項」がある場合は例外的に可能となることがあります。 |
この違いによって、賃貸人の請求に応じる必要性や交渉余地の範囲が変わってきます。契約書の中で特に注目すべきは、「賃料改定条項」「更新条項」「増額条件の記載」の有無です。加えて、書面の有効性や署名捺印の状態など、形式面の整合性も確認しましょう。
定期借家について詳しく説明しているこちらの記事もご確認ください。
改定額の妥当性を見極めるには?相場調査のやり方
通知で提示された賃料が妥当かどうかを判断するには、同条件下の「近隣物件の相場」との比較が不可欠です。以下のような調査を通じて、客観的な判断材料を整えましょう。
| 調査方法 | 詳細 |
| 近隣物件の坪単価情報を収集 | 立地、築年数、面積、設備のスペックが近い物件を選定し、相場データを把握します。 |
| 不動産会社・コンサル・鑑定士へのヒアリング | 現場感のある相場観を得るには、プロの視点が有効です。可能であれば、不動産鑑定評価書の取得も交渉材料になります。 |
| 商業用不動産サイトの活用 | 募集情報や成約事例から、近隣エリアの賃料傾向を確認 |
調査により、相場より明らかに高い賃料が提示されていた場合、「根拠資料の提示を求める」ことや賃借人は「再交渉を申し出る」ための土台ができます。裏付けのない金額改定には応じる必要はなく、むしろ根拠の提示を丁寧に求めることで、建設的な交渉の姿勢を示すことができます。
通知内容に不備はないか?文書チェックポイント
通知文の内容も非常に重要です。形式や記載事項に不備がある場合、その通知自体の効力や交渉の前提が揺らぐ可能性があります。
次の点を中心にチェックしましょう。
| チェックポイント | 詳細 |
| 通知日と発信者情報 | 送付された日付、発信者名、連絡先が明記されているか。 |
| 改定後の賃料と実施予定日 | 改定金額が明示されているか、いつから適用したいのかが明確か。 |
| 改定理由の記載 | 物価の変動、固定資産税の増加、周辺相場の上昇など、根拠が具体的に書かれているか。 |
| 合意前提での改定であるか | 借主が明確に同意しない限り、通知だけで自動的に増額されるわけではありません。にもかかわらず、「◯月から自動的に適用されます」などと記載されている場合は要注意です(黙示の承諾を狙った記述と見なされる可能性あり)。 |
口頭での通知しかない場合や、内容が曖昧な場合には、「正式な書面による通知をお願いしたい」と書面で依頼するのが安全です。対応を曖昧にしたまま放置すると、意図せず“合意済み”とされるリスクがあるため、早期に文書の確認・整理が必要です。 このように、賃料増額通知を受けた段階での初期判断には、契約内容の精査・賃料相場の把握・通知書面の妥当性チェックの3点が極めて重要です。いずれも社内法務部門や経営層と連携しながら慎重に進めることが、後の交渉を優位に進める基盤となります。
賃料増額の通知を受けたときの対応手順
対応フロー①:社内での初期対応と意思決定プロセス
賃料増額の通知を受けたとき、企業がまず取るべきステップは、情報を整理し、事実と契約内容を正確に把握することです。この初動対応を誤ると、交渉で不利になったり、意図せぬ合意が成立したとみなされる可能性があります。社内での判断と体制づくりが、以降の交渉の質を大きく左右します。
1. 初動対応|社内法務・総務・経営層への連絡
通知を受領したら、まず担当者レベルで止めずに、法務部・財務部・総務部・経営層などの関連部署へ速やかに共有します。共有時には以下のような観点をセットで伝えるのが効果的です:
- 通知書の原本またはスキャンコピー
- 賃料改定額・時期・理由などの要点整理
- 緊急性の有無(次月適用の可能性等)
この時点で「対応方針はまだ未定」であっても、関係部門に早めに認知させておくことが極めて重要です。
通知を黙殺してしまうと、場合によっては「黙示の承諾(受諾したとみなされる)」と解釈されるリスクがあり、既成事実化される前に動くことがトラブル回避の鍵となります。
2. 賃料改定提案の稟議・検討資料作成
次に行うべきは、通知内容の精査と影響分析に基づく稟議資料の作成です。経営層に対して「改定に応じるべきかどうか」を判断してもらうために、以下のような資料を整えると効果的です。
| 準備すべき資料 | 詳細 |
| 通知内容と現行契約書の比較表 | 改定前後の賃料・契約条件を一覧化。更新時期・条文の文言もあわせて整理。 |
| 相場調査結果の概要 | 周辺相場との比較、坪単価の推移、業種特性との整合性など。必要であれば不動産鑑定士の意見書も添付。 |
| 事業計画・収支シミュレーションへの影響 | 新賃料適用後の営業利益や販管費率への影響を、数字で可視化。店舗損益・本社運営費への波及効果を明示。 |
| 契約更新・移転・撤退などの代替案の整理 | 交渉決裂時のバックアッププランも提示することで、意思決定の幅を広げる。 |
こうした資料を整備することで、経営層が感情論ではなく「事業合理性」に基づいて判断を下すためのベースが構築されます。
3. 異議のある場合は?通知への対応方針の確定
検討の結果、「提示された賃料では受け入れがたい」という結論に至った場合は、ただ放置するのではなく、賃借人は必ず書面で“意思表示”を行う必要があります。
通知への回答は、単なる否定ではなく、以下のような交渉の余地を含んだ表現が推奨されます。
>「賃料増額通知を拝受いたしました。貴意は理解いたしますが、当社といたしましては、現時点で提示額の妥当性に一定の疑問があり、今後、条件等について協議を希望いたします。」
このように記載することで、賃借人は交渉においては、拒絶ではなく協議の意思を示すことで、関係の維持と円滑な対話につながります。また、可能であれば「相場との乖離資料」や「収支への影響分析」を添付し、論理的な主張に基づく交渉の流れに持ち込むことが重要です。
このように初動段階では、
①全社的な連携
②判断材料の可視化
③早期の意思表示
がカギを握ります。
“放置しない”“単独判断しない”“資料と数字で判断する”という3原則を意識することが、賃借人の賃料交渉を優位に進めるための礎となります。
4. 賃料増額通知を放置するとどうなる?
通知を無視した場合、法的には「黙示の承諾」とみなされる可能性があります。特に、通知に「◯月から自動的に適用」といった記載がある場合、沈黙=同意と解釈されるリスクが高まります。
そのため、通知を受け取ったら、必ず書面で意思表示を行うことが重要です。放置は交渉の機会を失うだけでなく、後の異議申立てが困難になる可能性があります。
対応フロー②:賃貸人との交渉・連絡・協議

1. 賃借人の交渉スタンスの明確化(合意・協議・拒否)
通知内容と社内検討の結果を踏まえて、企業側は明確な交渉スタンスを確立する必要があります。主に以下の3つの選択肢から方針を定めます。
| 選択肢 | 例 |
| 提示された増額条件をそのまま受け入れる | 経済合理性がある、契約上の制約がある等 |
| 一定の条件変更を求めて交渉を行う | 増額幅の縮小、分割適用、フリーレント対応等 |
| そもそも賃料増額自体に異議を唱える | 相場と乖離している、正当理由がない 等 |
これらの立場を明文化し、回答書や面談の場で賃貸人に対して誠実かつ明確に意思表示を行うことが重要です。回答が遅れると、相手に「沈黙=承諾」と解釈されかねません。
2. 賃貸人への伝え方・文例の工夫
賃料交渉では、回答文のトーンが交渉の成否を左右することがあります。否定や拒否の意図がある場合でも、対立姿勢ではなく協議の意思を示す表現が基本です。たとえば、以下のような文面は、誠実な姿勢を伝えつつ、協議の余地を残すことができます。
>「ご通知を拝受いたしました。賃料改定のご提案につきまして、社内にて検討いたしましたが、現時点においては当社として妥当性に疑義があると考えております。つきましては、今後の条件等について、協議の機会を頂戴できれば幸いです。」
このような表現により、相手に「対話可能な交渉相手である」という印象を与え、関係を悪化させずに協議フェーズへ移行することができます。
3. 賃料交渉に使える回答書の構成例
回答書を正式に作成する際は、以下のような構成で整理すると、相手に誠実かつ論理的な印象を与えやすくなります。社内稟議や法務確認にも活用しやすい形式です。
| 構成例 | 内容 | 詳細 |
| 件名 | 賃料改定通知への回答 | 件名は文書の目的を明確にするために必須。例:「賃料改定通知に関するご回答」など。 |
| 宛名 | 賃貸人名・会社名 | 通知を送ってきた相手の正式名称を記載。会社名・担当者名が分かれば明記。 |
| 通知内容の受領確認 | 通知を受け取ったことを明記 | 「◯月◯日付の賃料改定通知を拝受いたしました」など、受領日と通知内容を簡潔に記載。 |
| 社内検討の結果と現時点の見解 | 検討した旨と立場の表明 | 「社内にて慎重に検討いたしましたが、現時点では妥当性に疑義があると考えております」など。 |
| 協議の希望と今後の対応方針 | 協議の意思を示す | 「条件等について協議の機会をいただけますようお願い申し上げます」など、対話の姿勢を明記。 |
| 担当者名・連絡先・署名 | 企業側の窓口情報 | 担当部署・氏名・電話番号・メールアドレスなどを記載。署名・社印が必要な場合もあり。 |
この構成をベースに、社内での承認プロセスや賃貸人への正式回答に活用することで、交渉の土台を築きやすくなります。
4. 第三者の介入も検討を(不動産コンサル・弁護士)
賃料交渉が複雑化する場合や、相手が大手デベロッパー・資産運用会社など交渉慣れしている場合は、専門家のサポートを受けることで状況が一変します。
| 依頼先 | 強み |
| 不動産コンサルタント | 周辺相場・市場動向・契約条件に関する交渉材料を論理的に提示可能。 |
| 弁護士(借地借家法に精通) | 通知の法的妥当性、契約条項の効力、訴訟への備えなどを助言。 |
特に交渉が平行線になりそうな場合や、複数テナント間での一律改定が行われているようなケースでは、第三者の視点が「客観性」と「説得力」を持たせる武器になります。
合意に至らなかった場合の流れ
賃料改定通知を受けたあと、貸主との交渉がどうしても折り合わない場合、どのような展開があり得るのかを知っておくことは、借主にとっても重要です。ここでは、実務上よく見られる流れを紹介します。貸主がすぐにこれらの手段を取るわけではありませんが、貸主側がどのような対応を検討する可能性があるかを理解しておくことで、冷静な判断につながります。
調停や訴訟に進む可能性
交渉が難航し、合意に至らない場合、貸主が法的手続きに進むことがあります。主な選択肢は以下の通りです。
| 手段 | 詳細 |
| 調停の申立て | 不動産調停委員会等を活用し、公的立場を交えて妥協点を模索。 |
| 裁判所への賃料増額請求訴訟 | 双方が合意に至らない場合、最終的に裁判所が妥当な賃料を決定する。 |
ただし、訴訟には相応の費用・時間・リスクが伴うため、貸主側も安易に選択せず、調停や再交渉を優先するケースも見られます。
判例上の流れと所要期間
実務上、増額請求に関連する訴訟は、提起から判決まで半年から1年程度を要します。さらに控訴審に発展することもあり、長期化すれば弁護士費用などもかさみます。
また、判決が出た場合でも「妥当な中間水準」に落ち着くケースが多く、貸主・借主のどちらも完全に満足する結果とは限りません。そのため、判例上も“最終手段”として位置づけられています。
まとめ|通知が来ても慌てず冷静に、段階的に対応を
賃料増額の通知を受けた場合、感情的に反応してしまうのではなく、冷静かつ段階的に対応することが企業としてのリスク管理になります。
基本ステップは以下の4段階です
- 契約書の確認(条項・契約形態の把握)
- 相場調査による根拠の確認
- 社内の対応方針と交渉スタンスの決定
- 回答書・面談による丁寧な交渉開始
これらのプロセスを経て、最終的な判断を下す際には、外部の専門家の力も積極的に活用し、法的リスクや将来の経営負担を最小限に抑える視点が求められます。
賃料の増額は、一方的に決定されるものではなく、原則として賃借人との協議や相場との整合性が求められる手続きです。対応を誤らなければ、企業にとって有利な結果に導くことも十分に可能です。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化の分野で20年以上の実績を持つ専門企業です。これまでに累計35,558件の賃料削減を支援し、総額2,349億円のコスト削減を実現してきました。こうした経験と独自のデータベースを活用し、現在の賃料が市場価格と比べて適正かどうかを無料で診断しています。
自社の賃料が妥当かどうかを確認したい場合は、ぜひ賃料適正診断をご活用ください。
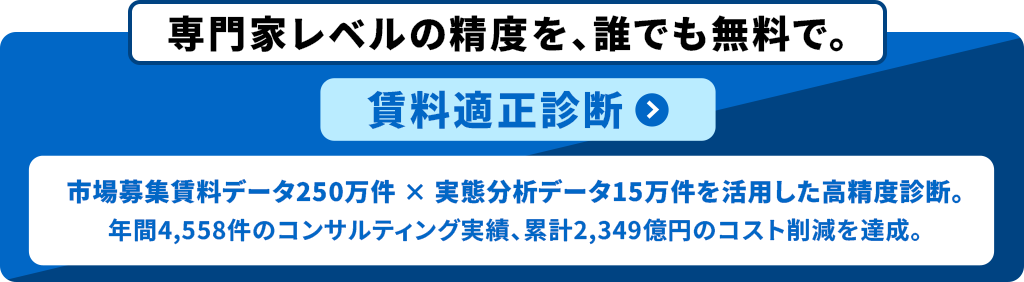
よくある質問(FAQ)
Q:賃料増額の通知は無視しても問題ないですか?
A:通知を放置すると、法的に「黙示の承諾」とみなされる可能性があります。特に通知文に「◯月から自動適用」といった記載がある場合は注意が必要です。意図しない合意とされないよう、必ず書面で意思表示を行うことが重要です。
Q:相場より高いと感じたらどうすればいいですか?
A:まずは、近隣物件の賃料相場や第三者による評価(不動産鑑定士など)を調査し、具体的な根拠をもとに交渉を申し出ることが有効です。感覚的な印象ではなく、客観的なデータを提示することで、交渉を有利に進めやすくなります。
Q:対応を誤ると訴訟に発展することはありますか?
A:交渉がまとまらない場合、賃貸人が裁判所に賃料増額請求訴訟を起こす可能性はあります。ただし、実務では調停や協議による解決が優先されるケースが多く、訴訟は最終手段とされています。初期対応を丁寧に行うことで、訴訟リスクを低減できます。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。












 人気記事ランキング
人気記事ランキング

