年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
店舗の定期借家契約|メリット・デメリットと普通借家との違いを解説
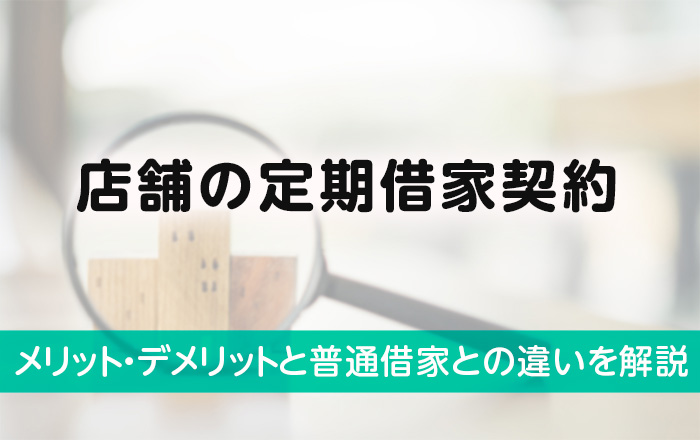
- 目次

定期借家契約は、期間を限定している更新のない賃貸借契約です。定期借家契約を検討している経営者や店舗マネージャーの中には、以下のような悩みを持つ方も多いでしょう。
- コストを抑える可能性がある契約を結びたい
- 定期借家契約と普通の契約の違いを知りたい
- 定期借家契約のメリットとデメリットを把握したい
定期借家契約はコスト削減に有効ですが、特有のリスクも伴います。
本記事では、定期借家契約のメリット・デメリット、契約前に知っておくべき注意点を詳しく解説します。適切な賃貸契約の締結にお役立てください。
定期借家契約とは

定期借家契約とは、あらかじめ定められた期間だけを対象とする賃貸借契約です。
定期借家契約は家賃が比較的安価な点が魅力ですが、賃貸人の合意がない限り場合は期間終了後の再契約ができない、中途解約が原則として認められないなど、いくつかの制約があります。一方、普通借家契約は契約期間が満了しても、賃借人が希望する限り更新が可能です。
次の表では、定期借家契約と普通借家契約を比較します。それぞれの特徴を考慮し、店舗・テナントの適切な契約を選びましょう。
| 項目 | 定期借家契約 | 普通借家契約 |
| 契約の流れ | 「更新なし、期間の満了により終了」の旨を説明し、書面にも明記 | 文書または口頭で契約 |
| 更新 | 原則不可(再契約なら可能な場合がある) | 賃借人の意向で更新可能 |
| 中途解約 | 原則不可(特約での合意が必要) | 契約に従い解約予告後に可能 |
| 賃料の増額・減額請求 | 請求できるが、特約に請求できない旨の記載があれば不可 | 契約に基づき請求可能 |
賃貸人が定期借家契約で店舗を募集する主な理由
定期借家契約を採用する賃貸人サイドの理由を知っておくと良いです。賃貸人が定期借家契約で店舗を募集する主な理由は次の4つです。
それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
理由その1:貸出できる期限が決まっている
賃貸人は、貸出できる期限が決まっている場合、定期借家契約を選ぶケースがあります。
具体的には建物の老朽化や再開発計画が進行中で、将来的に取り壊しが確実な場合などです。長期で借りたい店舗・テナント物件は、賃貸期間が決まっている物件を選択肢から外します。
建物の利用期間が限られている場合は、賃貸人は空き物件を避けるために安価な条件で賃貸することが多く、定期借家契約が有効とされます。
理由その2:何年か後に貸出できなくなる可能性がある
確定ではないものの、何年か後に貸出できなくなる可能性がある場合、賃貸人にとって定期借家契約が有効です。
例えば、将来的に物件を売却する計画があるが、具体的な時期が確定していない状況では、契約終了時に更新の必要のない定期借家契約が有効です。定期借家契約であれば、契約期間の更新について話し合うことなく契約は終了となります。賃借人が希望した場合、賃貸人の合意があれば再契約を結べるので、賃貸人のリスクはおさえられます。
定期借家契約は、柔軟に対応できるため、期限が不確定な物件に適しています。
理由その3:マナーの悪い入居者の更新を避けたい
マナーの悪い店舗や入居者の更新を避けるために、定期借家契約を採用しているケースがあります。
普通借家契約の場合、賃借人がマナーを守らない状況でも、用法義務違反など正当な理由がなければ退去を要求することは困難な場合があります。しかし、定期借家契約では契約期間が満了した場合は、自動的に契約が終了し、立ち退き料の支払いも不要になることがあります。
問題のない店舗や賃借人であれば、賃貸人は再契約を認めることもできます。
理由その4:テナント物件を賃貸人側でコントロールしたい
賃借人を賃貸人側でコントロールしたい場合、定期借家契約が適していると思われます。
ビル全体のコンセプトが変わる可能性がある場合、定期借家契約を利用することで、賃貸人はテナント物件の方向性を調整できます。特に商業施設や繁華街のビルでは、流行や市場の需要に応じてテナント物件を定期的に更新し、施設の魅力を維持することが重要です。
定期借家契約では不適合なテナント物件との契約を更新せずに済み、不動産価値を高める新しいテナント物件を迎えることに注力できます。
定期借家契約の店舗側のメリット

定期借家契約の店舗側のメリットは次の4つです。
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
メリットその1:賃料が相場に比べて安い
定期借家契約の賃料は、一般的な普通借家契約の相場よりも安く設定されていることが多いです。家賃が安いのは、定期借家契約では期限が決まっている、原則更新ができないなどの条件が定められている場合、市場相場の賃料なら賃借人は避ける可能性が高いからです。
定期借家契約の物件は、契約終了時の退去が前提となりますが、スタートアップや期間限定の事業、もともと元々短期間での移転を計画している賃借人にとっては魅力的です。
店舗の家賃相場について詳しく知りたい方は次の記事をチェックしてみてください。賃料の適正化について詳しく解説しています。
メリットその2:短期間の契約が可能である
定期借家契約は、最低期間が定まっていないことが多く、短期間の契約が可能です。
通常の普通借家契約では、最低でも1年以上の契約期間が必要ですが、定期借家契約では数ヶ月といった短期間での契約が許容されることがあります。プロジェクトベースでの事業や期間限定のイベントなど、短期間だけ特定の場所で活動を行いたい企業にとって有効です。
短期間での契約が可能であるため、賃借人は長期的な賃貸契約による縛りを避けられ、柔軟な事業運営が可能です。
メリットその3:審査基準が低く入居しやすい
定期借家契約は、普通借家契約に比べて入居審査の基準が低く設定されていることが多く、入居しやすい傾向にあります。
定期借家契約は、契約期間が限定されているため、賃貸人にとってリスクが比較的少なく、入居後の長期にわたるリスクが少ないです。そのため、賃貸人は支払い能力や過去のトラブル歴などについて厳しく審査する必要がなく、入居時の審査が通りやすい傾向にあります。
審査の通り易さは、特に新しい事業者や若手起業家にとっても利点となり得るため、定期借家契約が好まれる場合があります。
メリットその4:更新料が発生しない
定期借家契約は、更新がなく、更新料も発生しないというメリットがあります。
通常、普通借家契約の店舗物件では2年ごとに賃料1ヶ月分相当の更新料が必要です。一方、定期借家契約では契約期間が満了すると自動的に終了するため、更新料のような追加費用がかかりません。
所定の期間内で事業計画を立てている事業者にとって安心材料になります。
定期借家契約の店舗側のデメリット
定期借家契約のメリットだけでなく、デメリットも見ていきましょう。定期借家契約の店舗側のデメリットは次の4つです。
それぞれのデメリットを詳しく解説します。
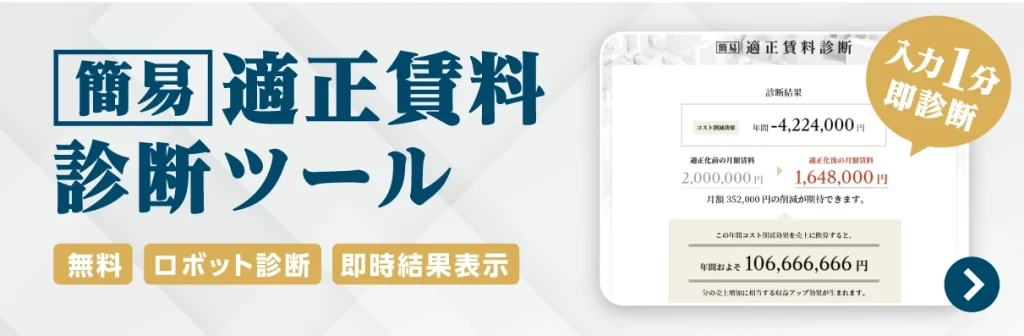
デメリットその1:原則として更新できない
定期借家契約のデメリットは、原則として契約が更新できないことです。
定期借家契約では、契約期間が満了すると自動的に終了し、賃借人は物件から退去する必要があります。ただし、両者の合意があれば再契約は可能ですが、賃貸人の裁量に依存し、賃借人には権利がありません。
契約を継続できるかわからない点は、事業の安定性や計画性に影響を与えるため、定期借家契約を選択する際は慎重に検討する必要があります。
デメリットその2:原則として途中解約できない
定期借家契約は、原則として途中解約が認められないため、経営状況が悪化しても契約期間が満了するまで賃料の支払いを続けなければならない場合があります。
新規事業や不安定な市場環境で活動する賃借人にとってリスクが高いと言えます。ただし、契約時に特別な条項を設けている場合は解約できる場合もありますが、多額の違約金が発生する可能性があります。
定期借家契約では事業の将来性を慎重に評価し、契約期間内は事業を継続する覚悟が必要です。
デメリットその3:再契約の場合は通常の更新よりも費用がかかる可能性がある
定期借家契約では、更新はできませんが、再契約が可能な場合があります。定期借家の再契約は、新たに契約を結ぶことになるため、初期の入居時と同様に礼金や保証金などの追加費用が発生することがあります。
また、再契約の際には市場の経済状況に応じて賃料の再評価が行われることが多く、賃料が増額されるなど、条件が前回の契約時より不利になることもあるでしょう。
デメリットその4:特約次第で賃料の減額請求できない可能性がある
定期借家契約では、賃料の減額請求ができない特約が設定されている場合があります。
普通借家契約では、市場の賃料相場に基づき、契約期間中でも賃料の減額請求が可能です。しかし、定期借家契約において特約で「賃料の減額を行わない」と明記されている場合、その請求ができなくなります。周辺の賃料相場が下がった場合にも、不当に高い賃料を支払い続ける可能性があるリスクを負うことを意味します。
契約前には特約の内容を十分に確認し、場合によっては専門家の意見を求めることが望ましいです。
定期借家契約でも賃料を減額できない旨の特約がない場合は、賃料を減額請求できる可能性があります。賃料減額請求に興味がある方は、次の記事もチェックしてください。賃料減額請求できる場合の法的根拠も解説しています。
定期借家契約の締結前におさえておきたい注意点
賃料が安いからという理由で安易に定期借家契約を締結するのは避けましょう。定期借家契約の締結前に確認しておくべきことは次の5つです。
それぞれの注意点を詳しく解説します。
注意点その1:定期借家契約の理由
定期借家契約を選択している理由を貸主や不動産会社に確認しておくことが重要です。
理由によっては契約の延長が完全に不可能である場合もあれば、条件次第で延長が可能な場合もあります。不動産会社が契約内容について曖昧な回答をしている場合は、言いにくい特殊な理由があるかもしれないため、さらに詳細を求めるか慎重な検討が必要です。
適切な情報を事前に把握することで、将来的なトラブルや不都合を避けることが可能になります。
注意点その2:再契約できるか
定期借家契約は原則として更新が認められていませんが、再契約の可能性があるかを確認することは重要です。
再契約が認められるかどうかは、物件によって異なります。例えば、賃貸人が建物の老朽化や取り壊し計画のために定期借家契約を選んでいる場合、再契約は難しいでしょう。一方で、過去に賃借人とのトラブルがあったために定期借家契約を採用している場合、マナーを守っていれば再契約の余地がある可能性があります。
契約前に不動産会社や賃貸人に再契約の可否や条件、実際に再契約を結んでいる事例があるかを詳しく尋ねることが、後々のトラブル回避につながることもあります。
注意点その3:途中解約できるか
定期借家契約は、原則として契約期間中の途中解約は認められませんが、特約を通じて途中解約が可能な場合もあります。
経営状況が変わる可能性がある賃借人や、不確実な市場環境にある事業者にとっては、途中解約の可否が事業のリスク管理に影響します。
- 途中解約の特約が含まれているか
- 解約の条件には何が含まれるのか
- 解約時に必要な違約金はいくらになるのか
契約を結ぶ前に、このような具体的な内容を理解し、契約書に明記されていることを確認しましょう。
注意点その4:賃料の減額請求ができない特約があるか
定期借家契約では、契約の特性上、賃料の減額請求ができない特約が設定されている場合があります。
契約を結ぶ前に、賃料の減額が可能かどうかを確認することが重要です。特に経済状況が変化して市場の賃料相場が下がった場合や、他の理由で賃料の見直しが必要になった際に、賃料の減額請求ができるかは大事なポイントです。
契約書に賃料の減額を請求することができない旨の条項が含まれている場合は慎重に契約を進めるべきです。減額請求が可能な場合でも、条件や手続きを確認しておくと良いでしょう。
注意点その5:契約書への記載内容・終了の通知
定期借家契約を結ぶ際には、契約書に「定期借家契約書」と明記されているかを確認することが重要です。契約期間終了については、契約期間の終了前1年から6ヶ月の間に賃貸人からの通知が行われなければ、普通借家契約と見なされる場合があります。
契約書には以下の内容が詳細に記載されている必要があります。
- 契約期間
- 更新の有無
- 途中解約に関する特約
記載が不明瞭だと、契約の法的な扱いが変わり、不測のトラブルにつながる可能性があります。契約書の内容をしっかりと確認し、終了の通知についても賃貸人と明確に合意しておきましょう。
契約前に専門家への相談も検討

賃料が市場相場より安いという理由だけで定期借家契約を締結するのは注意が必要です。
定期借家契約は、通常の普通借家契約と異なり、契約終了時の更新のないことや特定の条件下でのみ途中解約が可能など、多くの特殊な条項が含まれています。複雑な内容を適切に理解し、自分の状況に最適かどうかを判断するためには、専門家の意見を求めることも時には必要です。
賃料の適正化をはかりたい場合は、専門的なコンサルティングを活用することが有効です。気になる方は賃料適正化コンサルティングについてまとめた記事を参考にしてください。
定期借家契約の店舗物件は良し悪しを見極めて締結しよう
定期借家契約の店舗物件は、期限が決まっているものの、賃料を安くおさえるために有効です。しかし、更新できない、中途解約できない、など注意が必要です。
本記事では定期借家契約のメリットとデメリット、契約前の注意点を詳しく解説しました。定期借家契約の良し悪しを見極めて、適切な店舗物件の選定にお役立てください。
賃料減額交渉のためには、賃料の適正価格を診断することが有効です。次のサイトでは、無料で賃料適正価格診断が可能です。賃料の適正価格を判断したい方は、ぜひ活用してみてください。
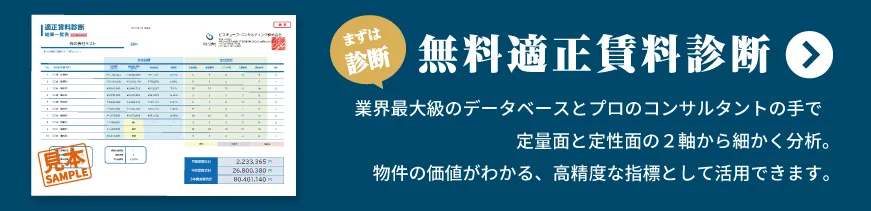
今の賃料が「安い」「適正」「高い」でハッキリわかる
【無料】実態分析賃料データ15万件分を駆使した高精度な賃料適正診断
店舗・事務所・オフィスなど、幅広くご対応いたします。
クライアント企業 全3,593社うち上場企業400社以上
累計削減件数 35,000件以上

【監修者】幸谷 泰造(弁護士)
東京大学大学院情報理工学系研究科修了。ソニー株式会社で会社員として勤めた後弁護士となり、大手法律事務所で企業法務に従事。一棟アパートを所有する不動産投資家でもあり、不動産に関する知識を有する法律家として不動産に関する法律記事の作成や監修、大手契約書サイトにおいて不動産関連の契約書の監修を行っている。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。













 人気記事ランキング
人気記事ランキング

