年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
賃料の値上げは拒否できる?店舗・オフィスが知るべき判断基準&交渉術を解説

- 目次

不動産の賃貸人から賃料増額請求は、賃料が周辺と比較して不相当に高い場合には、賃料増額請求を拒否する権利があります。賃料が値上がりする理由、賃借人は交渉する際のポイントについて理解しておきましょう。
本記事では、以下の悩みを抱える店舗経営者向けに解説しています。
- 賃料交渉のポイントは?
- 賃貸人が賃料を増額する理由は?
- 店舗の賃料が増額した際の対象方法は?
賃料の値上げは、店舗経営に大きな影響を与えます。賃料が値上げされ困っている経営者は、参考にしてください。
賃料の増額は拒否できる
不動産の賃貸人から賃料の増額請求は拒否できる場合もあります。なぜなら、賃料の値上げは賃貸人側と賃借人側でお互いの合意が必要だからです。ただし、賃料が周辺の賃料と比較して不相当に低廉である場合には、拒否しても増額が認められてしまう場合もあります。
賃借人側は、賃料の値上げを拒否する選択肢があることを、理解しておきましょう。ただし、拒否する際には、賃料相場より高い金額である、増額の理由が私的であるなど、客観的に否定できる根拠が必要です。
値上げを避けたいという理由だけでは、正当性に欠けるので、不動産の賃貸人にも納得してもらえるような資料やデータを用意しておきましょう。
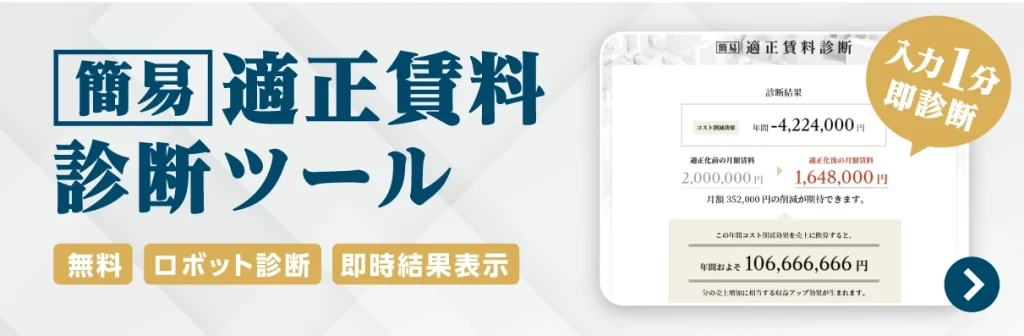
賃料の増額通知が来た際の対応
賃料の増額通知が来た際の対応は、以下の5つです。
賃料の増額通知が来た際の対応をあらかじめ理解しておくことで、増額通知が来た際に慌てることなく、対応できるようにしましょう。
① 賃貸人からの通知書を読む
対応の1つ目は、賃貸人からの通知書を読むことです。賃貸人側は、言った言わないを避けるために賃料の増額を書面で通知します。
届いた通知書を確認するポイントは、以下のとおりです。
- 改訂後の金額
- 賃料の値上げ理由
- 送付者の名前・連絡先
- 賃料の値上げ開始日
あらかじめ上記の4つを確認しておくことで、対応の流れがスムーズになります。この4つは、値上げを了承するかどうかの判断材料になるため重要な情報です。
もし、疑問点や不明点があれば、必ず不動産の賃貸人に確認しましょう。異議なく合意してしまうと、自分に不利な条件下での契約となり、トラブルの原因になります。
② 契約内容を確認する
対応の2つ目は、契約内容を確認することです。契約によっては、一定の期間は賃料を値上げしない旨の特約が含まれている場合もあります。
賃料の値上げをしない特約を結んでいるのであれば、応じる必要がない場合もあります。借地借家法32条により、一定の条件を満たすことで賃料の増減が認められています。しかし、増額しない旨の特約がある場合は認められないこともあります。
特約が優先され、定められた期間中は、賃料の値上げができません。そのため、契約書に特約の記載がないか、あらためて確認してください。もし、特約に賃料の値上げを1年間しないと記載があれば、特約を理由に賃料の値上げを拒否できます。
賃貸借契約を結んでから、時間が経ち内容を忘れている可能性もあるため、賃料の値上げ通知が届いた際は、通知書と合わせて契約書の内容も確認しましょう。
③ 周辺の賃料相場を調べる
対応の3つ目は、周辺の賃料相場を調べることです。賃料の値上げを要求する基準の1つに、周辺の賃料相場と比較して、契約中の店舗の賃料が低い可能性があることが挙げられます。周辺店舗の賃料相場を調べることで、賃料が適正であるのか、割安もしくは割高であるのか判断ができます。
仮に賃料相場を調べた結果、現在の賃料が相場より高い場合、値上げを拒否できる材料の1つになるでしょう。また、賃料相場は自分の主観感情ではなく、値上げを拒否する客観的なデータとして提示できるため、周辺の賃料相場を調べることをおすすめします。
店舗の賃料相場について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
④ 賃料の増額が妥当か検討する
対策の4つ目は、賃料の増額が妥当か検討することです。賃料の値上げには、賃料が不相当になったことが必要になります。
不相当となる事情には、以下の3つが挙げられます。
- 設備投資など維持管理費の増加
- 固定資産税など税金の値上がり
- 建物の老朽化による修繕費の増加
賃料を増額するには、上記のような客観的に賃料の値上げが必要であると、判断できる理由が必要です。どのような背景で賃料の値上げに踏み切ったのか、その背景は適切であるか検討しましょう。
検討の結果、賃料の値上げが妥当であると判断すれば受け入れ、もし妥当ではないと判断すれば、不動産の賃貸人に反対する旨を伝えてください。
一方的に値上げを拒否するだけでは、不動産の賃貸人に拒否した理由を理解してもらえません。値上げを拒否する際には、どの点に納得がいかないのか明確に伝えられるようにしましょう。
⑤ 賃料の交渉を行う
対応の5つ目は、賃借人が賃料の交渉を行うことです。1〜4の対応をした結果、賃料の増額に納得いかない場合、不動産の賃貸人と交渉することになります。賃料の増額には、借地借家法の規定が適用される場合を除いて、お互いの合意が必要です。一方的な値上げは契約違反となる可能性があります。
値上げを拒否する際には、賃借人側は一方的な拒否ではなく、交渉する意思があることを示しましょう。
不動産の賃貸人からの連絡を無視する、賃料の支払いを拒否するなどの行為は、不動産の賃貸人の印象を悪くし、自らの立場が悪くなる可能性があるため避けてください。特に賃料の未払いは、退去を命じられる原因になる可能性があります。
また、賃料の交渉には、賃料増減請求権を理解しておくことが重要です。以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
賃料を増額する理由
賃料を増額する理由は、以下の4つです。
賃料が上がる理由を適切に理解しておくことで、どういう背景で不動産が値上げに踏み切ったのか理解でき、効果的な交渉をできるようになるでしょう。
賃貸人の立場を把握しつつ、自分の主張を伝えられるよう、参考にしてください。
建物の維持費が増加
理由の1つ目は、建物の維持費が増加したためです。経年劣化により、修繕費が発生したり、設備を新しい物と交換するための費用が発生したりした場合に、賃料が増額されるでしょう。
特に築年数が古い物件は、防火や耐震の強化を目的に修繕されます。その際、安全性を担保するために行われた工事費が賃料に反映されやすいです。ほかにも、賃借人にとって有益であるスロープの設置や、宅配ボックスの増設など、利便性向上を目的に、設備投資が行われるでしょう。
このような工事費や設備投資などの維持費の増加が賃料増額の原因となります。
税金、保険料の増加
理由の2つ目は、税金、保険料の増加です。固定資産税や自然災害が起こった際の保険料が値上がりした際に、賃料も合わせて値上がりします。
賃料を値上げしないと一方的に負担が増加し、建物の維持管理に支障をきたす可能性があるため、不動産の賃貸人は値上げを実施します。ほかにも物件が都市開発区域内の建物であれば、都市開発税の負担を理由に賃料が値上がりするでしょう。
上記のように、税金や保険料などが理由で、不動産の賃貸人が値上げをする場合があることを理解しておきましょう。
周辺の土地、建物の価値が上がった
理由の3つ目は、周辺の土地、建物の価値が上がった場合です。土地の値上がりにより賃料が不相当となったことを理由とするに賃料の値上げは借地借家法32条で賃料増額請求権として認められています。周辺の土地、建物の価値が上がる原因には、インフレによる地価上昇、商業施設の建設にともなう、周辺地価上昇などが挙げられます。
上記のように、土地の価値や地価が上昇することで、賃料も合わせて増額されるでしょう。しかし、値上がりには適正率が存在します。地価が倍になったから、単純に賃料も倍にとはなりません。
地価の判断は、経営者1人ではできないため、専門家に調査を依頼しましょう。
参照:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090)
周辺の建物と比較して賃料が安すぎる
理由の4つ目は、周辺の建物と比較して賃料が安すぎる場合です。周辺物件の賃料相場と比較して安すぎる場合、適正価格に揃える目的で、賃料の値上げが通知されます。
賃料相場に合った賃料にするための値上げは、賃料が不相当となったことの理由として認められています。相場通りの賃料になった場合は、以前までお得に経営できていたと考えるようにしましょう。
不動産の賃貸人が儲けるために値上げを考えたのではなく、元の賃料が相場と比較して安すぎる場合があります。
賃料が増額できないケース
賃料が増額できないケースは、以下の2点です。
賃料の増額には、双方の合意または賃料が不相当である理由が必要になります。そのため、増額に納得いかない場合、拒否が可能です。増額できないケースを確認しておきましょう。
賃借人と合意が得られない
ケースの1つ目は、賃借人と合意が得られない場合です。賃料の増減は、双方の合意があってはじめて成立します。賃料の値上げを行う通知が来たからと言って必ず従う必要はありません。賃料の値上げに妥当性がないと判断した場合は、反対しましょう。
ただし、値上げに納得できない場合に、値上げ前の賃料の支払いもを拒むことは、自分が不利になるため避けましょう。賃料の滞納により退去を命じられる可能性があります。
両者の合意が得られない場合は、交渉は平行線をたどります。将来にわたって良好な関係性を維持していきたいのであれば、どこかで妥協点を決めておきましょう。
交渉がまとまらない場合は、賃料交渉の専門家や、弁護士に第三者として仲介してもらうことをおすすめします。
賃料が不相当である理由がない
ケースの2つ目は、賃料が不相当である増額理由がない場合です。賃料の増額には、不相当であることの客観的根拠が必要になります。客観的根拠がないと判断される理由としては、以下が挙げられます。
- 収入を上げたい
- 増額が賃料相場から大きく離れている
- 契約時に賃料の値上げをしない特約が含まれている
上記に当てはまる理由で値上げを通知された場合は、賃料の増額を拒否できる可能性があります。特に賃料相場は、調査する人次第で金額が変わるため、自社側でも調査を依頼できる鑑定士を見つけておきましょう。
契約時に賃料の値上げをしない特約が盛り込まれていても、契約から時間が経過することで忘れている可能性があります。賃料の値上げを通知された際には、契約書の内容を読み、値上げの妥当性があるか、確認しておくのがおすすめです。
賃借人が賃貸人と賃料交渉する際のポイント
賃借人が賃貸人と賃料交渉する際のポイントは、以下の3つです。
効果的な交渉をするためには、相手側の意見を尊重しながら、自分の主張もしっかり伝えなければなりません。お互いが納得した状態で交渉を終えるために、ここで紹介するポイントを参考にしてください。
代替案の提案
ポイントの1つ目は、代替案の提案です。代替案を提案することで、新しい角度からの考えが加わり、妥協点を見つけやすくなります。賃料の値上げ交渉が平行線の場合は、以下のような代替案を検討してみてください。
- 6ヶ月未満の退去をしない
- 次回の契約更新を必ず行う
- 賃料を据え置いてもらえたら2年契約を約束する
不動産の賃貸人側にとって賃料収入が途絶えることは避けたいものです。賃借人側は、不動産の賃貸人側の状況を考慮し、賃料を抑えてもらえれば、長く契約できることを伝えてみましょう。
元々は賃料の値上げをするか、しないかが交渉の論点でしたが、代替案を提案することで不動産の賃貸人側に別のメリットを提示できます。交渉が長期化する場合は、代替案を提案してみましょう。
丁寧に対応する
ポイントの2つ目は、丁寧に対応することです。交渉は、企業間同士で行っていることを忘れてはなりません。
賃料の値上げに納得できないからといって、高圧的な態度を取る、連絡を無視するなどの行為は、不動産の賃貸人側に悪い印象を持たれます。交渉が終わったのち、契約が継続される可能性を念頭に置いた頭に入れた対応をしましょう。新しく店舗を契約する際に断られたり、企業全体の評判が悪くなったりするリスクがあります。
賃料の交渉は感情的にならず、企業の代表者であることを自覚し、丁寧に対応するように努めましょう。
賃料の増額理由を教えてもらう
ポイントの3つ目は、賃料の増額理由を教えてもらうことです。不動産の賃貸人側には、賃料の増額を申し出た背景があります。
値上げを一方的に反対するのではなく、値上げしたい理由を把握しておきましょう。理由を聞くことで、やむを得ない背景があることが理解でき、納得できるかもしれません。もしくは、理由を聞くことで、値上げに正当性がないと判断できるかもしれません。
どちらの場合でも、理由を聞かずに賃料の値上げに賛成することは、避けましょう。固定費の増加は、1か月単位で見れば少額かもしれませんが、継続すると大きな金額になります。
賃料の値上げ理由を適切に理解した上で契約するために、増額理由を共有してもらうようにしましょう。
交渉が上手くいかない場合
賃借人が交渉が上手くいかない場合に取るべき対応は、以下の4つです。
当事者間で上手く交渉できれば問題ありませんが、場合によっては交渉が長期化する可能性があります。そうした場合には、第三者に介入してもらいましょう。
第三者に介入してもらうことで、交渉がスムーズになる場合があります。自分1人の力での解決が不安な経営者は、以下の章を参考にしてください。
弁護士に相談する
対応の1つ目は、弁護士に相談することです。弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスをもらえます。ほかにも、値上げに反対する資料集めや、過去の裁判例など調査してくれるでしょう。
弁護士が代理人として仲介してくれることで、直接自分が交渉する必要もなくなります。通常の経営をしながら、同時進行で交渉の準備は困難です。
法律を遵守しながら負担軽減したいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。賃料増額の訴訟経験のある弁護士なら、よりスムーズに解決に導いてくれるでしょう。
退去を視野に入れる
対応の2つ目は、退去を視野に入れることです。賃料の値上げは、固定費の増加を意味します。固定費は店舗経営していく上で、できる限り抑えたい項目の1つです。
固定費が上がることで、減少する場合があります。店舗契約であれば、賃料が十万、百万円単位の物件もあるでしょう。商品価格に賃料を転嫁しにくい業態にとっては痛手になります。最悪の場合、店舗経営に支障が出てしまいます。
交渉が上手くいかない場合には、退去を視野に入れておきましょう。
供託制度を利用する
対応の3つ目は、供託制度を利用することです。供託制度を利用することで、賃料滞納を防げる可能性があります。
賃料交渉が難航した場合に、値上げした賃料でなければ受け取らないと主張する可能性があります。受け取りを拒否されたからといって賃料を滞納することには、リスクがともないます。なぜなら、交渉期間中も賃料の支払い義務は継続されるからです。
賃料の増額について交渉中に支払いを拒否されたら、供託所に値上げ前の賃料を納めましょう。供託所とは、法務局が運営しており、大家の行方が不明在の場合や、受け取りを拒否された場合に利用できる機関です。
賃料滞納を理由に賃貸借契約の解除を避ける方法として、供託制度があることを理解しておきましょう。
賃料増額によるトラブル事例
賃料増額によるトラブル事例を紹介します。実際に賃料増額請求に関する判事例を理解しておくことで、教訓を得られるでしょう。自分が同じ過ちをおかす可能性を減らし、似た状況に遭遇した際に、冷静に対応できるようにしておきましょう。
賃料の増額を拒否する場合に退去を要求された
ここでは、賃料の増額を拒否する場合に、退去を要求された事例を紹介します。弁護士事務所フードロイヤーズの石崎弁護士の対応事例を参照しています。
東京で飲食店を経営していた際に、賃貸人が変更になり、変更通知と一緒に、次回更新時から賃料が2倍になる旨も記載されていたという事例ですました。
今回の事例では、普通賃貸借契約のため、賃料の値上げに応じる義務はありません。しかし、賃貸人は、値上げに反対するのであれば、退去してもらうと迫ってきました。
賃貸人は、周辺の賃料相場を根拠に、賃料の値上げの正当性を訴えています。店舗側も鑑定士に依頼し、調査したところ賃料の値上げは5%が適正であることが判明しました。
その後、交渉が平行線になったため、弁護士に賃料増額に対するの賃貸人との交渉を依頼しました。結果、賃貸人が物件を売却したため、値上げの話はなくなりました。
今回の事例では、妥当とは言えない金額の値上げです。そのため、賃料の値上げを拒否できると考えられます。しかし、退去を迫ってくるのであれば、不安を感じるでしょう。
自分1人での解決が難しいと判断した場合は、弁護士などの第三者に介入してもらい、効果的に交渉しましょう。
賃料の増額理由を理解し適切な金額で契約しよう
賃借人側には、賃料の増額を拒否する権利があります。賃料の値上げを打診されたら、まずは値上げ理由を教えてもらいましょう。理由に妥当性があれば、受け入れる必要がありますが、妥当性のない理由であれば、しっかりと反対の意思を表示してください。
双方の合意がなければ、賃料の値上げはできません。しかし、高圧的な態度での交渉は避けましょう。企業間同士の取引であるため、丁寧に対応しましょう。
もし、自分1人で賃料の交渉に不安がある、賃料の相場がわからない経営者は、賃料交渉のプロに相談依頼するのがおすすめです。不動産との関係性を維持しつつ、適正な賃料になるようコンサルティングしてくれます。興味のある方は、以下のサイトを参考にしてください。
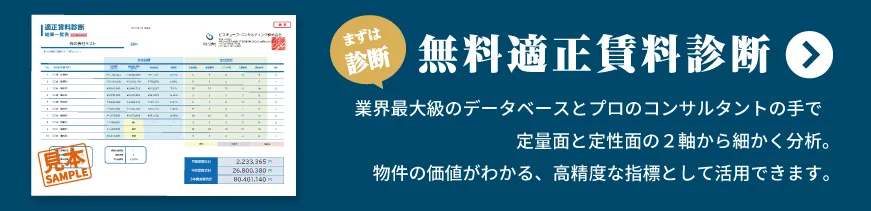
今の賃料が「安い」「適正」「高い」でハッキリわかる
【無料】実態分析賃料データ15万件分を駆使した高精度な賃料適正診断
店舗・事務所・オフィスなど、幅広くご対応いたします。
クライアント企業 全3,593社うち上場企業400社以上
累計削減件数 35,000件以上

【監修者】幸谷 泰造(弁護士)
東京大学大学院情報理工学系研究科修了。ソニー株式会社で会社員として勤めた後弁護士となり、大手法律事務所で企業法務に従事。一棟アパートを所有する不動産投資家でもあり、不動産に関する知識を有する法律家として不動産に関する法律記事の作成や監修、大手契約書サイトにおいて不動産関連の契約書の監修を行っている。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。












 人気記事ランキング
人気記事ランキング

