年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
利益率とは?粗利益率・営業利益率・純利益率の計算・分析・改善を完全解説

- 目次
利益率とは?なぜ今、利益率の「見える化」が重要なのか
利益率とは、売上高に対してどれだけの利益を得ているかを示す指標であり、企業の収益性を定量的に評価するために欠かせない財務指標のひとつです。
ただし「利益率」と一口に言っても、目的や分析対象によって使うべき指標は異なります。
代表的な利益率には以下のような種類があります。
| 利益率の種類 | 概要 |
| 粗利益率(売上高総利益率) | 販売活動の効率性を示す |
| 営業利益率 | 本業の収益性を示す |
| 経常利益率 | 通常活動全体の収益性を示す |
| 純利益率 | 最終的な利益力を示す |
たとえば、営業利益率が10%であれば、売上が1,000万円の場合、営業利益は100万円となります。この数値は、販管費や固定費の管理状況を反映し、本業の収益性を評価する材料となります。
利益率を「見える化」することで、現状の課題を明確にし、社内で共通の認識を持つことができます。利益率の推移や業界平均との比較をグラフや表で示すことで、経営陣や現場担当者の理解が深まり、意思決定のスピードと精度が向上します。
また、利益率の変動を定期的に確認することで、販売戦略の見直しやコスト削減施策の検討にも役立ちます。たとえば、原価率が高騰している場合には、仕入れ条件の見直しや価格改定の判断材料となります。
このように、利益率を把握することは、収益構造の改善やコスト削減など、具体的な経営改善の第一歩となります。経営者や管理職にとって、利益率の可視化は、健全な経営を支える基盤であり、効果的な戦略策定の起点となります。
利益率の種類と違い|粗利益率・営業利益率・純利益率の使い分け
企業の収益性を評価する際、「利益率の計算」は欠かせない指標です。
利益率には複数の種類があり、それぞれ異なる視点から経営状況を示します。目的に応じて使い分けることで、より精度の高い収益性分析が可能になります。
主な利益率とその特徴
| 利益率の種類 | 定義 | 特徴 | 活用例 |
| 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高に対する粗利益(売上高 − 売上原価)の割合 | 原価管理や価格設定の妥当性を評価 | 小売業での仕入れ見直し製造業での原材料費削減 |
| 売上高営業利益率 | 売上高に対する営業利益(粗利益 − 販管費)の割合 | 本業の収益性を示す。販管費の管理状況が反映される | 店舗運営コスト人件費の適正化 |
| 売上高経常利益率 | 売上高に対する経常利益(営業利益 ± 営業外収益・費用)の割合 | 財務活動や投資収益も含めた包括的な収益性評価 | 借入コスト金融収支を含めた経営判断 |
| 売上高税引前当期純利益率 | 売上高に対する税引前の当期純利益の割合 | 法人税等の影響を除いた最終利益水準を把握できる | 税制の影響を除外した分析 |
| 売上高当期純利益率 | 売上高に対する税引後の最終利益(当期純利益)の割合 | 最終的な収益力を示す。企業価値評価に直結 | 株主向け財務報告投資判断の材料 |
以下の記事では、「営業利益」に特化して解説しております。ご参考ください。
利益率の使い分けポイント
目的に応じて、以下のように利益率を使い分けることが重要です。
| 場面 | 確認すべき利益率 |
| 販売効率を見たい場合 | 売上高総利益率 |
| 本業の収益性を評価したい場合 | 売上高営業利益率 |
| 企業活動全体の収益性を見たい場合 | 売上高経常利益率 |
| 税務要因を除いた利益水準を見たい場合 | 売上高税引前当期純利益率 |
| 最終的な利益力を評価したい場合 | 売上高当期純利益率 |
利益率の種類と計算式を理解し、目的に合わせて使い分けることで、企業の収益構造を多角的に分析できるようになります。特に、営業利益率や粗利益率の計算式を活用することで、コスト削減や価格戦略の見直しにもつながります。
業界平均との比較や、改善施策の検討にも役立つため、財務・経営企画部門にとって重要な指標といえるでしょう。
利益率の計算方法|原価・売価・利益の関係を整理
企業の収益性を正しく評価するには、利益率の計算式を理解し、原価・売価・利益の関係性を整理することが重要です。
利益率は単なる数字ではなく、価格戦略やコスト管理の改善に直結する指標であり、経営判断の基礎となります。
利益率の種類と計算式|目的に応じた使い分け
利益率には複数の種類があり、それぞれ異なる角度から企業の収益性を評価します。
以下は代表的な利益率とその計算式です。
| 利益率の種類 | 計算式 | 用途例 |
| 粗利益率(売上高総利益率) | (売上高−売上原価)/売上高×100 | 原価管理や価格設定の妥当性評価 |
| 営業利益率 | 営業利益/売上高×100 | 本業の収益性分析(販管費の管理) |
| 経常利益率 | 経常利益/売上高×100 | 財務活動を含めた包括的な収益性評価 |
| 税引前当期純利益率 | 税引前当期純利益 ÷ 売上高 × 100 | 税務要因を除いた利益水準の把握 |
| 純利益率 | 当期純利益 ÷ 売上高 × 100 | 最終的な収益力の評価(株主還元など) |
原価率・マージン・値入率との違いと関係性
利益率と密接に関連する指標として、「原価率」「マージン」「値入率」があります。これらは価格設定や仕入れ戦略の見直しに役立つため、違いを理解しておくことが重要です。
| 指標名 | 定義 | 計算式 | 計算例 | 備考 |
| 原価率 | 売上高に対する原価の割合 | 原価/売上高×100 | 原価700万円 ÷ 売上高1,000万円 = 70% | 原価が高いほど利益率は低下 |
| マージン | 売価に対する利益の割合 | 利益/売価×100 | 利益200円 ÷ 売価1,000円 = 20% | 粗利益率と混同されやすい |
| 値入率 | 売価に対する粗利益の割合 | (売価−原価)/売価×100 | (1,000円 − 700円) ÷ 1,000円 = 30% | 値入率が高いほど利益効率が良い |
Excelでの利益率の出し方|初心者向けステップ解説
利益率を手軽に計算したい場合、Excelを使う方法が便利です。以下は初心者向けの基本ステップです。
【ステップ1】項目名を入力する
まず、Excelの1行目に以下のように項目名を入力します。
- A1セル:売上高
- B1セル:利益
- C1セル:利益率
このように項目を設定することで、どのセルに何を入力するかが明確になります。
【ステップ2】数値を入力する
次に、2行目に実際の数値を入力します。たとえば以下のように入力します。
- A2セル:1000000(売上高:100万円)
- B2セル:100000(利益:10万円)
※数字はカンマなしで入力しても問題ありません。
【ステップ3】利益率を計算する式を入力する
C2セルに、以下の計算式を入力します。
> =B2/A2*100
この式は、「利益 ÷ 売上高 × 100」を意味しており、利益率をパーセンテージで算出するものです。
【ステップ4】パーセンテージ表示にする(任意)
C2セルに表示される数値は「10」となりますが、これを「10%」と表示したい場合は、以下の手順で表示形式を変更します。
- C2セルを選択
- 右クリック →「セルの書式設定」を選択
- 「表示形式」タブで「パーセンテージ」を選択
- 小数点以下の桁数を「1」または「0」に設定
これで、C2セルには「10%」と表示されるようになります。
利益率の計算は経営改善の第一歩
利益率の種類と計算方法を正しく理解し、関連指標との違いや関係性を整理することで、企業は収益性を多角的に評価できます。
特に、原価率や値入率との比較を通じて、価格戦略や仕入れ方針の見直しが可能となり、営業利益率や純利益率の改善にもつながります。
業種別の利益率目安|自社の立ち位置を把握するための指標
企業が利益率を正しく評価するには、業界平均との比較が有効な手段と考えられます。
業種ごとに利益率の構造や水準は大きく異なるため、同業他社との比較を通じて、自社の収益性や改善余地を客観的に把握することが可能です。
業界別の粗利益率(売上高総利益率)の比較
粗利益率は、売上高に対する粗利益の割合を示す指標であり、原価構造や販売効率を評価する際に活用されます。以下は、主要業種の平均的な粗利益率です。
| 業界 | 粗利益率 | 補足説明 |
| 小売業 | 31.2% | 仕入れ原価が高く、薄利多売型。店舗運営や在庫管理が収益性に影響。 |
| 製造業 | 24.4% | 原材料費・製造コストの管理が重要。設備投資や生産効率が収益性に直結。 |
| サービス業 | 41.4% | 在庫を持たない業態が多く、原価が低いため高利益率。人件費管理が鍵。 |
| 情報通信業 | 43.2% | 初期投資は大きいが、運用コストが低く利益率は高め。サブスク型が主流。 |
| 運輸業、郵便業 | 24.0% | 固定費(燃料・人件費・設備維持費)が大きく、利益率は低め。 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 43.3% | 賃料収入による安定収益が見込まれるが、物件取得・維持費の影響あり。 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 66.2% | 変動費が多く、施設規模や立地により利益率が大きく変動。 |
※上記は、総務省統計局「中小企業実態基本調査(令和2年確報)」を基にした参考値です。業種・企業規模・年度により数値は変動します。
業界別の営業利益率の比較
営業利益率は、本業の収益性を示す指標であり、販管費や固定費の管理状況が反映されます。以下は代表的な業種別の目安です。
| 業界別 | 営業利益率 | 備考 |
| 小売業 | 2~5% | 薄利多売型。店舗運営コストや人件費の管理が重要。 |
| 製造業 | 5~10% | 生産効率や原価管理が収益性に直結。 |
| サービス業 | 5~15% | 人件費比率が高く、業態によって差が大きい。 |
| 情報通信業 | 10~20%以上も可能 | 高利益率が可能。固定費が少なく、スケーラビリティが高い。 |
| 飲食業 | 3~7% | 客単価・回転率・人件費の管理が収益性に影響。 |
| 建設業 | 3~6% | 工期管理・原価管理が収益性の鍵。 |
※上記の営業利益率の目安は、株式会社koujitsuによる業界分析記事(公開時点)を参考にしたものです。実際の数値は年度や統計方法により変動します。
参考:株式会社koujitsu「利益率の目安は何%を目指すべき?計算方法と業種別平均を解説」
利益率比較から見える改善余地
業界平均と自社の利益率を比較することで、以下のような改善施策の検討が可能です。
- 粗利益率が低い場合:仕入れ条件の見直し、価格戦略の再設計
- 営業利益率が低い場合:販管費(人件費・賃料・広告費など)の適正化
- 業界平均を上回っている場合:競争優位性の明確化と維持戦略の構築
利益率の改善を具体的に進めるには、仕入れや価格戦略の見直しだけでなく、日常のコスト管理や経費削減も重要なポイントです。
特に、販管費や固定費の最適化は営業利益率の向上に繋がるため、より実践的な手法を知りたい場合は以下の記事も参考にしてください。
これらの記事では、日常業務の中で実践できるコスト管理・経費最適化の具体策を詳しく解説しています。
利益率向上のための次のステップとして、ぜひ併せてご覧ください。
業界平均との比較は戦略的経営の出発点
利益率の計算だけでなく、業種別の平均値との比較を行うことで、自社の立ち位置や改善余地を客観的に把握できます。
特に、粗利益率や営業利益率は、価格設定・原価管理・販管費の見直しに直結するため、経営企画や財務部門にとって重要な指標です。
利益率の分析方法|過去・業界・他指標との比較で精度を高める
企業の収益性を評価する際、利益率の計算結果だけを見て判断するのは不十分です。
正確な経営判断を行うためには、以下の3つの視点から利益率を分析することが重要です。

1. 自社の過去データとの比較
利益率の推移を見ることで、収益構造の改善状況や課題の継続性を把握できます。
- 過去3〜5年分の営業利益率を並べることで、改善トレンドが見える
- 売上高や原価の変動と合わせて分析することで、要因の特定が可能
例:営業利益率が前年5% → 今年7%に上昇
→ 販管費の削減や売上総利益の増加など、改善施策が奏功した可能性
Point:過去との比較は、改善の成果や課題の継続性を判断するための基礎情報です。
2. 業界平均との比較
業界平均と自社の利益率を比較することで、競争力や収益性の水準を客観的に評価できます。
- 業界平均より高ければ、価格戦略やコスト構造が優れている可能性
- 業界平均より低ければ、改善余地があると判断できる
例:小売業の営業利益率が平均2%〜7%の中で、自社が6%
→ 高収益体質と評価でき、競争優位性の根拠となる
Point:業界平均との比較は、自社の立ち位置を把握し、戦略の方向性を定める材料になります。
3. 他の財務指標との併用
利益率だけで収益性を判断するのは不十分です。売上高・原価率・販管費率・営業利益率などの指標と併せて分析することで、より正確な経営判断が可能になります。
- 売上高が増えても利益率が下がっている場合 → 原価や販管費が増加している可能性
- 原価率が高い場合 → 仕入れ条件や製造コストの見直しが必要
- 営業利益率が低い場合 → 固定費(賃料・人件費など)の削減が有効
例:営業利益率が業界平均を下回り、販管費率が高い
→ 固定費の見直しが改善施策として有効
Point:複数の指標を組み合わせて分析することで、利益率の背景にある課題や改善ポイントが明確になります。
利益率分析は「比較」と「構造理解」が鍵
利益率を正しく読み解くには、
- 過去との比較
- 業界平均との比較
- 他の財務指標との併用
という3つの視点が有効です。これらを踏まえた分析を行うことで、収益性の課題を的確に把握し、改善策を検討することが可能になります。
利益率改善の実践方法|数値で見る効果
営業利益率が業界平均を下回り、販管費率が高い場合は、固定費であるテナント賃料の見直しが有効です。
その際には、ビズキューブ・コンサルティングの「賃料適正化コンサルティング」が、戦略的なコスト削減をサポートします。
▼ビズキューブ・コンサルティングの実績
- 賃料適正化のパイオニア企業
- 累計2,349億円のコスト削減を実現
- 3,593社(うち上場企業400社以上)との取引実績
店舗運営コストの見直しや契約条件の適正化を通じて、営業利益率の向上と収益性改善に直結します。テナント賃料の削減余地がどれくらいあるのか気になった方は、まずは無料の賃料適正診断をお試しください。弊社サービスは完全成果報酬制のため、安心してご利用いただけます。
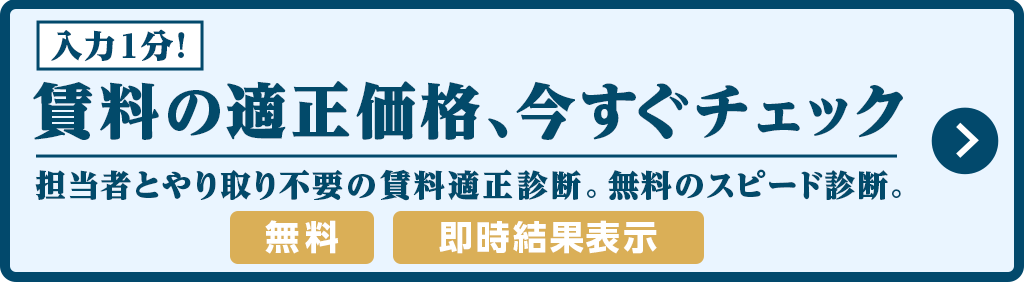
利益率を上げる方法|コスト削減と価格戦略の実践ポイント
利益率を高めるには、売上の増加だけでなく、コスト構造の見直しと価格戦略の最適化が有効と考えられます。
利益率は「利益 ÷ 売上高」で算出されるため、利益を増やすには「売上を伸ばす」「コストを減らす」またはその両方の施策が必要です。
以下では、利益率改善に効果的な4つの施策を紹介します。
1. マーケティング施策の見直し
Point:売上の「質」を高めることで、利益率の向上につながる
マーケティング施策は、売上の効率と利益構造に直結します。
単に集客数を増やすのではなく、高単価・高利益の商品への誘導が重要です。
- 販促費が利益を圧迫していないかを確認(例:CPAが高騰している場合)
- 顧客獲得単価(CPA)とLTV(顧客生涯価値)のバランスを見直す
- 高利益率商品の訴求強化、低利益率商品の販促抑制
2. 商品・サービスの見直しで販売ロスを削減する
Point:販売ロスの削減は、原価率・販管費率の改善に直結する
利益率が低い原因のひとつに、販売ロス(売れ残り・値引き・返品など)があります。
商品やサービスのラインナップを見直すことで、無駄なコストや機会損失を減らすことが可能です
- 売れ筋と死筋商品の分析による品揃えの最適化
- 値引き依存型の販売から脱却し、価値訴求型へ転換
- サービス提供の標準化によるオペレーション効率化
3. 仕入れ先の見直しで変動費を抑える
Point:仕入れコストの見直しは、粗利益率の改善に最も直接的な効果をもたらす
原価率が高い場合、仕入れ条件や取引先の見直しが有効です。
変動費の削減は、粗利益率の改善に直結します。
- 同品質でより安価な仕入れ先の選定
- 仕入れロットや納期条件の見直しによるコスト最適化
- 複数業者との比較による価格交渉力の強化
4. 人件費などの固定費を見直す
Point:固定費の見直しは、営業利益率の改善に直結し、利益率向上の持続性を高める
営業利益率を高めるには、販管費や固定費の見直しが不可欠です。
特に人件費・テナント賃料などは、継続的に利益を圧迫する要因となるため、戦略的な管理が求められます。
- 業務フローの見直しによる人件費の最適化
- 賃料の適正化による固定費削減
ビズキューブ・コンサルティングの「賃料適正化コンサルティング」では、賃貸借契約の条件の見直しや賃料の相場比較を通じて、戦略的なコスト削減を支援しています。
利益率計算ツールおすすめ|Excel・無料サイト・アプリ比較
利益率を正確かつ効率的に算出するには、自動計算ツールやテンプレートの活用が有効と考えられます。
特に、複数の数値を日常的に扱う担当者にとっては、手計算によるミスの防止や作業時間の短縮につながります。
利益率計算の基本とツール活用の必要性
利益率は「利益 ÷ 売上高 × 100」で算出されますが、
- 利益の種類(粗利益・営業利益・純利益)
- 売上の定義(税抜/税込、部門別など)
によって計算式が変わるため、計算ミスや認識のズレが起こりやすい指標です。
そのため、あらかじめ計算式が設定されたツールを活用することで、誰でも正確に利益率を算出できます。
自動計算ツールの活用方法
利益率を自動で計算できるツールには、以下のような種類があります。
①Excelの関数設定済みファイル
- 利益率の種類ごとに計算式が組まれており、売上高・原価・販管費などを入力するだけで自動計算できます。
- ただし、テンプレートは誰かが作成する必要があります(自社で作る、または配布テンプレートを利用)。
- 複数店舗や複数商品を一括管理できる構成も可能で、社内資料や報告書作成にも便利です。
②Web上の利益率計算サイト・アプリ
- ブラウザ上で数値を入力するだけで、粗利益率・営業利益率・純利益率などを即座に表示できます。
- 一部のツールでは、業界平均との比較やグラフ表示機能も搭載されています。
③販売管理システムや会計ソフトとの連携
- 販売管理システムや会計ソフトと連携することで、売上や原価データをもとに利益率をリアルタイムで確認できる環境を構築することが可能です。
- 工数削減だけでなく、担当者が変わってもスムーズに運用できる仕組みづくりにもつながります。
Point:ツールやテンプレートを活用することで、利益率の計算精度を高めつつ、作業効率も改善できます。
特に複数店舗・複数商品を扱う企業では、正確な数値管理と比較分析を両立できる点が大きなメリットです。
利益率計算式テンプレートの構成例(Excel)
Excelを使った利益率計算テンプレートは、複数拠点の収益性比較や社内資料作成に非常に便利です。
| セル | 内容 | 説明 |
| A1 | 売上高 | 商品やサービスの売上金額を入力 |
| B1 | 原価 | 仕入れや製造にかかったコストを入力 |
| C1 | 粗利益 | =A1-B1 で自動算出 |
| D1 | 粗利益率 | =C1/A1*100 で自動算出(%表示) |
| E1 | 販管費 | 人件費・賃料・広告費などを入力 |
| F1 | 営業利益 | =C1-E1 で自動算出 |
| G1 | 営業利益率 | =F1/A1*100 で自動算出(%表示) |
例:売上高1,000万円、原価700万円、販管費150万円の場合
粗利益率 = 30%、営業利益率 = 15%
このようなテンプレートを活用することで、複数の利益率を一括で管理・比較できるようになります。
ツール活用で利益率の「見える化」と「改善」を両立
利益率の計算は、ツールやテンプレートを活用することで、正確かつ効率的に実施可能です。
特に、複数店舗・複数商品を扱う企業では、Excelや業務支援ツールとの連携により、利益率の可視化と工数削減を同時に実現できます。
まとめ|利益率の「見える化」で収益性を高める第一歩
利益率の改善は、まず「見える化」から始めることが有効です。
現状の利益率を正確に把握し、比較・分析を通じて課題を特定し、改善施策を実行することで、企業の収益性は着実に向上します。
利益率改善の3ステップ|計算 → 比較 → 改善
利益率を高めるには、以下の3ステップを明確にし、社内で共有・実行できる体制を整えることが重要です。
① 計算:現状の利益率を把握する
- 粗利益率・営業利益率・純利益率など、目的に応じた指標を選定
- Excelテンプレートや自動計算ツールを活用し、数値を正確に算出
- 複数店舗・複数商品を扱う場合は、利益率の一括管理が有効
② 比較:過去・業界平均・他指標と照らし合わせる
- 自社の過去データとの比較で改善傾向を確認
- 業界平均との比較で競争力を評価(例:小売業の営業利益率平均は2〜7%)
- 原価率・販管費率などの関連指標と併用し、課題を特定
③ 改善:施策を立案・実行する
- マーケティング施策の見直し(高利益率商品の訴求強化)
- 商品・サービスの再設計(販売ロスの削減)
- 仕入れ条件や固定費の見直し(賃料・工事費など)
Point:
この3ステップを社内で定期的に実行することで、利益率の改善を継続的に推進できます。
ビズキューブの利益率改善に直結する2つのコスト削減支援
ビズキューブ・コンサルティングでは、営業利益率や粗利益率の改善に直結するコスト領域に対して、以下の2つの支援サービスを提供しています。
1. 賃料適正化コンサルティング
Point:賃料の見直しは、営業利益率の底上げに直結する即効性の高い施策です。
- 店舗や事業所の賃料を適正化し、毎月発生する固定費を削減
- 多店舗展開企業では、賃料見直しによる利益率改善インパクトが大きい
- 累計3,593社以上の支援実績、2,349億円のコスト削減を実現
※2023年3月時点での累計実績(自社調べ)
まずは、貴社の賃料が相場と乖離していないか、無料診断から始めてみませんか?
2. 工事費削減コンサルティング
Point:工事費の見直しは、粗利益率の改善と資金効率の向上に貢献します。
- 店舗やオフィスの移転・撤退時の原状回復費用を適正化
- 工事費は原価として計上されるため、粗利益率に直接影響
- 施工実務40年の実績を持ち、累計50,000件以上の契約書を精査してきた実績がある
余分な工事項目の有無を確認し、退去費用の適正化を支援します。
利益率改善は「仕組みづくり」から
利益率の改善は、単なる数字の操作ではなく、経営全体のコスト構造の見直しと仕組みづくりが必要です。
ビズキューブ・コンサルティングは、「賃料」と「工事費」という利益率に直結するコスト領域において、実務に即した支援を提供しています。
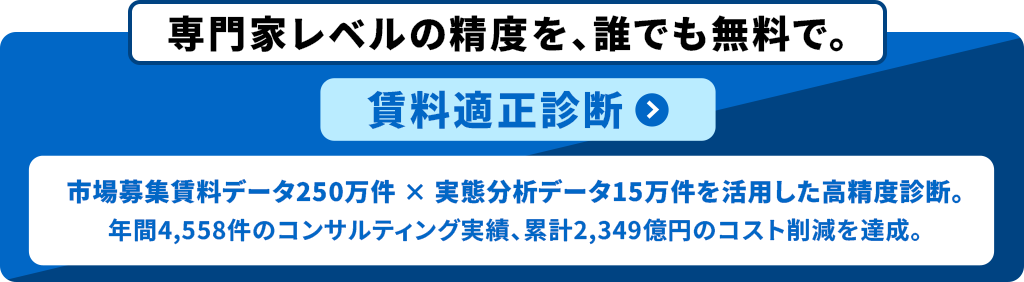
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。





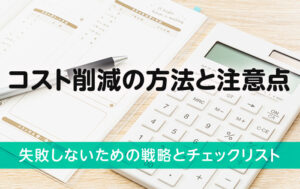

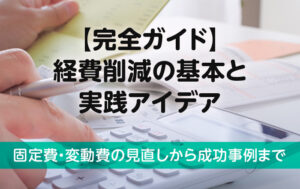






 人気記事ランキング
人気記事ランキング

