年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する不動産関連
【2025年9月】最新のオフィス空室率|動向と企業が押さえるべき活用ポイント
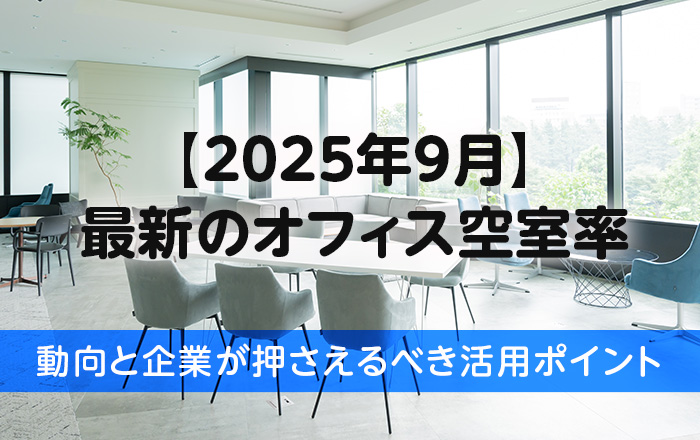
- 目次
オフィス空室率とは?基本の意味と重要性
オフィス空室率の定義
オフィス空室率とは、特定の地域にあるオフィスビルで、賃貸可能な床面積のうち空いている割合を示す指標です。この数値は、オフィスマーケットの需給バランスや賃料動向を把握するうえで、企業の意思決定に欠かせません。
オフィス空室率の計算方法
オフィス空室率は、次の計算式で求められます。
>空室率(%)=空きオフィスの床面積 / オフィスの賃貸可能な床面積 ×100
例えば、賃貸可能な床面積が10,000㎡のオフィスビルで2,000㎡が空室の床面積の場合、空室率は 20% です。
※統計によっては「募集床面積」を用いる場合があります。比較する際は定義の揃えにご注意ください。
オフィスの空室率が高い・低い場合の市場状況
| 状況 | 特徴 | 空室率が変動する要因 |
| 空室率が高い場合 | 市場は供給過剰で、賃料は下落傾向。オーナーは契約条件を緩和しやすい。 | ・新築ビルの大量供給 ・景気後退による企業縮小 ・テレワーク普及による需要減 |
| 空室率が低い場合 | 市場は需給が逼迫し、賃料は上昇傾向。良質な物件は早期に埋まる。 | ・景気回復や企業拡張 ・新規供給の停滞 ・人気エリアへの集中 |
企業にとっての活用ポイント
空室率を把握することで、賃料交渉・移転タイミング・長期コスト管理に役立ちます。
| 活用イメージ | 詳細 | 理由 |
| 賃料交渉 | 空室率が高いエリアでは、賃料や契約条件の見直し交渉がしやすくなる可能性があります。 | 空室が多いとオーナーは解約防止のため、賃料値下げやフリーレントを受け入れやすい。 |
| 移転タイミングの判断 | 市場の空室率を把握することで、コストを抑えた移転計画を立てやすくなります。 | 空室率が上昇している場合、供給過剰の兆しがあり、賃料が下がる傾向にあります。このタイミングで移転を検討することで、より有利な条件で契約できる可能性が高まります。 |
| 長期的なコスト管理 | 空室率を定期的に確認することで、オフィス戦略や契約条件の見直しに役立ちます。 | 市場の需給変化を把握することで、将来的な賃料上昇リスクや移転コストを予測し、計画的なコストコントロールが可能になります。また、テレワークや人員変動に応じて適正規模を維持し、不要な賃料負担を抑えることができます。 |
実際に賃料交渉を行う際には、賃料相場データを併せて提示することが重要です。相場データを示すことで、オーナーに「市場価格に基づいた合理的な根拠」を提示でき、感覚的な要望ではなく客観的なデータに基づく交渉が可能になります。その結果、オーナー側も納得しやすく、条件改善に応じやすくなります。
ビズキューブ・コンサルティングでは、無料の賃料適正診断をご用意しています。賃料の見直しは早めの対応がコスト削減につながります。まずは、貴社の賃料が適正水準と乖離していないか確認してみてください。
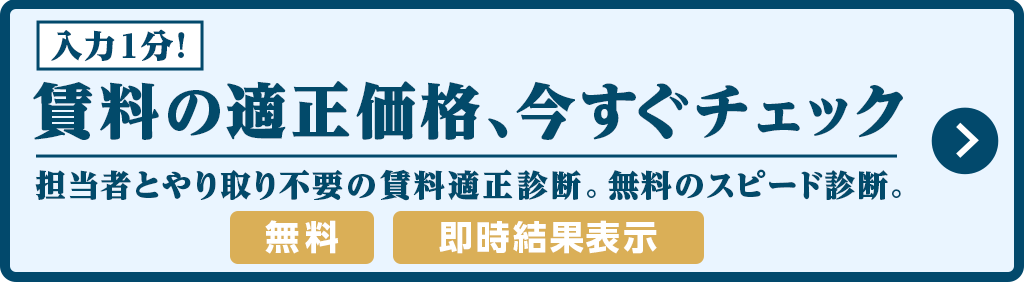
オフィス空室率の目安と判断基準
適正な空室率はどれくらい?
一般的に、約5%前後が「適正水準」といわれます。
市場に一定の空きがあることで入れ替えや新規需要に対応しつつ、過剰空室は避けられる適正な状態です。賃料の急変を招きにくく、コスト計画を立てやすくなります。
空室率別に見る市場の特徴と企業への影響
空室率の水準によって、市場環境や企業の選択肢は大きく変わります。以下は、一般的な傾向です。
| 空室率 | 市場の特徴 | 企業への影響 |
| 5%未満 | 需給が逼迫し、賃料は上昇傾向。人気エリアでは物件不足が発生しやすい。 | 賃料交渉は難しく、移転や増床の選択肢が限られる。早期の意思決定が必要。 |
| 5%前後 | 需給が均衡し、賃料は安定。 | 長期的なコスト計画が立てやすい。 |
| 5%超 | 供給過剰の兆し。賃料下落や物件価値の低下リスク。 | 契約更新や移転交渉で有利になりやすい。 |
| 10%超 | 市場は借り手優位。賃料下落が顕著。 | 大幅なコスト削減のチャンスだが、立地や物件選定に注意が必要。 |
※以下の空室率と市場傾向は、一般的な目安であり、地域や時期、物件の特性によって異なる場合があります。
最新のオフィス空室率動向と市場分析
2025年8月時点の主要エリアの空室率と賃料推移
東京のオフィスマーケットは、エリアごとに空室率と賃料の動きが異なります。
| エリア | 平均空室率 | 特徴 |
| 東京ビジネス地区 | 2.85% | 空室率は5カ月連続で低下。新築ビルでの成約やグループ集約による大型契約が進み、需給はタイト化。賃料は21,027円で前月比わずかに上昇。 |
| 大阪ビジネス地区 | 3.74% | 中小規模の成約が活発だが、新規供給や自社ビル移転による解約で空室率は小幅上昇。賃料は12,522円で緩やかに上昇。 |
| 名古屋ビジネス地区 | 3.93% | 大型解約の影響で空室率は2カ月連続上昇していたが、郊外からの移転などの成約が見られたことで低下。賃料は12,726円で微増。 |
| 札幌ビジネス地区 | 3.54% | 新築ビルで大型成約が進み、空室率は4カ月連続低下。既存ビルでも郊外からの移転や増床が見られる。賃料は10,916円で小幅上昇。 |
| 仙台ビジネス地区 | 6.02% | 直近、拡張移転や館内増床などに伴う成約が見られたことで空室率は低下。駅前や再開発エリアでの移転需要はあるが、全体では高水準。賃料は9,477円でほぼ横ばい。 |
| 横浜ビジネス地区 | 5.91% | 大型成約や建替え予定のビルからの移転により空室率は低下。みなとみらい地区は9%弱と高め。賃料は13,050円でやや上昇。 |
| 福岡ビジネス地区 | 4.91% | 拡張移転によって、空室率は低下。天神地区は9%台と高めだが、博多駅周辺は2%台で需給がタイト。賃料は12,108円で上昇傾向。 |
空室率と入居率の関係と変動要因

空室率は入居率と表裏一体で、景気・企業活動・供給計画を敏感に反映します。変動要因を理解すると、移転や交渉のタイミングを見極めやすくなります。
| 変動要因 | 市場への影響と企業が取るべき視点 |
| 景気拡大期 | 企業の拡張意欲が高まり、入居率は上昇、空室率は低下します。この局面では、賃料が上昇しやすく、移転や増床の選択肢が限られるため、早期の意思決定が重要です。 |
| 景気後退期 | コスト削減のためオフィス縮小や解約が進み、空室率は上昇します。このタイミングは、賃料交渉や移転条件の改善を狙う好機です。 |
| テレワークの普及 | オフィス面積の縮小が進み、空室率上昇の要因となります。企業は、ハイブリッドワークを前提としたオフィス戦略を検討する必要があります。 |
| 新築ビルの大量供給 | 一時的に空室率が上昇し、賃料が下落する可能性があります。供給計画を把握し、移転タイミングを見極めることがコスト削減の鍵です。 |
今後の見通しと企業が取るべき対応
今後も、景気動向・働き方の定着度・新規供給のタイムラインにより空室率は振れやすいと考えられます。経営目線では、次の観点で戦略を見直すと有効です。
| 検討項目 | 戦略的ポイント |
| オフィススペースの再評価 | 人員計画や働き方に合わせ、必要面積を最適化。レイアウト変更やサテライト導入で固定費を削減。 |
| 賃貸契約の見直し | 中途解約条項や短期契約など、柔軟な条件を確保し、景気変動リスクを低減。 |
| 移転タイミングの判断 | 空室率が上昇局面にある場合、賃料交渉や移転で有利な条件を得やすい。市場データを定期的に確認し、意思決定を迅速化。 |
| ハイブリッドワークの導入 | 出社実態に即した面積・仕様に。生産性とコストの最適点を設計。 |
オフィス空室率は、単なる市場データではなく、コスト構造と競争力に直結する経営指標です。定期的なモニタリングと柔軟な戦略が、企業の固定費最適化とリスク回避につながります。
オフィス空室率を活用した実務戦略
空室率を活用して賃料交渉を有利に進める
オフィス空室率は、賃貸契約の交渉において最も説得力のあるデータの一つです。特に、空室率が高いエリアでは、オーナーは入居者確保のために賃料や条件を柔軟に見直す傾向があります。
ただし、賃料交渉には契約条項や法的枠組みが大きく関わります。たとえば、借地借家法第32条では、経済状況の変化や周辺相場との乖離がある場合、賃料の増額・減額を請求できるとされていますが、契約や特約の内容によっては適用されないケースもあります。
こうした法的背景を踏まえたうえで、交渉が可能な状況であれば、より有利に進めるために、以下の4点の取り組みをおすすめします。
| 方法 | 詳細 | 調査方法 |
| 競合ビルの空室率・賃料情報を提示 | 同エリアの競合物件の空室状況や賃料を示し、貸主に他に選択肢があることをアピール。 | 不動産仲介会社に電話やメール、あるいは直接訪問して、競合ビルの空室率を確認。 |
| エリア全体の空室率データを提示 | 市場全体の需給バランスを示し、貸主に空室リスクを意識させる。 | 国土交通省、自治体の統計データ、市況レポートを確認。 |
| 入居中ビルの空室率(参考) | 自社ビルに空きがある場合は、条件改善を求める根拠に。 | 管理会社や貸主から直接確認。 |
| 類似物件の賃料情報を調査 | 同エリア・同規模の物件の賃料相場を把握し、比較データを提示することで交渉力を高められます。 | 賃貸ポータルサイトの活用や賃料適正診断によって、相場を把握。 |
賃料相場の調べ方については、以下の記事の「店舗の坪単価相場の調査方法」で詳しく解説しています。オフィスの場合も基本的な調査手順は同じですので、賃料相場を把握したい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
移転タイミングを見極める
移転のタイミングは、空室率と賃料の動きがカギです。市場の局面を見誤ると、コスト増や選択肢の制約につながります。
| 市場の状況 | 判断のポイント |
| 空室率が上昇している時期 | 賃料は下落傾向にあり、移転や増床の好機。条件交渉で優位に立ちやすい。 |
| 空室率が低い時期 | 賃料は上昇しやすく、良質な物件は早く埋まる。この場合、移転を急ぐか、現状維持を選ぶか慎重な判断が必要。 |
オフィス移転時には原状回復工事が原則として求められますが、高額な見積もりが提示されるケースも少なくありません。
ビズキューブ・コンサルティングでは、工事費削減に特化したコンサルティングを提供しています。工事実務40年の実績を持ち、累計5,000件以上の見積もり精査と豊富な施工経験に基づくノウハウがあります。
現在、原状回復の見積もりが適正か、不要な工事項目が含まれていないかを無料で診断しています。コスト削減の第一歩として、ぜひお気軽にご相談ください。
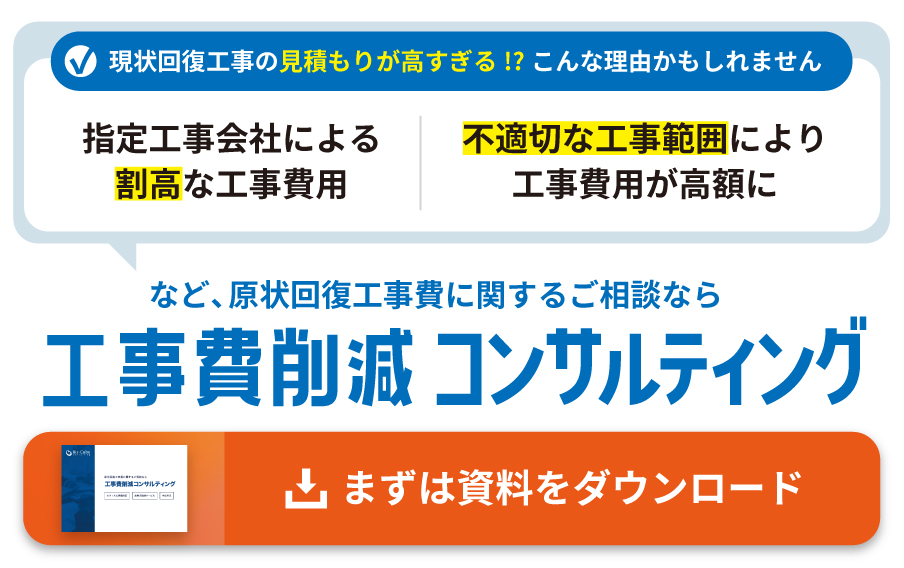
まとめ|オフィス空室率を理解してコスト削減に活かそう
オフィス空室率は、賃料交渉・移転戦略・空室対策の意思決定を支える重要な指標です。
- 空室率をモニタリングすることで、賃料交渉や移転タイミングを見極められる。
- 高い空室率を背景に、より有利な条件で契約できる可能性がある。
- 空室対策としてのリノベーションや設備改善は、企業価値の向上にも寄与する。
オフィス空室率を戦略的に活用することで、コスト削減と競争力強化を同時に実現できます。
オフィス空室率を踏まえて、賃料は適正か確認しましょう
オフィス空室率は、賃料交渉や契約条件の見直しを行ううえで重要な判断材料です。
特に、空室率が高いエリアでは、オーナーが条件を柔軟に見直す可能性が高まります。しかし、空室率の状況にかかわらず実際には「相場より高い賃料を払い続けている」ケースも少なくありません。
ビズキューブ・コンサルティングでは、250万件の市場募集賃料データと15万件の実態分析賃料データに基づき、賃料の妥当性を無料で診断しています。
- 現在の賃料は市場水準と比べて適正か?
- 契約条件の見直しで、どれくらいコスト削減できる可能性があるか?
こうした疑問を、データに基づいて明確化します。 賃料の見直しは、早めの対応が効果的です。まずは無料の賃料適正診断で、コスト削減の可能性を確認してください。
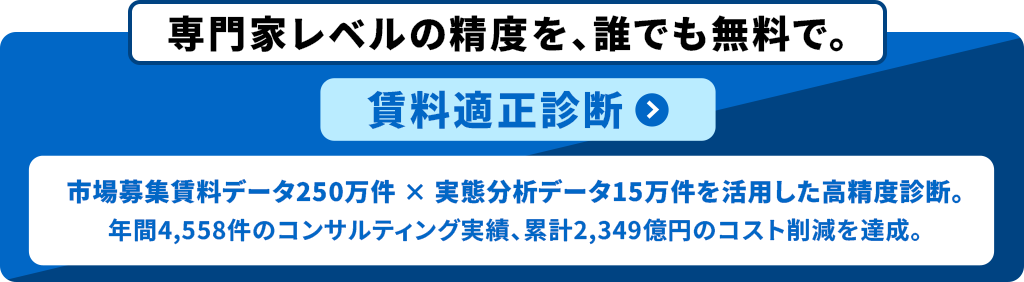
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。











 人気記事ランキング
人気記事ランキング

