年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する不動産関連
テナント定期借家契約の中途解約ガイド!可否判断・費用・注意点をわかりやすく解説

- 目次
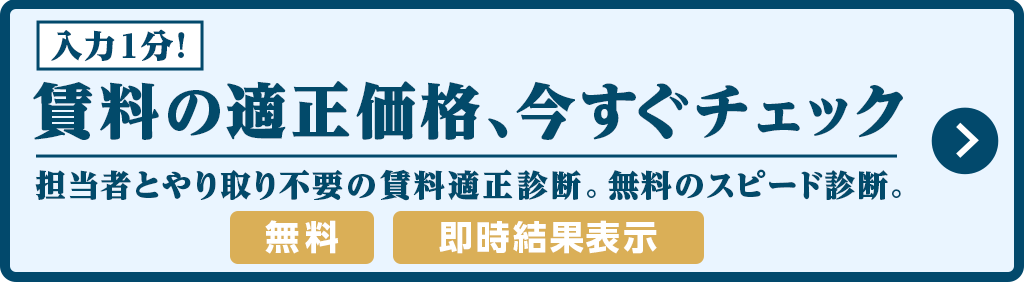
定期借家・借地契約を途中で解約したいと考えている方へ。原則として解約はできませんが、例外的に認められるケースや対応方法があります。
引越しや事業の都合で、契約期間中に賃貸物件や土地を手放さなければならない状況になることは珍しくありません。
この記事では、定期借家・借地契約の中途解約に関する疑問を解消すべく、以下の内容を解説します。
- 定期借家・借地契約とは何か
- 中途解約が可能なケース
- 中途解約の手続き
- 注意点やトラブル発生時の対応
定期借家・借地契約を検討中の方、契約期間中に解約が必要になった方は、ぜひ参考にしてください。
定期借家契約に関する基礎知識
賃貸物件の契約方法には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
ここでは、定期借家契約について特徴を交えて解説します。
そもそも定期借家契約とは
定期借家契約とは契約期間が決められた借家契約のこと。民法の特別法である「借地借家法」により定められています。
期間満了にともない契約終了となる仕組みで、一般的な普通借家契約とは異なり更新は行われず、契約終了時に借主は物件を明け渡さなければなりません。
定期借家契約の主な特徴
- 契約を延長するには貸主・借主双方の合意が必須
定期借家契約は、自動更新を前提としていない契約のため、契約延長には貸主・借主双方の合意が必要です。
普通借家契約の場合、借主の希望で契約を更新できるのが通常で、貸主は正当な事由がない限り更新の拒絶はできません。
- 貸主から借主へ契約終了の事前通知が必要
定期借家契約では、期間満了後に賃借人が代わりの物件を探したり、再契約の交渉をしたりする必要があるため、契約終了には貸主から借主への事前通知が必須です。
事前通知が行われなかった場合、借主は契約期間経過後も物件を利用でき、貸主は契約の終了を主張できません。
通知のタイミングは、1年以上の定期借家契約の場合、期間満了を迎える半年~1年前までに行う必要があります。
- 1年未満などの短期や、長期の契約も可能
普通借家契約では2年や3年といった契約期間が一般的ですが、定期借家契約は3カ月や半年など、1年未満の契約もできるのが特徴です。
そのため、期間の決まっているポップアップストアの出店などのシーンで利用されます。また、20年以上など長期の定期借家契約も可能で、その期間に上限はありません。
| 項目 | 定期借家契約 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 明確に定められている | 定めがない(更新あり) |
| 更新 | 原則なし | 借主に更新拒絶権あり |
| 解約 | 原則不可 | 借主はいつでも解約可能 |
事業用物件を定期借家契約で借りるメリット・デメリット
事業用の賃貸物件を探す場合、定期借家契約を活用するケースもあります。
こちらでは、事業用物件を定期借家契約で借りるメリットやデメリットを解説します。
メリット
定期借家契約できる物件には3カ月間~半年といった短期間で借りられる物件が多く、期間限定で出店するケースで利用しやすいのが魅力です。ポップアップストアやサテライトショップを短期間出店し、利用客の様子を確認する際にも有効活用できます。
5年以上、10年以上などの長期の定期借家契約を目的とした定期借家物件では入居者を集めるために値下げを行うことがあり、周辺地域の相場よりも安い賃料で好条件の物件を借りられる可能性があります。
普通借家契約で発生する2年ごとの更新料が不要な点もメリットです。
デメリット
定期借家契約には、途中解約や再契約が原則できないというリスクがあります。再契約とは、同じ物件で契約期間満了後に再び定期借家契約を結ぶことを指します。契約内容に再契約不可と規定されている場合や、トラブルを起こして再契約を拒否された場合は、借主は新たな物件を探さなければなりません。
また、契約期間の満了後に再契約する場合も、出費が多くなりやすい点がデメリットです。
具体的には、敷金、礼金、保証金など、入居時に支払った費用をもう一度請求される可能性があります。一定の期間で投資したコストを回収できるか見極めが必要です。再契約時には、賃料を値上げされるなど、条件が変わるおそれもあります。
定期借地契約の基本

土地を借りて利用したいけれど、所有権までは必要ない…そんな時に活用できるのが「定期借地権」です。定期借地権とは、文字通り一定期間、土地を借りて利用できる権利のこと。契約期間満了後は、更地にして地主に土地を返還する必要があります。
定期借地権には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 一般定期借地権: 住宅、アパート経営など、幅広い用途で利用可能。契約期間は自由に設定できます。
- 事業用定期借地権: オフィスビルや工場など、事業用施設の建設を目的とする場合に設定。契約期間は10年以上50年以下と定められています。
- 建物譲渡特約付借地権: 契約期間満了時に、地主が土地の買取を請求できる権利が付与されたもの。一般定期借地権と同様に、住宅や事業用施設など幅広い用途に利用できます。
それぞれの定期借地権は、契約期間や更新の有無、建物の買取請求権など、異なる特徴を持っています。土地利用の目的や期間などを考慮し、最適な定期借地権を選択することが大切です。
| 種類 | 契約期間 | 目的 | 更新 | 建物買取請求件 |
| 一般定期借地権 | 自由に設定可能 | 住宅、店舗、事務所など | 原則なし(特約による) | なし |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年以下 | 事業用施設 | 原則なし(特約による) | なし |
| 建物譲渡特約忖借地権 | 自由に設定可能 | 住宅、店舗、事務所など | 原則なし(特約による) | あり |
定期借地契約のメリット・デメリット
定期借地権は、所有権を取得するよりも手軽に土地を利用できるという魅力があります。しかし、メリットだけでなくデメリットも理解した上で契約することが重要です。
事業用物件を定期借地契約で借りるメリット・デメリット
メリット
- 初期費用を抑えて土地活用が可能:
土地所有権を取得する場合に比べて、定期借地権は初期費用を大幅に抑えられます。土地購入資金が不要なため、事業資金を建物の建設や設備投資に充てることができます。
- 固定資産税の負担軽減:
定期借地権を設定している場合、固定資産税等の負担は地主になります。借主は土地にかかる税金を気にすることなく、事業に専念できます。
- 計画的な土地利用:
契約期間が明確に定められているため、期間を定めて土地を活用したい場合に最適です。事業計画に合わせて期間を設定することで、無駄なく土地を利用できます。
デメリット
- 契約期間満了時の土地返還義務:
契約期間満了時には、更地にして土地を返還する義務があります。建物を解体する費用や、移転先を探す手間がかかる点は留意が必要です。
- 土地利用の制限:
地主の意向によっては、建物の種類や用途、高さなどに制限が課される場合があります。契約前に、どのような制限があるのかをしっかり確認することが重要です。
- 更新の可否:
一般定期借地権や事業用定期借地権の場合、原則として契約の更新は認められていません。長期的な事業展開を考えている場合には、更新の可能性についても事前に検討する必要があります。
定期借地契約は、土地の所有形態の一つとして、様々なメリット・デメリットがあります。土地活用を検討する際には、自身の状況や目的に合った選択をすることが重要です。
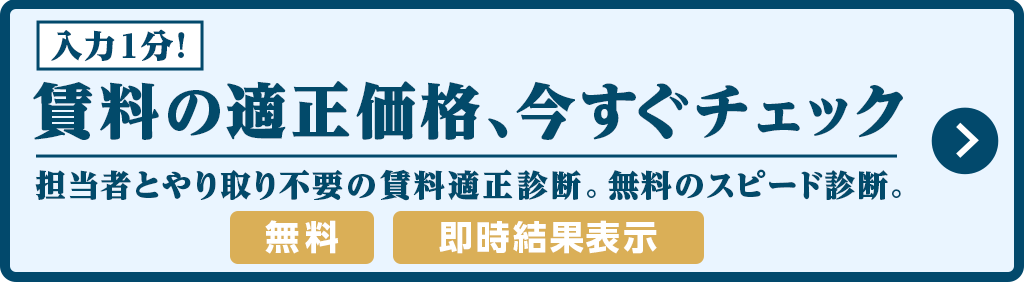
定期借家契約は途中解約できる?
定期借家契約を結ぶ場合には、解約権留保特約に関する理解が必須です。
ここでは、定期借家契約の途中解約に関する原則と例外についてポイントをご紹介します。
原則的に途中解約は認められない
原則として、定期借家契約の期間中に途中解約はできません。
定期借家契約とは期間の定めのある賃貸借契約であり、途中解約を認めると、「残存期間の賃料が受け取れない」など、大家さんや建物のオーナーなどの貸主の立場が不利で不安定になるためです。

ただし、以下の場合には中途解約が認められることがあります。
- 契約書に中途解約に関する条項がある場合
- 貸主と借主が合意した場合
- やむを得ない事情がある場合
定期借家契約の中途解約を可能にする特約
定期借家契約は、原則として契約期間中の解約はできません。しかし、ライフスタイルの変化や転勤など、やむを得ず引っ越しが必要になるケースも考えられます。
そこで重要なのが、契約時に「解約権留保特約」を盛り込んでおくことです。
解約権留保特約とは?
借主からの途中解約を可能にする
解約権留保特約とは、一定の条件の下で、借主または貸主の都合で契約期間中に解約できる権利をあらかじめ契約書に明記しておくものです。ただし、この特約は借主側にのみ認められるものであり、貸主側から契約を打ち切ることはできません。
特約の内容は、以下の点を明確に定めておく必要があります。
- 解約の申し入れ期間
解約を希望する場合は、少なくとも〇か月前までに貸主へ申し入れる必要がある、といった具合に具体的な期間を設定します。
- 違約金の有無や金額
中途解約する場合には、違約金として賃料〇か月分を支払う、といった条件を定めることができます。
特に、事業用物件を借りる場合は、公正証書に解約権留保特約を盛り込むことが一般的です。
その他の途中解約方法
解約権留保特約以外に、以下の方法で途中解約が認められる場合があります。
- 合意解約
貸主が合意すれば、契約期間中でも解約が可能です。ただし、貸主の承諾を得るためには、新しい借主を自分で探す、残りの契約期間分の賃料を支払うなどの条件が提示されることがあります。また、解約承諾料が発生する可能性もあります。
- 例外的な中途解約
借地借家法では、居住用の定期借家契約で、床面積が一定以下の場合、やむを得ない事情があれば、借主からの申し出で中途解約が認められる場合があります。
定期借家契約を結ぶ際は、解約に関する条項をよく確認し、将来的な変化にも対応できるよう、事前に準備しておくことが大切です。
事業用定期借地権における中途解約
事業用定期借地権では、当事者間での合意か、契約に中途解約条項を設けることが不可欠です。この条項には、解約時の違約金の有無や額、建物買取の有無などを明確に記載しておく必要があります。ただし、貸主側からの一方的な解約は、借主の保護を目的とした借地借家法の趣旨により、原則として認められていません。
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権の中途解約
一般の定期借地権や建物譲渡特約付借地権において、中途解約条項がない場合は、合意解約が基本となります。特に、建物が滅失した場合などのやむを得ない事情が生じたときに、双方の理解のもと合意解約が検討されることがあります。このような状況では、適切な法的手続きを踏むことで、双方にとって円滑な解決を図ることが重要です。
貸主側からの解約は、借主の保護を図る借地借家法の趣旨から、原則として認められません。
中途解約条項を設ける場合は、弁護士等の専門家に相談し、内容を慎重に検討することが重要です。
借主側からの中途解約の手順
定期借地契約の中途解約は、借主・貸主双方にとって大きな影響を及ぼすため、適切な手続きを踏むことが重要です。
合意解約の場合
貸主と解約条件を交渉: 解約時期、解約に伴う金銭の支払い(解約承諾料など)、建物の取り扱いについて貸主と交渉し、合意に至る必要があります。
合意書の作成
解約条件を明確にするために、合意書を作成します。合意書には、土地の情報、解約日、解約承諾料、敷金残金、損害金などの項目を記載します。
解約権留保特約がある場合
契約内容の確認: 契約書に記載された解約権留保特約の内容を確認します。解約事由、解約通知期間などが定められています。
解約通知: 契約書で定められた期間前までに、貸主に対して解約通知を行います。解約通知は書面で行い、貸主に確実に届くよう内容証明郵便を利用するなど、配達記録が残る方法で送付することが望ましいです。
貸主側からの中途解約の手順 (借主の債務不履行の場合)
借主が地代滞納などの債務不履行を起こした場合、貸主は契約を解除し、土地の明け渡しを求めることができます。
催告解除
1. 内容証明郵便による催告
貸主は、借主に対して債務の履行を催告する通知を内容証明郵便で送付します。催告には、履行期限を明確に記載する必要があります。
期間内に債務が履行されない場合の解除
借主が履行期限までに債務を履行しない場合、貸主は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができます(民法541条)。
2. 土地の明け渡し請求
契約解除後、貸主は借主に対して土地の明け渡しを請求します。
土地明渡請求訴訟、強制執行: 借主が土地の明け渡しに応じない場合、貸主は裁判所に土地明渡請求訴訟を提起し、判決に基づき強制執行を行うことができます。
3. 無催告解除
民法542条、612条の内容に該当する場合: 借主が土地を著しく毀損した場合など、民法で定められた要件に該当する場合、貸主は催告なしに契約を解除できます。
無催告解除特約がある場合: 契約に無催告解除特約がある場合、特約に定められた事由が発生したときは、貸主は借主に解除の意思を伝え、明け渡しを求めることができます。
注意点
中途解約の手続きは、法律や契約内容によって異なる場合があります。
トラブルを避けるため、中途解約を行う場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
定期借地契約の中途解約以外の選択肢
定期借地契約は、原則として契約期間中の解約は難しいもの。しかし、状況によっては、中途解約以外の方法で土地を手放すことも可能です。
借地権の売却
地主の承諾を得ることで、借地権を第三者に売却・譲渡することができます。
- 譲渡承諾料: 一般的に、借地権価格の1割程度が相場となります。ただし、地主との交渉や契約内容によって異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。
- 借地専門の買取業者: 専門業者に依頼することで、売却活動の手間を省き、スムーズな取引を進めることができます。また、地主との交渉を代行してくれるケースもあります。
借地権の相続
借地権は、相続の対象となる財産の一つです。相続が発生した場合、相続人は借地権を引き継ぐことができます。
ただし、地主の承諾が必要となるケースもあるため、相続手続きと並行して、地主への連絡や手続きも進める必要があります。
借地権の更新
定期借地契約は、原則として契約期間満了後は更地にして土地を返還する必要があります。しかし、契約内容によっては、更新条項が設けられている場合もあります。
更新を希望する場合は、契約内容をよく確認し、地主との交渉が必要となります。更新料の発生や、契約条件の変更なども考えられるため、事前に十分な検討が必要です。
定期借地契約は、契約期間が長期にわたるため、途中で状況が変化することも少なくありません。 中途解約以外にも様々な選択肢があることを理解し、状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。
事業用物件を定期借家契約で借りる際の注意点
- 数年後の移転の可能性を視野に入れておく
定期借家契約で物件を借りた場合、期間満了時に別の物件へ移転する可能性があります。
そのため、数年後の移転を想定し、店舗経営で起こり得るリスクに備えておくことが重要です。
例えば、既存の店舗で獲得した顧客を失うリスクや、原状回復や移転で高額な費用がかかるリスクなどへの備えは欠かせません。
- 長期の場合は途中解約を認める特約を結ぶか検討する
事業用の場合、原則的に特約がなければ途中解約は認められないため、途中解約に関する特約を結ぶか事前に検討する必要があります。特約がない状態で退去する場合は、契約期間満了までの家賃を請求されるおそれがあります。特約を結ぶ場合は、「○カ月分の家賃を支払うことで途中解約が可能」などの条項を入れるのが一般的です。
- 契約満了後の再契約には、敷金、礼金、保証金などの費用が再度発生する可能性
契約満了後に再契約を行う際は、新規契約として扱われるため、以下の費用が再度発生する可能性があります:
- 敷金(通常賃料の6~12ヶ月分)
- 礼金(賃料の1~2ヶ月分)
- 保証金(賃料の10~12ヶ月分)
- 仲介手数料
そのため、事業計画を立てる際には、これらの追加費用も考慮に入れる必要があります。
適正な賃料で、賃貸契約を有利に。専門家のサポートを活用しませんか?
定期借家・定期借地契約を検討する際には、契約内容や解約条件だけでなく、適正な賃料設定も重要なポイントです。
ビズキューブ・コンサルティングの賃料適正化コンサルティングでは、契約条件の見直しなどを通じて、コスト削減と事業の最適化を実現します。
「現在の賃料が適正なのか知りたい」「契約更新時に条件を見直したい」など、お悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
『賃料適正化コンサルティング』のご提供だけでなく、もし撤退・解約が確定した場合でも、『撤退・解約に伴う窓口業務や後継テナントの誘致などのサポート』も行っております。
物件周りでお困りの場合はお気軽にご相談ください。
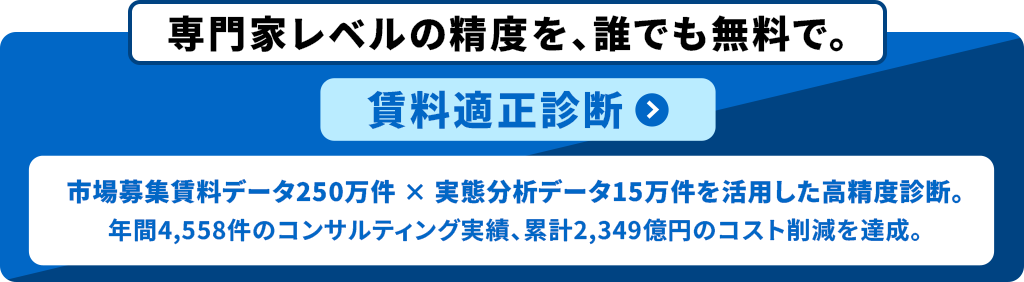
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。











 人気記事ランキング
人気記事ランキング

