年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する店舗経営
オフィス原状回復の費用と範囲を徹底解説|トラブル回避とコスト削減のポイント
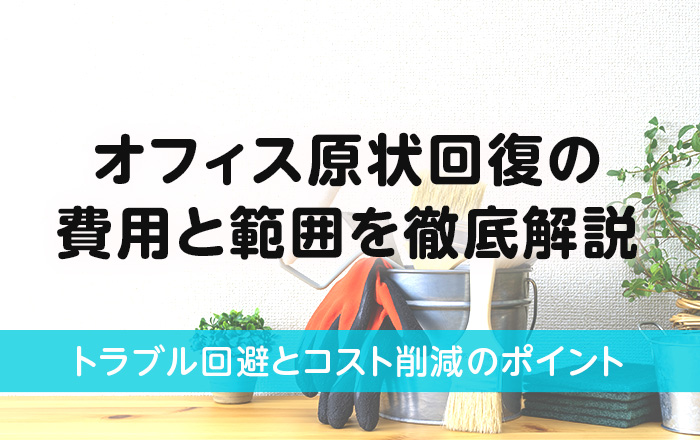
- 目次
この記事は、初めてオフィスの退去・移転を検討している中小企業の経営者や総務担当者の方に向けて、原状回復の基本から費用対策までをわかりやすく解説します。
原状回復とは?オフィス退去時に必要な対応を解説
オフィス退去時に必要となる「原状回復」とは、賃貸借契約に基づき、借主が物件を契約開始時の状態に戻す義務を指します。退去に際しては、契約書の内容や特約を事前に確認し、必要な対応を把握しておくことが大切です。契約書の内容や特約を事前に確認しておくことで、原状回復に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
原状回復の定義と法律上の位置づけ
原状回復は、民法第621条に基づく借主の義務の一部です。借主は物件を適切に使用し、契約終了時には元の状態に戻す必要があります。ただし、通常損耗や経年劣化(例:照明の劣化、壁紙の色あせなど)は原状回復の対象外とされることが一般的です。
一方で、賃貸借契約書に記載された「特約」によって、原状回復の範囲や内容が大きく変わる可能性があります。たとえば、「スケルトン戻し(内装をすべて撤去し、コンクリートむき出しの状態に戻す)」が求められるケースでは、工事費が大幅に増加することもあります。
参考:e-Gov法令検索「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)」
オフィスにおける原状回復の範囲
原状回復の対象となる範囲は、契約内容や使用状況によって異なりますが、一般的には以下のような項目が含まれます。
| 該当箇所 | 対応内容 |
| 壁紙や塗装 | 壁に傷や汚れがある場合は、補修や再塗装が必要です。特に、ポスターや棚の設置による穴や日焼け跡などは、原状回復の対象となることが多く、張替え費用が発生します。 |
| 床材(カーペット・フローリングなど) | 椅子や什器の移動による擦り傷、飲食によるシミなどがある場合は、張替えや部分修繕が求められます。カーペットの場合、1坪あたりの張替え費用は約5,000〜10,000円が目安です。 |
| 配線・設備 | 照明器具、空調設備、LANケーブルなどを取り外した場合は、元の状態に戻す必要があります。特に、天井や壁に穴を開けて設置した設備は、撤去後の補修も含めて原状回復の対象になります。 |
これらの工事費は、貸主・借主間の費用負担区分によって異なります。特に契約書に記載された特約条項の内容によって、借主が負担すべき範囲が変わるため、注意が必要です。
また、使用年数や設備の資産価値の減少を踏まえ、費用調整が行われるケースもあります。費用負担の妥当性を判断するためには、契約書の内容を精査し、必要に応じて原状回復の専門家による診断を受けることが推奨されます。
「借りたときの状態に戻す」の誤解
「借りたときの状態に戻す」という表現は、原状回復の場面で誤解を招きやすい言い回しです。実際には、通常使用による自然な劣化については、借主が修繕費を負担しないケースが多くあります。
一方で、過失による損傷(例:什器の設置による壁の穴、飲食によるカーペットのシミ、配線撤去による天井の破損など)は、借主の責任で修繕が必要になる可能性があります。
こうした責任の範囲は契約書の特約によって定められているため、退去前には契約書をよく読み、貸主や管理会社と事前にすり合わせを行うことが重要です。
契約書の特約に要注意!原状回復の義務と法的リスク
オフィス退去時の原状回復に関する責任は、賃貸借契約書に記載された「特約」によって大きく左右されます。特に中小企業の経営者や総務担当者にとっては、契約書の読み解きが難しく、退去時に予期せぬ費用負担が発生するリスクもあります。こうしたトラブルを防ぐには、専門家に依頼して特約条項の内容と法的効力を事前に確認しておくことが重要です。
契約書に記載される原状回復に関する特約条項の例
賃貸借契約書には、原状回復に関する特約が記載されていることが多く、退去時の費用負担や対応範囲に直接影響します。代表的な特約には以下のようなものがあります。
| 特約条項 | 内容 |
| 全額負担特約 | 退去時の原状回復費用を借主が全額負担するという内容。例えば、通常使用による損耗も含めて、壁紙・床材・設備の修繕費をすべて借主が支払うケースがあります。 |
| 免除特約 | 契約期間が長期(例:3年以上)である場合や、設備の状態が次の入居者にも使用可能と判断される場合など、一定条件を満たすことで原状回復義務が免除される条項です。 |
| 修繕範囲の明確化特約 | 借主が負担する修繕工事の範囲を具体的に定めた条項。たとえば、「壁紙の張替えは借主負担だが、天井の塗装は貸主負担」といったように、項目ごとに責任範囲が明記されていることがあります。 |
実際の賃貸借契約書に見られる記載例
以下は、実際の賃貸借契約書で見られる原状回復に関する特約の記載例です。
| 特約条項 | 記載例 | 補足 |
| スケルトン戻しに関する特約 | 借主は、本契約の終了時において、本物件を契約締結時の状態に復旧し、天井・壁・床・間仕切り・造作・設備等をすべて撤去し、スケルトン状態(コンクリート躯体現し)にて明け渡すものとする。 | このような条項がある場合、内装解体・設備撤去・廃材処分などの費用が高額になる傾向があるため、工事費削減コンサルティングの活用が有効です。 |
| 敷金から原状回復費用を相殺する特約 | 本契約終了時において、貸主は、借主が負担すべき原状回復費用を敷金から控除し、残額がある場合に限り、これを借主に返還するものとする。 | このような条項がある場合、見積もりの妥当性や工事内容の妥当性を事前に確認しておくことが、敷金返還トラブルの防止につながります。 |
これらの特約は、文言が抽象的・包括的である場合、裁判で無効と判断される可能性もあるため、契約締結前または退去前に、契約書の具体性と明確性を確認することが重要です。
経年劣化への対応は契約書によって異なる
原状回復の範囲には、「経年劣化」や「通常損耗」が含まれるかどうかが重要なポイントです。
民法では、通常使用による損耗は借主の負担外とされていますが、契約書に「経年劣化も借主負担」と明記されている場合、修繕義務が発生する可能性があります。たとえば、照明の寿命や床の摩耗などが「通常損耗」として免除されるか、「修繕対象」とされるかは契約書の文言次第です。
民法改正による影響と注意点
2020年の民法改正により、賃貸借契約における借主・貸主の義務が明文化されました。特に以下の点に注意が必要です。
| 民法改正による影響 | 詳細 |
| 通常損耗の扱いが明文化 | 改正後の民法では、「通常の使用による損耗や経年劣化は借主の原状回復義務に含まれない」と明記されました。これにより、借主が不必要な修繕費を負担するリスクが減少しています。 |
| 特約の有効性には厳格な条件が必要 | 借主が負担する範囲が契約書に具体的かつ明確に記載されていること、借主がその内容を理解し合意していることが求められます。 |
契約内容に不安がある場合の相談先
契約内容に不安がある場合は、弁護士(不動産法務に詳しい専門家)や宅地建物取引士、不動産管理会社の担当者などに相談することをおすすめします。例えば、以下のようなケースでは専門家の助言が有効です。
- 契約書に記載された特約の意味や法的効力が不明な場合
- 原状回復の範囲や費用負担について、貸主と認識が食い違っている場合
- 敷金返還の条件や相殺額に納得できない場合
- 民法改正の影響で、従来の契約内容との違いが気になる場合
専門家に相談することで、法的根拠に基づいた判断ができるようになり、不要な費用負担やトラブルを未然に防ぐことが可能になります。特に退去前のタイミングで相談しておくと、交渉や準備がスムーズに進みます。

よくあるトラブル事例とその回避策
オフィス退去時の原状回復に関しては、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
| トラブル事例 | 詳細 |
| 敷金返還トラブル | 退去後、貸主から原状回復費用として高額な請求があり、敷金がほとんど返還されないケース。たとえば、壁紙の軽微な汚れや床の通常使用による摩耗まで借主負担とされることがあります。 |
| 修繕範囲の認識違い | 借主は「通常損耗」と認識していた箇所について、貸主が「修繕対象」と主張することで、費用負担を巡って対立が生じるケース。特に、賃貸借契約書に修繕範囲が曖昧に記載されている場合に起こりやすいです |
トラブルを防ぐための具体的な対策
| 対策 | 詳細 |
| 契約書の事前確認 | 退去前に、賃貸借契約書の「原状回復義務」や「特約条項」を丁寧に読み込みましょう。たとえば、「通常損耗は借主負担外」と記載されているか、「全額負担特約」があるかなどを確認し、不明点は貸主や管理会社に質問しておくことが重要です。 |
| 業者との綿密な打ち合わせ | 原状回復工事を依頼する業者とは、現地調査の段階で修繕箇所や工事内容を詳細に確認しましょう。 |
事前に、以下の項目を契約書や貸主に確認しておくと安心です。
| 確認項目 | 具体例 |
| どの箇所が修繕対象となるのか | 壁紙、床材、天井、設備など |
| 修繕の理由 | 通常損耗か、借主の過失によるものか |
| 工事の方法と範囲 | 全面交換か部分補修か |
| 見積もりの内訳 | 材料費・施工費・諸経費など |
| 工事の必要性と妥当性 | 貸主の要求に基づくものか、業者の判断か |
見積もりの内訳が不明瞭な場合は、項目ごとの費用や工事の必要性について説明を求めることで、不要な工事を防げます。
退去は単なる事務手続きではなく、契約理解と交渉力が求められる重要な場面です。工事費削減コンサルティングを活用することで、費用負担を抑え、スムーズな退去を実現できます。不安や費用削減に関心がある方は、ぜひ一度、無料相談からお試しください。
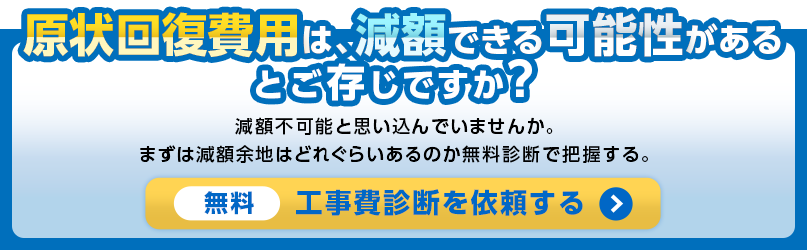
原状回復工事の区分と費用負担者
オフィスの原状回復工事には、一般的に「A工事」「B工事」「C工事」という3つの区分が存在します。これらは、工事の内容・責任主体・費用負担者によって分類されており、退去時の費用精算や工事手配に大きく関わるため、事前に理解しておくことが重要です。
A工事:貸主が実施・負担する工事
A工事とは、ビルオーナー(貸主)が主体となって実施し、費用も貸主が負担する工事です。主に、建物全体の維持管理や法令に基づく設備更新などが該当します。
対象範囲の例:
- 共用部の空調設備の更新
- エレベーターの保守点検
- 防災設備の改修
借主が直接関与することは少なく、原状回復とは別枠で扱われることが一般的です。そのため、A工事に関する費用負担や施工内容は、契約書上で明確に区分されているかを確認することが重要です。
B工事:貸主が実施し、借主が費用を負担する工事
B工事は、貸主が工事を手配・管理するものの、費用は借主が負担する工事です。主に、借主専有部の原状回復や設備撤去などが該当します。
対象範囲の例:
- 借主が設置した内装・什器の撤去
- スケルトン戻しに伴う造作解体
- 電気・空調・LAN配線の撤去と復旧
この区分では、貸主指定の業者が施工するケースが多く、見積もりの妥当性や工事内容の精査が重要です。
費用が高額になる傾向があるため、工事費削減コンサルティングの活用が有効です。特に、複数見積もりの取得が難しい状況では、第三者による診断がコスト適正化に役立ちます。
C工事:借主が実施・負担する工事
C工事は、借主が自ら業者を選定し、施工・費用負担を行う工事です。主に、入居時の内装工事や退去時の軽微な修繕などが該当します。
対象範囲の例:
- パーティションの設置・撤去
- 什器の移設・処分
- 床材の部分補修
借主が自由に業者を選べるため、コスト調整やスケジュール管理がしやすい一方で、貸主の承諾が必要な場合もあるため、事前の確認が欠かせません。また、C工事の内容がB工事に該当すると判断されるケースもあるため、契約書や工事区分表の確認が重要です。
工事区分の確認と費用負担の整理がトラブル防止のカギ
原状回復工事においては、どの工事がA・B・Cに該当するかを契約書やビル管理会社との打ち合わせで明確にしておくことが重要です。特にB工事は、借主負担でありながら貸主指定業者による施工となるため、費用の妥当性や工事内容の透明性を確保する必要があります。
また、工事区分が曖昧なまま進めてしまうと、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
- 想定外の高額請求(B工事)
- 工事内容の認識違いによる再施工
- 敷金返還額への影響
こうしたリスクを回避するためにも、退去前には契約書の確認と、工事費削減コンサルティングの活用が有効です。
原状回復にかかる費用相場と内訳
オフィスの原状回復にかかる費用は、物件の広さや状態、工事内容、依頼する業者によって大きく異なります。初めて退去を経験する中小企業の経営者や総務担当者にとっては、事前に費用の相場感を把握し、予算を立てておくことが重要です。
以下では、2025年時点の最新相場をもとに、坪単価の目安、工事内容別の費用内訳、そして補助金・助成金の活用可能性について解説します。
2025年時点の坪単価の目安と規模別の費用感
原状回復費用は一般的に「坪単価」で算出されます。地域や業者によって差はありますが、以下が目安です。
| オフィス規模 | 坪単価の目安 | 想定条件 |
| 小規模(〜30坪) | 約4.0〜6.0万円 | 一般的な内装、標準設備 |
| 中規模(31〜100坪) | 約6.0〜11.0万円 | 床・壁・天井の更新含む |
| 大規模(101坪〜) | 約11.0〜15.0万円 | 高機能設備やスケルトン戻し含む |
物件のグレードや立地、契約条件によっては、坪単価が高額になるケースもあります。自社の坪数をもとに概算し、複数業者の見積もりを比較することで、適正価格を把握しやすくなります。
工事内容別の費用内訳
原状回復工事にはさまざまな項目が含まれます。代表的な工事項目と単価の目安は以下の通りです。
| 工事項目 | 単価目安 | 備考 |
| 壁紙(クロス)張替え | 1,400〜2,000円/㎡ | 素材・厚みにより単価変動 |
| タイルカーペット張替え | 3,500〜5,000円/㎡ | 接着方法で単価変動 |
| 天井塗装 | 1,800〜2,600円/㎡ | 下地状況で単価変動 |
| 配線復旧工事 | 40,000〜150,000円/件 | LAN・電源系統など |
| 設備の取り外し | 30,000〜80,000円/件 | 空調・照明・什器など |
これらの費用は、オフィスの状態や工事の難易度によって変動します。必ず複数業者から見積もりを取得し、工事内容と金額の妥当性を確認しましょう。
オフィス移転向けの補助金・助成金の活用
原状回復費用の負担を軽減する手段として、自治体や公的機関が提供する補助金・助成金制度の活用も検討できます。特に以下のような制度が、オフィス移転や設備改修に関連して対象となる可能性があります。
| 制度 | 詳細 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が販路開拓や業務効率化を目的として行う取り組みに対して、費用の一部を補助する制度です。原状回復に伴う設備撤去や改修が、事業目的(業務効率化・販路拡大等)と合致する場合に限り、補助対象となる可能性があります。制度ごとに対象範囲が異なるため、事前確認が必要です。 |
| ものづくり補助金 | 中小企業が生産性向上や業務革新を目的として行う設備投資に対して、費用の一部を補助する制度です。原状回復に伴う設備更新や、オフィス移転に伴う業務プロセス改善を目的とした改修が対象となる可能性があります。 |
| IT導入補助金 | 中小企業が業務効率化やDX推進を目的としてITツールを導入する際に、費用の一部を補助する制度です。オフィス移転に伴う業務管理システムの導入や、契約管理・工事管理のクラウド化などが対象となる可能性があります。 |
※補助金制度は年度ごとに内容が変更される場合があります。2025年度の情報をもとに記載していますが、最新情報は公式サイトをご参照ください。
これらの制度は、申請タイミングや対象条件が厳密に定められているため、事前に制度内容を確認し、専門家に相談することが推奨されます。また、補助金の活用を前提とした工事計画を立てることで、費用の最適化と資金繰りの安定化につながります。
参考:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金」
参考:全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「IT導入補助金2025」
原状回復にかかる期間とスケジュールの立て方
オフィス退去に伴う原状回復工事では、工事期間の見積もりとスケジュール設計がトラブル回避の鍵となります。特に中小企業では、業務への影響を最小限に抑えるためにも、事前の計画が不可欠です。
ここでは、一般的な工事の流れ、退去通知から逆算したスケジュール例、そして急ぎの場合の対応策について具体的に解説します。
原状回復工事の流れと各工程の目安
原状回復工事は、以下のステップで進行するのが一般的です。
| ステップ | 所要期間 | 内容 |
| 現地調査 | 約1日 | 業者がオフィスを訪問し、壁・床・天井・設備の状態を確認。電気・空調・配線の撤去範囲や、スケルトン戻しの有無などもこの段階で判断されます。 |
| 見積もり提出 | 約3〜7日 | 調査結果をもとに、工事項目ごとの費用を記載した見積書が提出されます。内訳の明確さや、通常損耗の扱いに注意して確認しましょう。 |
| 契約締結 | 約1日 | 見積もりに納得したら、正式に契約を締結。工期・費用・支払い条件・追加費用の有無などを明文化しておくことが重要です。 |
| 工事準備 | 約2〜3日 | 資材の手配、作業員のスケジュール調整、ビル管理会社への工事申請などを行います。※ビルによっては「工事申請書」「施工業者の事前登録」「工事可能時間帯の制限」などがあるため、管理規約の確認が必須です。 |
| 工事実施 | 約5〜10日 | オフィスの広さや工事内容によって変動します。スケルトン戻しや空調・電気工事が含まれる場合は1〜2週間かかることもあります。 |
| 完了検査 | 約1日 | 貸主または管理会社の立ち会いのもと、工事内容を確認。不備があれば再工事が必要になるため、余裕を持った日程設定が望ましいです。 |
この流れを把握しておくことで、退去日から逆算した計画が立てやすくなります。
退去通知から逆算したスケジュール例(通知が1ヶ月前の場合)
退去通知を1ヶ月前に提出する場合、以下のようなスケジュールが想定されます。
| 時期 | やること |
| 退去通知提出(30日前) | 管理会社・貸主に退去の意思を伝える |
| 通知後1週間以内 | 業者に現地調査を依頼、見積もり取得 |
| 通知後10日以内 | 見積もり確認後、契約締結 |
| 通知後2〜3週目 | 工事準備・資材手配・ビル申請など |
| 退去日2週間前 | 原状回復工事スタート(5〜7日間) |
| 退去日1〜2日前 | 完了検査・鍵の返却・引き渡し |
なお、ビルによっては「退去30日前までに原状回復工事を完了しておくこと」と定められている場合もあるため、契約書や管理規約の確認が必須です。
急ぎの場合の対応方法(1〜2週間で退去したいケース)
急ぎの原状回復でも、段取りと交渉によって対応できる可能性があります。以下のような対応策を講じることで、短期間でもスムーズな退去が実現できます。
| 対応策 | 詳細 |
| 即日対応可能な業者を選定 | 「原状回復専門業者」や「短納期対応可」と明記された業者を事前にリストアップしておくと安心です。 |
| 短期工事プランの交渉 | 工事内容を最小限に絞る、夜間・休日工事を活用するなど、納期優先のプランを相談しましょう。 |
| 早めの現地調査依頼 | 退去通知前でも、仮見積もりや現地調査を依頼しておくことで、スムーズに着手できます。 |
| 必要最低限の工事に絞る | 貸主と協議のうえ、「次の入居者がそのまま使う設備は残置可」などの合意が取れれば、工期短縮につながります。 |
急ぎの原状回復では、「段取りの早さ」と「確認の丁寧さ」がトラブル回避のカギになります。
トラブルを避けるための事前準備と交渉術
原状回復に関するトラブルは、契約書の確認と貸主・管理会社との円滑なコミュニケーションによって未然に防ぐことが可能です。ここでは、契約書の確認ポイント、業者選定の注意点、そして交渉時に意識すべきポイントを整理します。
契約書の確認ポイントと質問例
契約書には、原状回復に関する重要な情報が記載されています。退去前に確認すべき主な項目と、貸主に対して行うべき質問例は以下の通りです。
| 確認項目 | 質問例 |
| 原状回復義務の範囲 | 「どこまで戻す必要がありますか?」 |
| 特約の内容 | 「この特約は具体的にどのような意味がありますか?」 |
| 修繕負担のルール | 「通常損耗は借主負担になりますか?」 |
| 敷金返還の条件 | 「敷金はどの条件で返還されますか?」 |
契約書の条文だけでなく、実際の運用や過去の事例も踏まえて確認することで、認識違いによるトラブルを防げます。
原状回復業者は誰が選ぶのか?
賃貸借契約書には、原状回復工事の業者選定権についても記載されていることがあります。多くのテナントでは、貸主が指定する業者での施工が求められるケースがあり、「貸主指定業者による施工」と明記されていることもあります。
一方で、業者指定がない場合や、貸主の了承が得られれば、借主が業者を選定できるケースもあります。過去に同じビルで退去したテナントが自社で業者を選定した事例がある場合、交渉の余地がある可能性もあります。
費用や工期に直結するため、業者選定の自由度については契約書で確認し、必要に応じて貸主と事前にすり合わせておくことが重要です。
貸主・管理会社との円滑なコミュニケーション
契約書の確認だけでなく、貸主や管理会社とのコミュニケーションも、原状回復をスムーズに進めるための重要な要素です。以下の対応を心がけましょう。
| 実施すべき対応 | 詳細 |
| 定期的な連絡 | 退去予定が決まったら、定期的に貸主や管理会社と連絡を取り、現在の状況を共有します。これにより、誤解を招く可能性を減少させることができます。 |
| 明確な意思表示 | 自社の意向や不安については、なるべく明確に伝えるように心がけましょう。誤解を避けるため、具体的な事例や状況を交えて説明すると良いでしょう。 |
| 問題発生時の迅速な対応 | 万が一問題が発生した場合は、すぐに連絡を取り、解決策を協議します。早期の対応がトラブルを大きくしないための鍵です。 |
| 書面による記録 | 重要なやり取りについては、メールや書面に記録を残しておくことが推奨されます。後日、確認が必要な場合に役立ちます。 |
| 柔軟な姿勢 | 払い戻しや交渉に対して柔軟な姿勢を持つことで、相手との信頼関係を構築しやすくなります。特に貸主との関係を重視し、相手の立場にも配慮することが重要です。 |
こうした事前準備と信頼関係の構築が、スムーズな退去とトラブル回避の鍵となります。
敷金返還と原状回復|損しないための実務ポイント
オフィス退去時における「敷金返還」と「原状回復費用」は密接に関係しています。契約内容や退去時の対応次第で、敷金がどこまで返還されるかが大きく変わるため、事前の理解と準備が不可欠です。
敷金返還額に影響する3つの要因
敷金は、賃貸契約時に貸主へ預ける保証金であり、退去時に原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。返還額に影響する主な要因は以下の通りです。
| 要因 | 内容 |
| 原状回復義務の履行状況 | 借主が契約に基づく原状回復義務を適切に履行しているかどうかが、返還額に直結します。たとえば、壁紙の汚れや床の傷を放置したまま退去すると、修繕費が敷金から差し引かれる可能性があります。 |
| 通常損耗の扱い | 2020年4月1日に施行された改正民法により、通常の使用による損耗(経年劣化など)は借主の負担対象外と明記されました。例えば、日焼けによる壁紙の色あせや、椅子による軽微な床の凹みなどは、敷金から差し引かれるべきではありません。 |
| 貸主の請求根拠の妥当性 | 貸主が原状回復費用を敷金から差し引く場合、その請求内容が賃貸借契約書や特約に基づいているかが重要です。たとえば、ハウスクリーニング代を敷金から差し引くには、契約書に明記されている必要があります。 |
原状回復費用との相殺の仕組み
退去時には、原状回復費用が敷金から差し引かれるのが一般的です。以下の流れで相殺が行われます。
| 原状回復費用との相殺の流れ | 内容 |
| 費用の算定 | 業者による現地調査と見積もりをもとに、原状回復にかかる費用が算定されます。たとえば、クロスの一部汚れでも全面張替えが必要とされる場合があり、費用が高額になることもあります。 |
| 敷金との相殺 | 確定した費用が敷金から差し引かれ、残額が返還されます。費用が敷金を上回る場合は、追加請求されることもあります。 |
| 記録の保管 | 原状回復の見積書や請求書は必ず保管しておきましょう。万が一トラブルが発生した際の証拠になります。退去立会時の写真や動画も有効です。 |
トラブルを避けるための準備
敷金返還に関するトラブルを未然に防ぐためには、以下の準備が効果的です。
| 準備すべきこと | 詳細 |
| 賃貸借契約書の確認 | 原状回復義務や敷金の取り扱いについて、賃貸借契約書の該当条項を事前に確認しておきましょう。特約の有無や内容も重要です。 |
| 現状記録の保存 | 入居時や退去前に、オフィスの状態を写真や動画で記録しておくことで、損傷の有無を客観的に証明できます。特に壁紙や床材、設備の状態は重点的に記録しましょう。 |
| 業者との事前協議 | 原状回復工事の内容や費用について、業者と事前に打ち合わせを行い、認識のズレを防ぎます。見積もりの内訳や工事範囲の説明を求めることが大切です。 |
| 交渉資料の準備 | 敷金返還に関する交渉では、契約書や入居時の状態を記録した写真・動画や工事見積書・請求書の控えといった記録資料をもとに自社の立場を明確に伝えることが重要です。過去の事例やガイドラインを参考にするのも有効です。 |
| スケジュールの共有 | 退去日が近づく前に、貸主や業者とスケジュールを共有し、余裕を持った対応を心がけましょう。完了検査や精算のタイミングも事前に確認しておくと安心です。 |
このような準備を行うことで、敷金返還に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去手続きを進めることができます。賃貸借契約書の理解と記録の徹底が、損をしないための最大のポイントです。
原状回復が不要になるケースも?契約書の特約を確認
賃貸借契約書に特約が設けられている場合、原状回復義務が一部または全部免除されることがあります。退去時の費用負担を軽減できる可能性があるため、契約時・退去前に必ず確認しましょう。
原状回復免除の特約例
| 特約例 | 詳細 |
| 期間限定特約 | 契約期間が3年以上など一定期間を超える場合、通常損耗や経年劣化に伴う修繕費用を借主が負担しないとする特約。 |
| 特定設備の取り扱い特約 | 家具付きオフィスなどで、設置済みの設備について「原状回復不要」とする条項。たとえば、備え付けの棚や照明器具をそのまま残して退去できるケース。 |
| 設備の使用条件に関する特約 | 設備が老朽化しており、次の入居者も同程度の状態で使用することが前提の場合、原状回復を免除する条項。 |
| 営業用施設の特殊事情による特約 | 飲食店や美容室など、業種特有の内装について、貸主が次のテナントに引き継ぐ意向がある場合、一部の原状回復を免除することがある。 |
これらの特約は、契約書に明記されている必要があり、口頭での合意や曖昧な記載では無効となる可能性があります。また、借主がその内容を十分に理解し、納得したうえで契約していることが法的にも求められます。
交渉で原状回復を減らせる可能性
契約書に原状回復義務が記載されていても、交渉によって負担を軽減できる場合があります。
| 交渉ポイント | 内容 |
| 退去理由の説明 | 経営状況の悪化や事業縮小など、合理的な事情を説明することで、貸主の理解を得られる可能性があります。 |
| 契約更新時の交渉 | 契約期間の延長と引き換えに、原状回復の条件を緩和する交渉も有効です。たとえば「次回更新時は壁紙の張替えを免除する」など。 |
| 市場状況の共有 | 工事費用の高騰や賃貸市場の空室率などを背景に、貸主にとっても早期退去や次の入居者確保が優先される場合、交渉の余地が生まれます。 |
契約時に確認すべき原状回復・敷金のポイント
賃貸借契約書を締結する際には、以下の点を必ず確認しましょう。
| 確認すべきポイント | 詳細 |
| 原状回復義務の範囲 | どの部分まで借主が修繕する必要があるか。壁紙、床材、設備などの具体的な対象を確認。 |
| 免除特約の有無 | 原状回復が不要となる条件や範囲が明記されているか。曖昧な表現は避け、具体的な金額や対象を記載しているかが重要です。 |
| 敷金・保証金の扱い | 返還条件や原状回復費用との相殺ルール。償却条項がある場合は、その金額や理由も確認。 |
| 除外条件・制限事項 | 原状回復義務に関する例外や、借主に不利な条項(例:自然損耗まで借主負担とするなど)が含まれていないかを確認。 |
これらを事前に確認し、納得したうえで契約を結ぶことで、退去時の負担やトラブルを防ぐことができます。特約の有効性は、借主が内容を理解し、合理的な理由があるかどうかで判断されるため、契約時の説明と記録も重要です。
退去前に確認したい原状回復チェックリスト
退去前には、原状回復に関する準備を漏れなく進めることが重要です。これにより、費用の予測が立てやすくなり、貸主との認識違いによるトラブルを防ぐことができます。以下のチェックリストを参考に、必要な確認を行いましょう。
退去通知前にやるべきこと
※このチェックリストは、退去前に必要な準備を整理し、費用予測や貸主との交渉をスムーズに進めるためのものです。
| 確認項目 | 詳細 |
| オフィスの現状把握(損傷箇所のリストアップ) | 壁紙の汚れ、床の傷、設備の不具合など、損傷箇所をリストアップ。写真や動画で記録しておくと、後の交渉資料になります。 |
| 契約書の再確認(原状回復・敷金条項) | 原状回復義務や敷金返還に関する条項、特約の有無を確認。特に「貸主指定業者」や「全額負担特約」があるかどうかは重要です。 |
| 工事業者のリサーチと見積もり準備 | 契約上、借主が業者を選べる場合は、原状回復の実績がある業者を複数比較。概算見積もりを取得しておくと予算計画に役立ちます。 |
| 移転スケジュールの立案と関係者への共有 | 退去日から逆算して、工事期間・検査日・引き渡し日を設定。社内の担当者やビル管理会社とも共有しておきましょう。 |
工事前に確認すべき項目
※このチェックリストは、原状回復工事の内容や費用の妥当性を事前に確認し、不要な工事や追加費用を防ぐためのものです。
| 確認項目 | 詳細 |
| 業者による現地調査の実施 | 壁・床・天井・設備の状態を確認し、工事範囲を明確化。貸主立ち会いが必要な場合もあるため、日程調整を早めに。 |
| 見積もり内容の確認(内訳・金額の妥当性) | 工事項目ごとの内訳、単価、諸経費の有無を確認。不明点は業者に質問し、追加費用のリスクを減らします。 |
| 工事範囲の明確化(通常損耗の扱い含む) | 賃貸借契約書に基づき、借主が負担すべき範囲を確認。経年劣化や通常使用による損耗は原則負担不要です。 |
| 工事スケジュールの調整と共有 | 工事開始日・完了予定日・検査日を業者とすり合わせ。ビルの工事可能時間帯(例:平日9〜17時)にも注意が必要です。 |
貸主・管理会社との確認事項
※このチェックリストは、貸主・管理会社との認識のズレを防ぎ、退去手続きや敷金精算を円滑に進めるための確認ポイントです。
| 確認事項 | 詳細 |
| 退去日の正式確認 | 賃貸借契約書に記載された通知期限や退去日を再確認。口頭ではなく、メールなどで記録を残すのが安心です。 |
| 原状回復ルールの再確認(特約の有無) | 貸主が独自のルールを設けている場合もあるため、賃貸借契約書と実際の運用に差がないか確認します。 |
| 敷金返還の条件と手続き | 返還時期、相殺の有無、精算方法などを確認。敷金の償却条項がある場合は、その金額と根拠も明確にしておきましょう。 |
| 業者選定に関する承認の有無 | 借主が業者を選べるかどうか、貸主の承認が必要かを確認。貸主指定の場合は、見積もりの妥当性もチェックポイントです。 |
このように、退去前に必要な確認事項を整理しておくことで、原状回復に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して退去手続きを進めることができます。
原状回復工事をする際の疑問
オフィス退去に伴う原状回復工事では、初めての対応となる企業ほど「何をどう進めればいいのか」「どこまで対応すべきか」といった疑問が多く生じます。ここでは、よくある質問とそのポイントを整理し、トラブルを防ぐための実務的な視点から解説します。
Q1. 原状回復工事はどこまでやればいい?
A. 賃貸借契約書に記載された「原状回復義務の範囲」と「特約条項」によって異なります。
一般的には、借主が設置した内装・什器・設備の撤去と、壁紙・床材・天井などの修繕が対象です。ただし、経年劣化や通常損耗は借主負担外とされるケースもあるため、範囲を明確にすることが重要です。
Q2. スケルトン戻しは必ず必要?
A. 必要かどうかは賃貸借契約書の特約に明記されているかで判断されます。
「スケルトン状態での明け渡し」と記載されている場合は、内装・造作・設備をすべて撤去し、コンクリート躯体が露出した状態に戻すことが求められる可能性があります。
Q3. 見積もりの金額が妥当かどうか判断できない…。
A. 原状回復工事の見積もりは、項目ごとの単価や工事範囲が明記されているかが重要です。
「一式」表記や内訳が不明瞭な場合は、追加費用が発生するリスクがあります。複数業者から相見積もりを取得し、工事内容と金額の妥当性を比較検討することが推奨されます。
また、ビズキューブ・コンサルティングでは、指定業者がいても対応可能な「工事費削減コンサルティング(完全成果報酬型)」を提供しています。契約書の診断と見積もり精査を通じて、不要な工事費の削減をサポートいたします。原状回復費用に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ|原状回復は「早めの準備」と「正しい知識」がカギ
オフィス退去時における原状回復は、企業にとって重要なプロセスです。特に初めて退去・移転を経験する中小企業の経営者や総務担当者にとっては、「早めの準備」と「正しい知識」が、費用の無駄やトラブルを防ぐための鍵となります。
指定業者であっても、原状回復の費用は削減できる
原状回復工事の業者が貸主指定であっても、費用を抑える余地はあります。たとえば、工事内容の見直しや不要な作業の削減を業者と交渉することで、見積もり金額が下がるケースがあります。
また、通常損耗(経年劣化)に該当する箇所は借主負担ではないため、契約書や国土交通省のガイドラインをもとに、工事対象から除外できる可能性もあります。貸主指定業者であっても、見積もりの内訳を確認し、「なぜこの工事が必要なのか」「どこまでが借主負担なのか」を明確にすることで、不要な費用を防ぐことができます。
ビズキューブ・コンサルティングでは、指定業者がいても対応できる、移転や退去時に発生する工事費を削減する成果報酬型サービス「工事費削減コンサルティング」を提供しています。
累計50,000件以上の賃貸借契約書を解読してきた実績豊富なコンサルタントが、契約書内に明示された適切な工事項目を割り出します。また実績40年の工事会社として、貴社の原状回復費用は適切な単価なのか否かを診断します。原状回復費用の減額交渉においても、専任コンサルタントによるサポート対応が充実しております。
原状回復費用に不安がある方は、是非お気軽にご相談ください。
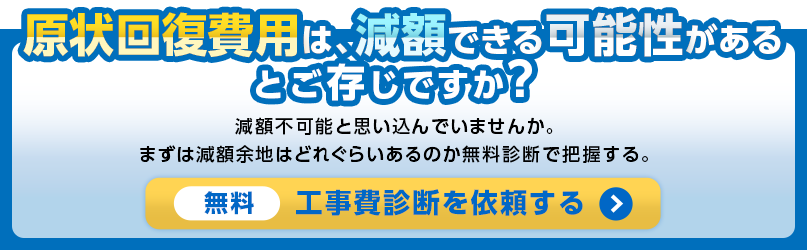
実は原状回復費用だけでなく「別拠点のオフィス賃料」も見直しできる
原状回復費用は、退去時に一度だけ発生するスポット費用(変動費)ですが、テナント経営において継続的にかかる固定費の代表格が「賃料」です。
「長年同じ条件で借りている」「周辺相場と比べて高い気がする」といった場合に、賃料の見直しによって、毎月のコストを継続的に削減できる可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングでは、賃料の適正価格を診断したうえで、減額のご要望がございましたら、「賃料削減コンサルティング」サポートを提供しております。
これまでに多数の企業が、平均16.2%の賃料削減を実現しております。初期費用不要の成果報酬型なので、削減できた分からのご請求となります。
「退去はまだ先だけど、今の賃料が気になる」「他テナントの賃料を見直したい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。賃料が適正価格か否かの診断だけでも無料で対応可能できます。
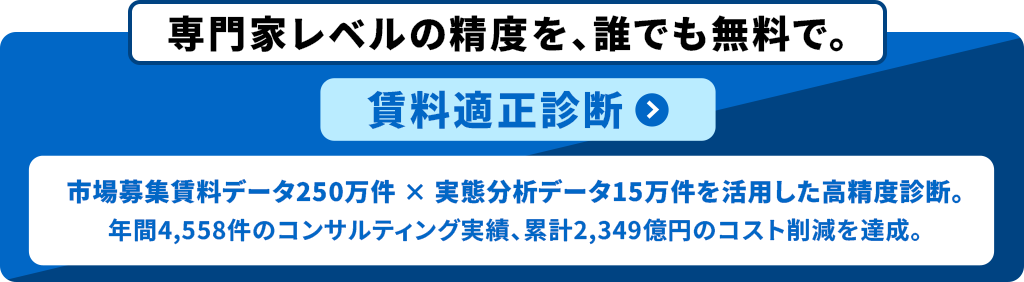
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。










 人気記事ランキング
人気記事ランキング

