年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する店舗経営
多店舗展開で失敗しないために|成功企業が実践するDX・組織・立地戦略

- 目次
多店舗展開とは?なぜ今注目されているのか
多店舗展開とは、同一ブランドや業態を複数拠点で運営し、効率的な経営と市場拡大を図るビジネスモデルです。飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスで広く採用されており、「チェーン展開」の一形態といえます。目的は単なる売上拡大ではなく、地域ごとの顧客ニーズに合わせて店舗運営を最適化し、全体としての収益性を高めることにあります。
多店舗展開が注目される理由
デジタル技術(DX:デジタルトランスフォーメーション)の進展が、多店舗展開を強力に後押ししています。本部と店舗間でリアルタイムに情報共有が可能となり、次のような経営改善が進むようになりました。
- 売上・在庫・顧客データを活用した意思決定が可能
- 店舗ごとのオペレーション状況を可視化できる
- 複数店舗を低リスクかつ高効率で運営できる
また、消費者の購買行動がオンラインとオフラインを横断するようになり、ブランド体験の一貫性が競争優位の鍵となっています。
店舗展開と多店舗経営の違い
「店舗展開」と「多店舗経営」は似ていますが、意味する段階と目的が異なります。
以下の表にまとめると違いが明確です。
| 項目 | 店舗展開 | 多店舗経営 |
| 段階 | 拡大フェーズ(成長期) | 経営フェーズ(成熟期) |
| 目的 | 出店による売上・市場拡大 | 全体最適化と収益性向上 |
| 主な課題 | 立地戦略、初期投資、開業スピード | 組織体制、人材育成、運営の標準化 |
| 経営の中心 | 出店戦略 | 運営マネジメント |
| 求められる視点 | 拡大のための戦略思考 | 継続的な経営体制の構築 |
この違いを理解することで、経営判断を誤らず、自社の成長段階に合わせた戦略設計が可能になります。
多店舗展開が注目される背景
多店舗展開が再び注目を集めている背景には、市場構造と消費行動の変化があります。
背景1:市場環境の変化
- 単一店舗での成長が難しくなり、「スケール経営(規模の経済)」が重視されている
- 仕入れコストの高騰や人材不足により、本部主導の一元管理が求められている
背景2:リスク分散と地域展開
- 複数拠点を持つことで、特定立地・客層への依存を軽減
- 地方・郊外市場への展開により売上の安定を実現
背景3:ブランド価値の向上
- SNSや口コミによる認知拡大で「店舗数=信頼性」として機能
- 統一されたブランド体験が顧客ロイヤルティを高める
このように、多店舗展開は単なる拠点数の拡大ではなく、経営資源を最適に配分するための「仕組みづくり」として注目されています。
次章では、この多店舗展開がもたらす具体的なメリットとリスクを整理します。
多店舗展開のメリットとデメリットを正しく理解する
多店舗展開は、成長戦略として大きな可能性を持つ一方で、リスク管理を誤ると経営全体のバランスを崩す危険もあります。特に飲食・小売などの店舗型ビジネスでは、スピードを優先した拡大の結果、オペレーションの不統一や人材不足に陥るケースが少なくありません。
成功の鍵は、「メリットとデメリットを正しく理解し、計画的に拡大すること」です。ここでは、多店舗展開がもたらす主な利点と課題を整理します。
多店舗展開の主なメリット
多店舗展開の利点は、以下の3点に大別されます。
| メリット | 内容 | 経営への効果 |
| 売上・利益の安定化 | 地域や業態ごとの売上変動を平準化し、特定店舗の不振リスクを軽減できる。 | 経営の安定化・中長期的なリスク分散 |
| ブランド力の向上 | 同一のサービス体験を複数拠点で提供し、顧客の信頼と認知度を高める。 | 集客力・採用力の強化、新規出店交渉の優位性 |
| スケールメリットの獲得 | 仕入れ・広告・システム費用を本部で集約することでコスト効率を高める。 | 利益率の向上・業務効率化 |
さらに、デジタル技術(DX)の進展により、複数店舗を統合的に運営する環境が整いつつあります。
これらの要素を組み合わせることで、単なる店舗数の拡大ではなく、経営基盤の強化につなげることができます。
よくあるデメリットと失敗パターン
一方で、多店舗展開には以下のような課題も存在します。
| デメリット | 具体的なリスク | 主な原因 |
| 管理コストの増大 | 店舗数増加により、情報共有や意思決定のスピードが低下。 | 本部と現場の連携不足、システム整備の遅れ |
| 人材確保・育成の難航 | 拡大スピードに人材育成が追いつかず、サービス品質が低下。 | 教育体制の未整備、属人的な管理 |
| 投資回収の遅れ・成長疲労 | 拡大による固定費増大や店舗間競合で利益圧迫。 | 市場調査不足、拡大優先の経営判断 |
とくに多い失敗パターンは、「店舗を増やせば成功する」という誤解です。
十分なシミュレーションやデータ分析を行わないまま拡大を急ぐと、固定費負担の増大やブランド毀損につながるリスクがあります。
失敗例から学ぶ「拡大の落とし穴」
実際の失敗事例に共通する要因は、次の2つです。
1. 現場の“見えない化”
本部が現場の実情を把握できず、店舗ごとにオペレーションが分断される。
結果としてサービス品質がばらつき、ブランド価値が低下する。
2. 管理の属人化
店舗ごとに異なる方法で売上・在庫管理を行い、経営判断が遅れる。
撤退や再投資の判断が後手に回り、損失が拡大する。
これらは、拡大初期に特に起こりやすい典型的な“落とし穴”です。
回避のポイント
- 出店スピードよりも経営基盤の整備を優先する。
- 本部主導のオペレーション標準化を行い、属人化を防ぐ。
- DXによる情報の一元化を進め、データに基づく経営判断を徹底する。
多店舗展開は、拡大そのものが目的ではありません。
「持続可能な経営体制を構築するプロセス」と捉えることで、長期的な成長へとつなげられます。
次章では、この「成功する多店舗展開」を実現するための戦略を、3つの観点から整理します。
多店舗展開を成功させる3つの戦略
多店舗展開を持続的に成長させるためには、「店舗数を増やすこと」よりも「成長を支える仕組みを整えること」が欠かせません。
成功企業の多くは、拡大フェーズに入る前に以下の3つの軸を確立しています。
| 戦略の軸 | 目的 | 代表的な取り組み |
| 組織体制の整備 | 本部と現場の役割を明確化し、指揮系統と情報の流れを整える | 戦略立案・データ分析・人材育成・品質管理など本部機能の強化 |
| 標準化とDX | サービス品質のばらつきを防ぎ、業務を仕組み化する | マニュアル整備、教育のデジタル化、クラウド管理・AI分析 |
| 立地・事業戦略 | 店舗拡大の「数」より「質」を重視し、事業の持続性を高める | 商圏分析、直営・FCの併用、オムニチャネル展開 |
これら3つはいずれも相互に関連しており、どれか1つが欠けると経営全体のバランスを崩す危険があります。
以下でそれぞれの戦略を詳しく見ていきましょう。
① 組織体制の整備 ― 本部機能と現場の連携強化
多店舗経営の基盤は、「本部機能の確立」にあります。
店舗数が増えるほど、本部と現場の役割を明確にしなければ、意思決定の遅れや情報の断絶が起こります。
本部が担うべき主な機能と具体例
| 機能 | 内容 | 実例 |
| 戦略立案とKPI設計 | 売上やコスト構造を定量的に管理し、全店の方向性を統一 | 月次で売上・客単価・人件費率を分析し、現場と共有する仕組み |
| データ分析と意思決定支援 | 現場の状況を可視化して迅速な判断を支援 | POSデータを活用し、繁忙期の人員配置を最適化 |
| 人材育成・評価制度 | 店長候補を計画的に育て、離職を防止 | ステップ評価制度や動画研修プログラムを導入 |
| 品質管理とオペレーション改善 | サービス水準の均一化と改善の継続 | 覆面調査の結果を共有し、全店で改善策を検討 |
また、単に「指示を出す」だけではなく、現場の声を経営判断に反映する仕組みが重要です。
デジタルツールを使った情報共有や、定例ミーティングでの双方向コミュニケーションにより、全社で共通のKPIを追う文化をつくることが、多店舗経営成功の第一歩です。
② 標準化とDX ― オペレーションを仕組み化する
店舗ごとにサービス品質や業務手順が異なると、ブランド価値の一貫性が失われます。
そのため、オペレーションの標準化とDX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化が不可欠です。
標準化とDXの具体策と活用例
| 施策 | 内容 | 活用例 |
| 業務マニュアルの整備 | 調理・接客・衛生・発注などを明文化し、誰でも再現可能に | 飲食業では「30秒以内に声かけ」など接客指針を共有 |
| 教育体制のデジタル化 | Eラーニングや動画教材で教育を標準化 | 新人研修をスマホアプリで提供し、OJT依存を軽減 |
| データの一元管理 | POS・在庫・勤怠情報をクラウドで統合 | 在庫過多を検知し、自動で発注調整を行うシステムを導入 |
| AI・BIツール活用 | 売上データを分析し、最適な人員配置や仕入れ量を算出 | 小売業ではAIによる需要予測を導入し、在庫の過不足を抑えるなど、効率的な店舗運営を実現する動きが広がっている |
こうした仕組みは導入コストこそ発生しますが、属人化の排除や業務の見える化、利益率の改善に直結します。
DXは、作業を効率化するためだけのIT投資ではなく、全店舗の経営判断を支える「情報基盤」への投資として位置づけることが重要です。
③ 立地・事業戦略 ― 数より質の拡大を意識する
多店舗展開で失敗が多いのは、「店舗数=成長」と短絡的に考えるケースです。
成功している企業は、立地・事業ポートフォリオ・顧客接点を戦略的に設計しています。
効果的な出店・事業戦略と実例
| 戦略項目 | 内容 | 実例 |
| 商圏データ分析 | 人口動態・競合状況・交通動線をもとに出店判断 | 郊外SC内に集客導線を意識して出店し、週末来店率を2割増 |
| 直営とFCの併用 | 投資リスクを分散し、スピードと品質を両立 | 本部主導のFC制度を構築し、管理コストを抑えながら拡大 |
| オムニチャネル展開 | オンラインとオフラインを融合した顧客接点の最適化 | EC購入者を店舗イベントへ誘導し、再来店率を向上 |
単なる出店数ではなく、「顧客との接点をどうデザインするか」「ブランド体験をどう統一するか」という事業戦略の設計力が成長の分かれ道になります。
データで読み解く出店戦略
出店判断を誤ると、その後の努力では取り返しがつかないこともあります。
多店舗展開において「どこに出すか」は、経営の成否を分ける最重要ポイントです。
近年では、商圏データ・人流情報・競合状況などを活用し、データに基づく出店戦略を立てる企業が増えています。感覚や経験だけに頼らず、数値と根拠をもとに立地を判断することが成功の鍵です。
ビズキューブ・コンサルティング株式会社では、データ分析と不動産ネットワークの両面から、出店判断の精度を高める店舗開発支援サービスを提供しています。
- 物件情報の収集:長年培った不動産業者・ビルオーナー・デベロッパーとのネットワークを通じ、クライアント企業の出店条件に合った物件情報を迅速に収集・提案
- 商圏分析と立地シミュレーション:人流データや競合環境を掛け合わせ、最適な出店候補地を可視化
- 収益性予測の支援:賃料・売上・損益分岐点を算出し、投資判断を数値的にサポート
- 多拠点配置設計:既存店舗との商圏重複(カニバリ)を回避し、全体収益を最大化する配置戦略を立案
こうした支援を通じて、「この立地で本当にいいのか?」という不安をデータと専門知見の両面から解消できます。
感覚ではなく根拠に基づいた出店判断こそが、持続可能な多店舗展開を支える基盤です。
➡サービス内容や具体的な事例の詳細をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。
多店舗展開の課題をどう解決する?現場で起きている問題
多店舗展開を進めると、理論上の戦略だけでは解決できない「現場発」の課題が次々と浮かび上がります。
特に店舗数が5店舗を超えたあたりから、情報共有・人材育成・コスト管理がボトルネックになりやすく、経営スピードを鈍化させます。
以下は、多店舗経営で頻発する主要な課題とその解決方向の整理です。
多店舗展開における主な課題と解決方向
| 課題 | 背景 | 解決の方向性 |
| 情報共有不足 | 複数ツールの併用や本部指示の分散により、最新情報が伝わらない | 共有ツールの一元化・承認フローの自動化・データのリアルタイム可視化 |
| 人材育成・採用難 | 店舗拡大に教育が追いつかず、リーダー層が不足 | 教育のデジタル化・評価制度の明確化・採用ブランディング強化 |
| 運営コストの増加 | 店舗単位での発注・運営が非効率でスケールメリットを活かせない | 購買集約・業務自動化・管理会計導入による収益可視化 |
よくある課題①:本部と店舗間の情報共有不足
多店舗展開で最も多いのが、本部と現場の情報断絶です。
営業報告やキャンペーン情報が正確に共有されないことで、現場判断にズレが生じ、店舗間でサービス品質の差が生まれます。
改善ポイント:
- 情報共有ツールを一元化し、全店舗がリアルタイムに同じデータを参照できる環境を整える。
- 承認フローや日報をDX化し、報告・承認業務を自動化。
- KPIを可視化するダッシュボードを導入し、経営判断のスピードを高める。
例:クラウド型の店舗管理システムを導入し報告作業を自動化した企業では、情報更新のタイムラグを半減。

よくある課題②:人材育成・採用難
店舗数が増えるほど、人材育成のスピードと質の両立が難しくなります。
店長候補が育たない、教育が属人化している、採用競争が激しい―こうした状況は多店舗経営では共通です。
改善ポイント:
- オンライン研修・動画教材で教育を標準化し、OJT依存を軽減。
- キャリアステップや評価基準を明確化し、成長実感を持てる環境を構築。
- 企業理念や教育体制を発信し、“働きたいと思われるブランド”を形成。
例:オンライン研修を導入した結果、離職率が減少し、管理職候補の育成スピードが向上。
よくある課題③:運営コストの増加
多店舗化により固定費や物流費が増加し、規模拡大が利益圧迫要因になるケースも珍しくありません。
改善ポイント:
- 購買業務を本部集約し、仕入れコストを最適化。
- 在庫データを可視化し、発注重複や廃棄ロスを防止。
- 管理会計を導入し、店舗別の損益を把握して意思決定を迅速化。
例:購買業務を本部集約した結果、仕入れコストを約10%削減し、在庫回転率を改善。
これらの課題は、組織の成長とともに必ず直面するものです。
しかし、仕組み化・標準化・可視化の3点を意識すれば、現場負荷を抑えながら継続的な拡大を実現できます。
次章では、こうした構造的課題を根本から解決するために、外部の専門家によるコンサルティング活用について解説します。
課題解決の鍵 ― 専門家支援で“拡大に強い仕組み”をつくる
多店舗展開を成功させるには、出店スピードを高める「攻め」と、コスト構造を整える「守り」の両輪が欠かせません。
特に、物件選定・施工・賃料など店舗運営に直結する領域は、外部の専門家と連携することで大きく成果が変わります。
ここでは、拡大フェーズで成果を上げるための店舗開発・賃料最適化の考え方を紹介します。
出店を成功に導く「立地戦略と店舗開発支援」
多店舗展開の要は「立地」と「スピード」です。
出店候補地の収集から開発・改装までを効率化することで、拡大のチャンスを逃さず動けます。
ビズキューブ・コンサルティングでは、不動産業者・ビルオーナー・デベロッパーなどとの強固なネットワークを活かし、条件に合った物件情報をスピーディに提案。さらに出店から改装・リニューアルまでを一元的に支援し、店舗の品質とコストを両立します。
主な支援内容
- 物件情報の収集・提案(立地条件や商圏データに基づく分析)
- 出店・改装・原状回復を含む店舗開発の一元支援
- 管理会社やオーナーとの交渉代行による出店スピード維持
- 新業態開発やブランドリニューアルを見据えた空間企画
既存店舗の賃料を見直し、“固定費体質”を改善する
多店舗展開を進める企業にとって、店舗数が増えるほど影響が大きくなるのが賃料コストです。経済情勢や近隣相場が変化するなかで、契約当初に設定した賃料が今も妥当とは限りません。
そのため、定期的に「現在の賃料が市場水準に対して適正か」を確認することが、経営の健全化につながります。近年では、データに基づく賃料適正診断を行い、改善余地を客観的に把握する企業が増えています。
ビズキューブ・コンサルティングが提供する「賃料適正診断」は、約3分で現在の賃料水準を確認できるサービスで、年間約5,000件以上のご利用実績があります(自社集計データに基づく)。
無料で、現在の賃料が相場と比べて適正かどうかを確認できますので、まずは診断から状況を把握していただくことをおすすめします。
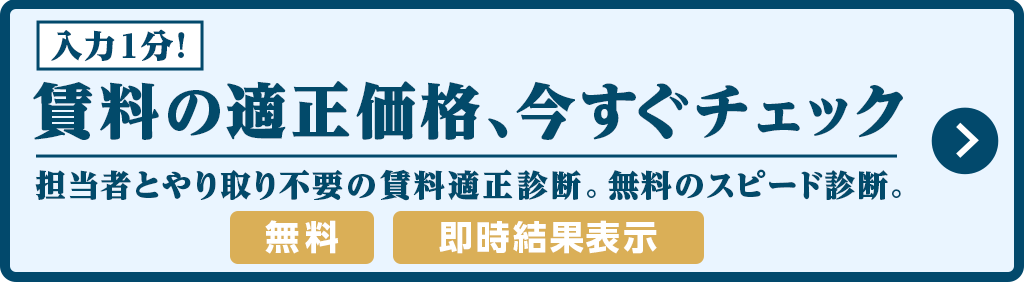
成長を支える専門家ネットワーク
このように、ビズキューブ・コンサルティングでは「出店」と「既存店最適化」の両面から、多店舗展開を支える仕組みづくりを伴走支援しています。
| 領域 | 内容 | 効果 |
| 店舗開発支援 | 物件情報の収集・出店支援・施工管理 | 出店スピード向上・品質安定化 |
| 賃料適正化コンサルティング | 市場分析・オーナー交渉・条件見直し | 固定費削減・収益改善 |
| 改装・リニューアル支援 | レイアウト設計・コスト最適化 | ブランド価値向上・長期利用最適化 |
多店舗展開の課題は、「拡大する力」と「支える仕組み」の両立にあります。出店や改装のスピードを高める一方で、既存店舗のコスト構造を見直すことが、持続的な成長の鍵です。
成功パターンに学ぶ ― 多店舗展開の成長モデル
多店舗展開の成功モデルは、業種や事業ステージによって異なります。
飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスにはそれぞれ独自の課題がありますが、共通しているのは「仕組みで成長を支えること」と「顧客体験の一貫性を保つこと」です。
ここでは、業種ごとに見られる成功パターンと、スモールスタートで成長した企業に共通する傾向を整理します。
業種別に見る成功パターン(飲食・美容・小売)
飲食業界 ― 標準化と地域適応のバランスが鍵
飲食業界では、調理工程や接客マニュアルなどを標準化しながらも、地域の嗜好や立地特性に応じてメニューや店舗デザインを調整する企業が成果を上げています。
こうした「統一と柔軟性の両立」が、ブランドの信頼性を保ちながら地域顧客の支持を得るポイントです。
加えて、原材料の一括仕入れやモバイルオーダーなど、DXによる効率化の取り組みも広がっています。
美容業界 ― 教育体制とキャリア設計がブランドを強くする
美容業界では、スタッフ教育とキャリア形成が成長の基盤です。
教育プログラムを体系化し、オンライン研修を導入することで技術レベルのばらつきを防ぎ、全国的に一定品質を維持する企業が増えています。
また、キャリアアップを支援する制度を整え、人材定着とサービス品質の向上を両立させようとする企業も増えています。
小売業界 ― データドリブン経営による効率的な展開
小売業界では、POSデータや顧客購買データを活用して商圏を分析し、立地重複を防ぐデータドリブン出店戦略が主流です。
さらに、オンラインストアと実店舗を連携させるオムニチャネル戦略を展開することで、顧客接点を拡大し、販売機会を最大化しています。
いずれの業種にも共通するのは、現場任せにせず仕組みで品質を保ち、顧客体験を一貫させることです。
スモールスタートで成長を実現した企業に共通する傾向
近年の多店舗展開では、いきなり規模を拡大するのではなく、まず1店舗で成功モデルを確立し、その仕組みを横展開する“スモールスタート型”が有効なアプローチの一つとされています。
多くの成長企業に共通して見られるのは、「再現性のある強み」を初期段階で明確化している点です。
例えば、1号店で顧客導線・商品構成・教育体制を検証し、得られた成果を仕組みとして定義化したうえで、2号店以降に展開する流れです。
また、予約管理や勤怠・在庫を一体化したシステムを導入し、業務効率を高めて出店スピードを安定化させる企業も増えています。
このようなスモールスタート型の利点は、リスクを抑えながら「成功モデルの確立 → 標準化 → 横展開」というプロセスを確実に進められることです。
短期的な拡大よりも、持続的に利益を生み出せる仕組みを整えることが、本当の意味での成長といえます。
ビズキューブ・コンサルティングが支援する成長モデル構築
ビズキューブ・コンサルティングでは、多店舗展開を目指す企業に対し、戦略立案・出店計画・コスト構造の見直しなどを通じて、再現性のある成長モデルの構築を支援しています。
特に、出店戦略の策定や物件情報の収集、賃料適正診断など、店舗開発&管理に直結する領域を強みとしています。
経営層が意思決定に集中できるよう、現場と本部をつなぐ仕組みの整備をサポートし、拡大に強い経営基盤を整えます。
多店舗展開の本当の成功とは、店舗を増やすことではなく、「どの店舗でも同じ成果を再現できる仕組み」を持つことです。ビズキューブ・コンサルティングは、その成長の仕組みづくりを企業と共に設計します。
➡今後の多店舗展開の進め方について、無料でご相談いただける窓口もご用意しています。
まとめ ― 失敗しない多店舗展開のために
多店舗展開の成功は、単に店舗数を増やすことではありません。
本質は、「経営の再現性を高める仕組みを構築できるかどうか」にあります。
出店スピードだけを優先してしまうと、一時的な売上増の裏側で現場の疲弊やブランド力の低下を招く恐れがあります。一方で、戦略・仕組み・人の3要素が整えば、安定した成長と収益性の両立が可能になります。
ここであらためて、失敗しない多店舗展開のポイントを整理します。
戦略・仕組み・人 ― 成功を支える3つの要素
多店舗経営を軌道に乗せるには、この3つの要素をバランスよく整えることが不可欠です。
| 要素 | 重点ポイント | 効果 |
| 戦略 | 市場データや商圏分析をもとに、出店エリア・提供価値を明確化。数より質を重視した展開を行う。 | 出店計画の精度向上とブランド価値の維持 |
| 仕組み | オペレーション標準化やDX活用で、判断スピードと再現性を高める。属人化を防ぎ、どの店舗でも同品質を実現。 | 経営効率とサービス品質の安定化 |
| 人 | 教育体制・キャリア設計を整え、スタッフが誇りを持てる環境を構築。 | 現場力の強化と定着率の向上 |
この3要素を段階的に整えることで、企業全体が「拡大しても崩れない経営体制」へと進化していきます。
ビズキューブ・コンサルティングが支援できること
ビズキューブ・コンサルティング株式会社は、 多店舗展開を行う企業の「コスト構造適正化」と「店舗物件管理・開発支援」 に特化した支援を提供しています。
具体的な支援内容として、以下のサービスがあります。
| 支援領域 | 説明 |
| 賃料適正化コンサルティング/賃料適正診断 | 支払われている賃料が相場に対して適正かどうかを無料診断し、必要に応じて賃料の見直し支援を実施します。 |
| 設計・デザイン施工(内装工事・原状回復工事等) | 新規出店・改装・退去に伴う内装・原状回復工事をワンストップでサポートします。 |
| 店舗開発支援/物件管理・契約管理サービス | 出店候補物件のご提案や契約管理、テナント管理のアウトソーシングなど、物件・出店プロセスを包括的に支援します。 |
これらを組み合わせることで、企業は「何を優先して改善すべきか」「どの物件・契約がコスト構造を圧迫しているか」といった課題を可視化できます。
ビズキューブは、理論と実務をつなぐパートナーとして、データと実績に基づく改善プロセスをともに設計します。
多店舗展開のゴールは、店舗数を増やすことそのものではありません。
「増やしたすべての店舗が、継続的に利益を生み出し続ける状態」をつくることが、本当の意味での成功です。
ビズキューブ・コンサルティングは、その実現に向けた選択肢のひとつとして、コスト構造と店舗開発の両面から企業の成長をサポートします。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。










 人気記事ランキング
人気記事ランキング

