年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する店舗経営
ドミナント戦略とは?成功の秘訣と事例を解説

店舗ビジネスにおいて利益や売上を増加させるには、多店舗展開する方法があります。
そして、多店舗展開を実現するひとつの手法として、小売店や飲食店で採用されているのが「ドミナント戦略」です。
本記事では、ドミナント戦略のメリットやデメリット、成功事例、実践のポイントについて解説し、皆様の経営戦略の参考にしていただくことを目的としています。
特定地域での自社のシェア率向上や、フランチャイズ展開をご検討の場合は、ぜひ参考にしてください。
ドミナント戦略の基礎知識
ここでは、ドミナント戦略の定義などの基本的な知識や、混同されることが多いランチェスター戦略との違いをご紹介します。
限られた経営資源で効率良く店舗展開を行うためには、小売業を中心に採用されている、ドミナント戦略への理解を深めましょう。
ドミナント戦略とは?
ドミナント戦略とは、特定地域へ集中的に出店する戦略のこと。
英語の「dominant」は、「支配的な」「もっとも有力な」という意味の言葉です。
集中出店などにより、もっとも高いシェア率を獲得しているエリアは、「ドミナントエリア」と呼ばれます。
ドミナント戦略は、チェーンストアやフランチャイズ方式の小売店、飲食店で採用されることが多いのが特徴です。
コンビニエンスストアやスーパーマーケット、カフェなど顧客の来店頻度が高い業態に向いているとされます。
ドミナント戦略とランチェスター戦略の違い
ランチェスター戦略は、中小企業が市場で優位に立つための戦略で、特定の分野やターゲットに集中することが特徴です。
例えば、特定のジャンルの品揃えを充実させる、特定のユーザー層へ向けた商品で人気を得るなどの方法が考えられます。
一方、ドミナント戦略はランチェスター戦略の「集中」戦略を地域に特化させたものです。
両戦略の大きな違いは、ドミナント戦略が特定エリアでのシェア獲得を目指すのに対し、ランチェスター戦略は特定分野でのシェア獲得を目指す点にあります。
ドミナント戦略のメリット
店舗間の距離が近いコンビニチェーン店などを見かけると、「もう少し離したほうが効率良く顧客を獲得できるのでは?」と思うこともあるのではないでしょうか。店舗管理や成長戦略にドミナント戦略を取り入れると、ライバル企業との競争にどのような利点をもたらすのでしょうか。
- 配送業務を効率化できる
- 出店地域内での認知度アップが期待できる
- エリアマーケティングの最適化につながる
- 地域性に合わせて広告を変更しやすい
- 競合他社の参入抑制につながる
- スーパーバイザーが巡回しやすい
配送業務を効率化できる
ドミナント戦略では、出店している店舗ごとの距離が近いため、配送効率が高まりやすいのが特徴です。
配送センターと店舗を効率的なルートで巡回できます。商品を迅速に配送できることで、鮮度の高い商品を購入できるなど、顧客の利便性向上につながります。また、配送の効率化により、1店舗あたりの物流コスト削減が期待できるのもメリットです。
出店地域内での認知度アップが期待できる
ドミナント戦略によって商圏内の消費者に対する単純接触効果が高まるため、地域内で自社ブランドの知名度がアップし、売上向上の効果が期待できます。
単純接触効果とは、接触した回数が多くなるほど、好感度が高まる現象のことです。ドミナントエリアでは、住民が店舗や看板、広告などを見かける機会が多くなるため、無意識に対象への好感度が高まる傾向にあります。
エリアマーケティングの最適化につながる
エリアマーケティングとは、ターゲットとなる地域の消費者の年齢層や趣向、ライフスタイル、地理的な事情などの地域特性を踏まえた宣伝活動を行うことを指します。
ドミナント戦略では、特定地域に絞って市場調査を行うため、地域特性を深く理解しやすいのが特徴です。
その結果、エリアマーケティングの最適化につながり、効果的な宣伝や出店場所の選択、需要にマッチした商品の販売などが可能になります。
地域性に合わせて広告を変更しやすい
ドミナント戦略によって出店状況が特定の地域に集中していると、地域性に合わせて広告をカスタマイズしやすくなります。
店舗ごとに広告を変更するのは、コストや効率の面で負担となりますが、ドミナント出店では手間や費用を抑えて宣伝活動が可能です。
競合他社の参入抑制につながる
ドミナント戦略によって特定地域の市場を独占できれば、競合他社の参入抑制が期待できます。
その地域では、「スーパーといえば○○」「コンビニといえば○○」といったブランドイメージが定着しており、他社が参入しても利益を生みづらい環境になっているためです。
また、市場の独占によって他社との競争にリソースを割く必要性が減少し、商品の品質向上や作業の効率化に投資しやすくなるのもメリットです。その結果、地域市場における自社の優位性をさらに高めることができ、利益の最大化や経営の安定化につながりやすくなります。
スーパーバイザーが巡回しやすい
ドミナント戦略では店舗が特定のエリアに集中しているため、スーパーバイザーが短時間で巡回できるのも魅力です。
1店舗あたりの指導時間を長く確保することも容易になり、サービスの質向上にも役立ちます。
ドミナント戦略のデメリット
ドミナント戦略の成功事例として挙げられる企業の多くが、デメリットにも配慮した経営を行っています。
ドミナント戦略を実践する際は、以下の注意点・問題点を理解しておきましょう。
- 自然災害のダメージが大きい
- 出店地域の状況変化の影響を受けやすい
- 新規エリアに出店しにくい
- カニバリゼーションが起こるおそれがある
- マイナスイメージの波及
- 新規エリアでのノウハウ不足
- 店舗拡大による人材不足
自然災害のダメージが大きい
ドミナント戦略は、出店地域で自然災害や大規模な事故が発生した場合、甚大な被害を受けるおそれがあります。店舗が特定のエリアに集中していることから、周辺地域で各店舗が同時に被害を受けやすいためです。
異なるエリアに出店していく戦略の場合、災害によるリスクを分散しやすくなります。
日本は地震や台風、豪雨、豪雪、河川の氾濫、津波、火山噴火などの自然災害が多い国といわれるため、リスクに備えた対策が必要です。
出店地域の状況変化の影響を受けやすい
自然災害のリスクと同様、ドミナント戦略では特定地域に店舗が集まっているため、経営が地域事情の変化に影響を受ける可能性があります。具体的には、少子高齢化による人口減少、交通アクセス環境の変化、ライバル店の出店、地域産業の衰退などが考えられます。自社でコントロール不可能な事情で需要が変わり、売上が低迷するおそれがあるのです。
そのため、ドミナント戦略の出店エリアは、地域の将来性も考慮した上で、慎重に検討することが重要になります。
新規エリアに出店しにくい
ドミナント戦略を実践する際は、特定地域に絞ってマーケティングやプロモーションを行うのが基本です。
そのため、新規エリアへの出店を検討する際に情報が不足する傾向にあり、他社に後れを取りやすくなります。
広範なエリアに出店している企業は、多くの地域の情報を集められるため、新規エリアへの出店も比較的容易です。
また、ドミナント戦略を中心に経営している場合、コスト面でも出店地域の拡大が難しくなるおそれがあります。
新規エリアでは既存の配送方法や店舗管理の手法を維持できないケースも多く、新たなシステムの構築やオペレーションの確立が必要となるためです。ドミナント戦略から他地域への出店拡大を検討する際は、緻密な資金計画を立て、採算面を確保した上で実行に移すことが大切です。
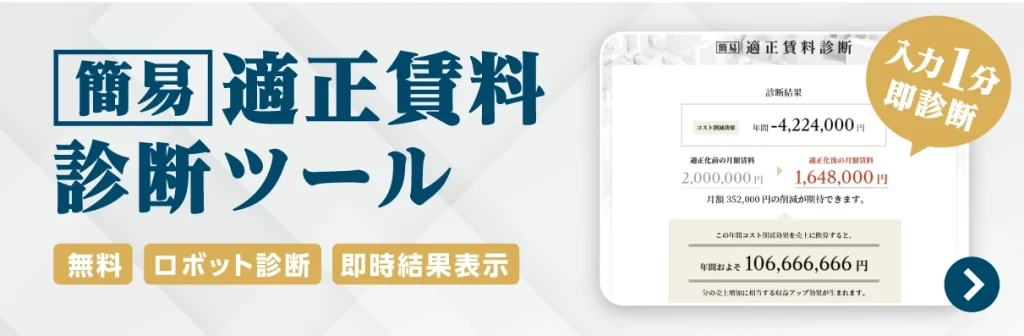
カニバリゼーションが起こるおそれがある
カニバリゼーションとは、同一企業内における顧客の奪い合いを意味するマーケティング用語です。
ドミナント戦略によって地域の店舗数が過剰になると、店舗同士で顧客を奪い合うことになり、売上が低下するおそれもあります。特に、フランチャイズ展開している場合は、店舗ごとに採算を取っているため、売上の低下は避けたいところです。
ドミナント戦略を実践する際は、地域特性を踏まえて適切な店舗数や店舗間の距離を見極める必要があります。
マイナスイメージの波及
同一地域の店舗展開は、ブランドイメージを共有するため、一店舗の問題が顧客のブランド全体への不信感に繋がり、近隣店舗にも負のイメージが波及するリスクがあります。
新規エリアでのノウハウ不足
特定地域での成功体験は、異なる地域特性を持つ市場では通用しない可能性があります。地域に合わせた戦略の見直しやノウハウの蓄積が必須となります。
店舗拡大による人材不足
店舗網の拡大は、人材需要の増加に直結します。質の高いサービス維持には、採用強化と人材育成プログラムの構築、そして増加する人件費への対策が不可欠です。
ドミナント戦略を成功へ導くポイント
経営リソースの少ない弱者が強者に勝つためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、ドミナント戦略を成功させるためのポイントや考え方を解説します。
出店予定の地域を詳細に調査しておく
ドミナント戦略を成功させるには、エリア内で十分な利益が見込めるかを見極める必要があります。
具体的には、地域情勢や人口の推移、ユーザーニーズ、需要特性、競合他社の参入状況などを確認しましょう。
提供する商品やサービスが地域の風土や住民のニーズに合っていないと、売上を伸ばすことはできません。
自然災害に備えてBCP(事業継続計画)に取り組む
ドミナント戦略による自然災害リスクは、BCPを策定して備えるのがおすすめです。
BCPとは「Business Continuity Planning」の略語で、災害や緊急時における企業の事業継続計画を意味します。
BCPに取り組むことで、災害発生時の行動が明確になり、ブランドイメージの低下や他社への取引の流出などの防止が可能です。
BCPの策定方法や内容については、「東京都防災ホームページ」や内閣府の「事業継続ガイドライン」で公開されています。
また、BCP策定後は定期的に見直しを行い、災害発生時に機能するようアップデートする必要があります。
【参考】
「BCP(事業継続計画)」(東京都防災ホームページ)
「事業継続ガイドライン(令和3年4月)」(内閣府)
競合他社の出店計画との差別化をはかる
ドミナント戦略を進める際は、競合他社が出店していない地域や、市場での優位性を確保していない地域を探す必要があります。すでに特定の企業が根付いている地域に出店しても、シェアを伸ばすのは難しく、コストや時間が無駄になるおそれがあるためです。
データ分析に基づく意思決定
ドミナント戦略を成功させるには、データ分析を活用した意思決定が重要です。POSシステムや顧客管理システムを導入し、購買履歴や来店頻度などのデータを収集・分析することで、視点層に最適な商品開発やサービスが提供される可能性があります。さらに、データをもとに価格戦略や販売促進策を立てることで、競争力のある市場展開ができます。 データドリブンな経営を取り入れることで、より効率的で確実な成長を実現できます。
フランチャイズ展開における注意点
フランチャイズによるドミナント戦略の展開には、オーナーの負担軽減と本部との連携強化が要注意です。 特に、未経験のオーナーが安心して運営できるよう、開業研修前の認定や開業後の継続的なサポートが求められます。本部とフランチャイズ加盟店の関係を強化するため、定期的な情報共有や経営相談の機会を設け、経営課題の早期解決を決意することが成功の鍵となります。 さらに、地域特性に合わせた運営方針の柔軟な調整も必要です。
ドミナント戦略の成功事例
ここでは、各業界の企業が実践するドミナント戦略の成功事例を紹介します。
【コンビニエンスストア】セブン-イレブン
セブン‐イレブンは、ドミナント戦略により、ブランドの認知度向上と物流の効率化を実現しました。その象徴的な事例が、1974年の第1号店開業後の「江東区から出るな」という方針です。特定地域への集中出店により、消費者の目に触れる機会を増やし、ブランド浸透を図るとともに、広告宣伝や店舗サポートの効率化を可能にしました。
また、この戦略を活かし、おにぎりや弁当などのオリジナル商品の専用工場を設置。販売時間帯に合わせた配送を行うことで、高品質で新鮮な商品提供を実現しました。現在、全国に165拠点の専用工場を持ち、商品開発力の強化につながっています。
さらに、高齢化やライフスタイルの変化に対応し、「セブンミール」などのサービス展開も進行中です。全国展開を急ぐ他社とは異なり、地域密着のドミナント戦略を貫くことで、店舗開発の精度を高め、地域の生活インフラとして成長し続けています。
参考:セブン&アイの挑戦(株式会社セブン&アイホールディングス)
【カフェ】スターバックスコーヒー
スターバックスは、都市部での集中出店により、ブランドの認知度を向上させています。東京都内には約400店舗あり、特に千代田区や港区などの都心部に多く展開しています。
<多く展開している地区>
千代田区49店舗
港区43店舗
渋谷区42店舗
新宿区34店舗
中央区25店舗
世田谷区21店舗
この戦略により、街中でスターバックスのロゴを頻繁に目にすることで広告効果を生み出し、ブランド認知を強化。さらに、混雑時でも近隣店舗を利用できるため、顧客満足度を維持しやすく、売上の安定にもつながっています。
参考:東京都の店舗一覧 |スターバックス コーヒー ジャパン
【ドラッグストア】ツルハグループ
ツルハグループは複数のブランド展開で地域のニーズに対応し、M&Aを通じて事業を拡大しました。地域ごとの特性に合わせた店舗運営が成功の鍵です。
参考:ツルハグループが選ばれる3つの理由(ツルハホールディングス)
【ホテル】アパホテル
アパグループは、全国最大の734ホテル・113,115室を展開する総合都市開発企業です。
中央区日本橋エリアを重点地域とし、ドミナント戦略を推進しており、現在東京都中央区内では建築・設計中を含め17棟・2,947室を展開しています。
好立地に集中出店し、店舗間のヘルプ体制でサービス品質を維持しています。ドミナント戦略により知名度とブランド力を高めました。
参考:アパグループ 中央区「小伝馬町駅」にホテル開発用地を取得(アパグループ)
【スーパーマーケット】ヤオコー
ヤオコーは都心近郊のドーナツ型エリアに集中出店し、地域特性に合わせた店舗づくりで成功しています。ネットスーパーの活用も強みです。
参考:ヤオコー/目標年商26億円「武蔵浦和店」オープンで浦和ドミナント強化(流通ニュース)
ドミナント戦略は綿密な市場調査が成功の鍵を握る
今回は、ドミナント戦略の概要やメリット・デメリット、成功の秘訣をご紹介しました。
ドミナント戦略は限られた経営資源でも特定地域のシェアを確保できるメリットがある一方、地域事情の変化に影響を受けやすいという弱点があります。そのため、市場調査を綿密に行い、商品と顧客のニーズ、他社の出店計画などをもとに、最適な出店場所を探すことが大切です。
ドミナント戦略においては、出店する特定地域の賃料相場を知り、店舗コストを下げることも非常に重要です。
ビズキューブ・コンサルティングの『賃料適正化コンサルティング』では、ご契約中の店舗(物件)における今の賃料が適正かどうか調べるだけでなく、プロのコンサルタントが貸主様との賃料協議もサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。
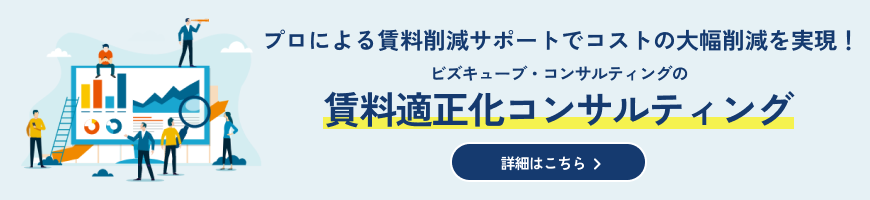
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。











 人気記事ランキング
人気記事ランキング

