年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
テナント賃料の決め方とは?相場・交渉・決定要因まで徹底解説

- 目次
テナント賃料の決め方を知っておくことで、借主は貸主との賃料交渉の成功率を高められる可能性があります。賃料交渉を検討している借主の中には、次のような悩みを持つ方もいるでしょう。
- 周辺相場より高い賃料で、経営コストが圧迫されている
- 交渉したいが、やり方や賃料相場がわからない
- 賃料交渉に必要な知識・情報が不足している
本記事では、テナント賃料の決め方、相場に影響を及ぼす要因や目安について、詳しく解説します。テナント賃料の決め方を理解し、円滑な賃料交渉に役立ててください。
借主がテナント賃料の決め方を知っておくと良い理由
テナント賃料とは、商業施設やオフィスなどのテナントとして使用される物件の賃料を指します。テナント賃料を決める方法を知っておくことは、借主にとっても賃料交渉をする上で重要です。例えば、次のような場合に交渉が必要になることがあります。
- 現在の賃料が周辺の相場に比べて高すぎる
- 物件の価値が下がっているのに、同じ賃料を払い続けている
- 賃料の値上げを要求されたが、根拠が不明瞭なので交渉したい
借主が賃料交渉を行う際には、具体的で客観的な理由を提示することで、より有利な条件を引き出す可能性が高まります。借主もテナント賃料の決め方や現在の妥当な相場を理解しておくと良いでしょう。
テナント賃料とは?賃料・家賃・テナント料の定義と違い
「テナント賃料」とは、商業施設・店舗・オフィスなど事業用物件に支払う賃料の総称です。混同しやすいのが「家賃」という言葉。住居における賃料は「家賃」と表現されることが多いですが、事業用不動産では「テナント料」「テナント賃料」として区別されます。テナント賃料の中には、次のような費用が含まれます。
- 賃料本体
- 共益費(管理費)
- 保証金・敷金・礼金
- 税金(消費税・固定資産税相当額など)
- 仲介手数料(賃貸借契約時)
つまり、「テナント料とは?」と問われた場合、単に坪単価だけでなく、上記すべてを考慮した総費用が事業コストとして発生するという点を押さえておくことが重要です。
テナント料に消費税はかかる?
テナント賃料(事業用物件の賃料)には、原則として消費税がかかります。これは、テナント賃料が「事業の対価」としてサービス提供に該当するため、消費税法上の課税対象となるためです。2019年10月以降、消費税率は10%となっています。借主が法人・個人を問わず、事業目的でテナントを借りる場合は、賃料に消費税が加算されます。
テナント賃料に影響を及ぼす要因
賃料相場は一定ではなく、立地条件や建物の状態、さらに需要と供給で決まることから、常に変動する可能性があります。賃料相場を決定する主な要因には、以下のような項目があります。
| 要因 | 内容 |
| ① 立地 | 都心 or 郊外、主要駅近、通行量など |
| ② 用途・業種 | 飲食店、美容院、事務所などで需要と坪単価は変化 |
| ③ 建物の状態 | 築年数・階数・構造・設備の有無など |
| ④ 周辺環境 | 商業施設や競合の存在、集客力の有無 |
| ⑤ 面積・間取り | 小規模店舗か大型フロアかによる柔軟性の差 |
| ⑥ 経済事情・税金 | 管理費や固定資産税の変動による影響 |
特に環境変化の多い都心は価格変動が激しく、契約時の賃料が適正価格であるかの見極めが重要です。それぞれの要因を詳しく見ていきましょう。
要因その1:立地
テナント物件の立地や周辺環境は、テナントの賃料に大きな影響を与える要因の1つです。特に、都市部とその他の地域では賃料相場に大きな差が生じます。例えば、東京や大阪など、特に人口の多い都市部では、需要が高いため賃料相場が全般的に高く設定されています。一方で、比較的人口が少ない地方都市や郊外の地域では、需要が限られているため賃料が低く設定される傾向があります。
同じ地域内でも、商業エリアや主要な交通ハブに近い物件は利便性が高く、賃料が高くなりがちです。逆に、人の集まる施設が少ない場所や交通アクセスが悪い場所では、賃料が低くなることが一般的です。
要因その2:用途
テナントの賃料は、用途や業種によっても大きく異なります。例えば、飲食店やカフェなどの店舗は、集客力の高い場所や視認性の良い立地が求められるため、賃料が高く設定されることが一般的です。飲食店やカフェなどの業種は、通行人の多い商業エリアや駅前など、立地が集客に直接影響するため、多少高い賃料を支払っても売上で回収できる場合が多いです。
一方、倉庫やオフィスなどの場合は、業種によっては必ずしも人通りが多い場所にある必要がなく、立地条件を緩く設定することで、賃料も比較的安くなることがあります。
要因その3:建物の価値
建物の価値もテナント賃料に大きな影響を与える要因であり、次の4つの条件に左右されます。
- 設備
- 階数
- 間取り
- 築年数
例えば、1階にある店舗はアクセスが良く集客が見込めるため、賃料が高くなる傾向があります。一方で、2階以上や地下階の場合、集客力が低下するため賃料が下がることが一般的です。また、新築やリノベーションされた物件は設備が新しく、賃料も高めに設定されることが多いです。逆に、築年数が増えると設備が老朽化し、維持費が増えるため、賃料が低下する傾向があります。
要因その4:経済的な事情
経済的な事情もテナント賃料に大きく影響を及ぼします。例えば、インフレが進行すると物価や不動産価格が上昇し、賃料も上がる可能性があります。貸主の維持費や固定資産税、管理費などが増加するため、賃料を引き上げる必要が生じるためです。
日本では「借地借家法」により、賃料の変更には正当な理由と借主の合意が必要です。借主としては、賃料の変更が正当なものであるかを見極めるために、経済的な背景を理解しておくことが重要です。
インフレによる賃料への影響が気になる方は次の記事を参考にしてください。インフレが経営に与える影響を回避する方法も詳しく解説しています。
テナント賃料の決め方
テナント賃料は、物件の収益性や市場相場を考慮し、適正な賃料を算出します。具体的な評価手法として、主に4つの手法があります。それぞれの評価手法について詳しく説明します。
| 評価手法 | 概要 | 活用場面 |
| 賃貸事例比較法 | 類似物件の賃貸事例を比較・補正して賃料を算出する方法 | 周辺に類似物件の賃貸事例が豊富にある場合や、市場動向を反映した賃料設定を行いたいときに有効です。新規募集時や賃料改定時に活用できます。 |
| 利回り法 | 土地価格に期待利回りを乗じて純賃料を求め、必要経費を加算して算出 | 貸主が投資効率や収益性を重視した賃料設定を行いたい場合、また不動産価格が大きく変動している局面で賃料を見直したいときに適しています。 |
| 差額配分法 | 現行賃料と新規賃料の差額を分配して調整する方法 | 継続中の賃貸借契約で、賃料の見直しや適正化を検討する際に有効です。既存テナントとの条件調整や、段階的な賃料改定を行いたい場合に活用できます。 |
| スライド法 | 合意時点からの変動率を乗じて賃料を再設定する方法 | 長期契約で物価や経済指標の変動を賃料に反映させたい場合や、定期的な賃料改定ルールを設けたいときに有効です。 |
新規設定賃料の算出方法として、収益分析法、積算法もあります。2種類の方法は、次の記事で詳しく解説しているので、気になる方は下記リンクをチェックしてください。
決め方その1:賃貸事例比較法
賃貸事例比較法とは、対象物件と類似する不動産の賃貸事例を比較し、補正を行いながら賃料を算出する手法を指します。
類似する物件や取引事例を集め、事情補正(特別な事情の反映)や時点修正(価格の変動)を行い、最終的に比較対象の賃料情報から対象物件の賃料を設定します。
賃貸事例比較法は、新規及び継続賃料の両方に利用され、実際の市場動向を反映した賃料設定が可能です。賃料の比較対象件数が多いほど、正確な賃料を算出しやすいといわれています。
決め方その2:利回り法
利回り法とは、継続賃料の設定に用いられる手法で、現行賃料の利回りを基にして賃料を算出する手法です。
具体的には、物件のある土地の価格に期待利回りを乗じて純賃料を求め、純賃料に必要経費として公租公課や管理費を加算した額を相当賃料とするものです。利回り法によって求められた賃料は、積算賃料と呼ばれています。
利回り法は、不動産価格が急激に変動する局面で使用されることが多く、貸主の収益を確保しやすい方法ですが、借主のコスト負担が増える傾向にあります。
決め方その3:差額配分法
差額配分法は、現行賃料と新規賃料との差額に基づいて賃料を調整する方法です。
具体的には、現在の賃料に新規賃料との差額の一部を加えることで、賃料を決定します。差額配分法は、賃料が上昇した場合に借主の負担を緩和するために使われますが、賃料の下落時には算出方法が複雑になる傾向にあります。
差額配分法は、既に継続中の賃貸借契約がある場合において、賃料適正化のように、何らかの理由により新たに設定される賃料を求める際に用いる算出法です。
決め方その4:スライド法
スライド法は、合意した時点から現時点までの経済的な変動率を乗じて賃料を算定する手法です。特に長期契約における継続賃料の設定で用いられます。
現行賃料に対して、以下のような指標を基に変動率を算出し、再設定します。
- 消費者物価指数(CPI)
- 賃金指数
- 公租公課(固定資産税など)の変動
これらの指標を用いることで、経済事情の変化を反映した柔軟な賃料設定が可能になります。ただし、どの指標を採用するかや契約内容によって結果が異なるため、慎重な検討が必要です。
🔍豆知識:新規契約時には「収益分析法」や「積算法」も活用されます。これらは店舗の売上や収益性に基づいて適正家賃を逆算する方法です。
固定賃料と歩合賃料
テナント賃料は大きく分けて「固定賃料」と「歩合賃料」の2つに分類されます。それぞれの賃料形態は、物件の種類や店舗の営業形態により異なります。固定賃料と歩合賃料について詳しく見ていきましょう。
固定賃料とは
固定賃料は、毎月決まった額を支払う賃料形態で、主に路面店やフリースタンディング店舗などで採用されます。
固定賃料の形態では、借主は一定の金額を支払うため、長期的なコスト予測がしやすく、経営計画を立てやすいという利点があります。一方、売上が低調な月でも賃料は変動せず、一定額を支払わなければならないため、リスクを借主が負う形になります。
歩合賃料とは
歩合賃料は、テナントの売上に応じて賃料が変動する形態です。
主にショッピングモールや商業施設で採用されており、売上の一定割合を賃料として支払うため、売上が高い月は賃料も増加し、負担が大きくなる一方、売上が低い月は賃料が軽減されるメリットがあります。
また、最低保証賃料を設定することで、貸主が一定額の賃料を確保する仕組みが採用されているケースも一般的です。その他、固定賃料と歩合賃料を組み合わせた賃料設定もあります。
テナントの賃料相場の目安

テナントの賃料相場は、坪単価で算出することが多く、次の2つの用途に分けて考えると良いでしょう。賃貸人のテナント収入の目安は、貸店舗とオフィスの場合で変わってきます。それぞれの賃料相場の目安について詳しく見ていきます。
目安その1:貸店舗の賃料相場
貸店舗の賃料相場は、立地や物件の種類や規模、用途などによって異なります。ここでは物件別のテナント料の考え方を解説いたします。
1. ショッピングモール系のテナント賃料
ショッピングモール系のテナント賃料は、固定賃料ではなく売上歩合制が一般的で、売上の10%程度(2011年~2022年の平均で物販10.32%、飲食11.14%)を目安に賃料として支払います。
具体的には、月間の売上額に対して売上歩率を掛けて賃料を算出する方法です。業種やショッピングモールの場所によっても歩率は異なり、人気のフードコートや高級ブランド店など、客単価の高い店舗では歩率が高めに設定されることがあります。賃料が売上に連動するため、収益状況に応じた柔軟な経営が可能です。
2. 百貨店系のテナント賃料
百貨店系のテナント賃料は、売上歩合制で設定されることが多く、ショッピングセンターよりも高い比率で設定される傾向にあります。 テナントの売上に応じて賃料が変動するため、売上が高いほど賃料も高くなる仕組みとなっています。
百貨店では、ブランド力のある店舗や高い売上が期待できるテナントを集めるため、賃料水準が高めに設定されることが多いです。東京都の人気エリアなどではさらに高い歩率が設定されることもあります。
3. 小規模物件のテナント賃料
小規模物件のテナント賃料は、物件の立地、用途、賃借人のニーズによって大きく異なります。小規模物件の賃料相場は地域ごとにある程度決まっていますが、用途や物件の条件によっては相場を大きく外れることもあるので注意が必要です。特に、飲食店やサービス業のように特定の立地を必要とする業態では、相場よりも高い賃料設定がされることもあります。
小規模物件の賃料交渉の際には、様々な要因を考慮することが重要です。
4. 居抜き物件のテナント賃料
居抜き物件のテナント賃料は、残された設備や家具の価値が加味されて決定されます。居抜き物件は、飲食店舗などで特に多く、設備が整っているため新たに設備投資が不要で、賃料が高くなることがあります。居抜き物件は供給数が少なく、条件によって賃料設定が多岐に渡るため、相場が不明瞭であることが多いです。
テナントを選ぶ際には、設備の状態やその価値を十分に考慮して判断することが求められます。
また以下の記事の「最近の店舗賃料動向」にて、直近の店舗の賃料相場を紹介しております。あわせてご参考ください。
目安その2:オフィスの賃料相場
オフィスのテナント料の相場は、一般的に坪1~2万円程度です。2025年の8月31日時点の主要都市の賃料平均は以下の通りです。
| エリア | 相場賃料 |
| 東京都心5区 | 31,022円/坪 |
| 札幌市 | 17,869円/坪 |
| 仙台市 | 15,268円/坪 |
| 名古屋市 | 17,916円/坪 |
| 大阪市 | 19,199円/坪 |
| 福岡市 | 18,107円/坪 |
大型オフィスビルは、賃料負担力の高い大企業が入居する可能性が高いため、賃料が高く設定される傾向があります。一方で、中小企業が入居する可能性の高いとされる、比較的小さなビルの賃料相場は低くなる傾向にあります。また、間取りや階数、周辺環境によっても賃料相場は大きく変動するため、条件を考慮して妥当な金額かを判断しましょう。
テナント賃料の交渉が必要になるケース
借主がテナント賃料の交渉を検討できるケースはいくつかあります。
まず、店舗の業績が賃料に見合っていない場合が挙げられます。たとえば、店舗を借りた当初に想定していた集客や売上が達成できていない場合、賃料が経営を圧迫する可能性があります。
また、契約時と比べて立地条件や周辺環境が大きく変化した場合も、賃料交渉の余地が生まれます。たとえば、周辺の商業施設が閉店したり、地域の人口が減少したりしたことで集客力が低下した場合、現行の賃料が実態に合わなくなることがあります。このような場合には、賃料を再度算定することが必要になる場合があります。
さらに、現在支払っている賃料が周辺の類似物件と比較して明らかに高額である場合も、賃料交渉を検討できる可能性があります。たとえば、同じエリアで同等の立地や設備条件を持つ他のテナントと比べて、自店舗の賃料が著しく高い場合には、貸主に対して賃料の見直しを申し入れる余地が考えられます。このような場合には、近隣物件の賃料相場や最新の募集条件など、客観的なデータを収集し、貸主に提示することが交渉の根拠となります。ただし、賃料交渉が必ず成立するとは限らず、契約内容や物件ごとの事情によって結果が異なる点には注意が必要です。
交渉の目安として、賃料が固定費に占める割合を参考にする方法もあります。業態によって異なりますが、たとえば飲食店の場合、店舗の賃料を売上の7〜10%に収めることが推奨されています。賃料が売上の7〜10%の範囲を超えている場合は、賃料の見直しを検討するとよいでしょう。
適正賃料のセルフチェック方法
テナント賃料が現在の相場と比べて適正かどうかを判断するためには、複数の情報源を活用して客観的に調査することが重要です。
| チェック方法 | 詳細 | 参考例 |
| 周辺物件の賃料相場を調べる | 賃貸ポータルサイトや不動産会社の情報をもとに、同じエリア・類似条件の物件の賃料を複数比較する。 | アットホーム、店舗相場TOWNなど |
| 市場レポート・統計データを参照 | 日本不動産研究所やCBREなどのレポートで、エリアごとの賃料動向やトレンドを把握する。 | 日本不動産研究所「店舗賃料トレンド」など |
| 賃料適正診断サービスを活用する | 賃料適正診断を利用し、実態データに基づいて現在の賃料が適正かどうかを客観的にチェックする。 | ビズキューブ・コンサルティング「賃料適正診断」 |
ビズキューブ・コンサルティングでは、実態分析賃料データ15万件分を駆使した高精度な賃料適正診断を無料で提供しています。診断に必要な事項を伝えることで、今の坪単価が適正なのか否か診断してくれるため、社内の調査工数を削減することができます。
費用は一切かからないため、現在の賃料が相場と乖離していないか気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
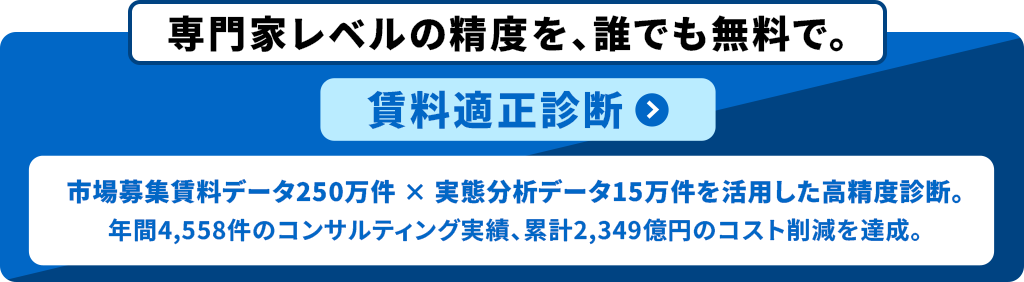
テナントの賃料交渉の成功率を上げるための方法
借主がテナントの賃料交渉を成功させるためには、貸主に対して納得のいく根拠を示すことが重要です。それぞれの方法について詳しく解説します。
方法その1:根拠になる資料を集める
借主がテナント賃料の交渉を成功させるには、根拠となる資料を準備することが重要です。
まず、賃貸借契約書や公正証書を用意し、契約内容や特約、更新条件などの詳細を確認します。さらに、支払い明細、過去の工事・修繕記録などを参照し、物件の現状が契約当時と比較してどう変わっているかを検証することも重要です。
加えて、自社の財務状況を示すPL(損益計算書)などの経済的指標も準備し、現状の経済事情や経営の健全性を伝えることが、交渉の説得力を高めるポイントとなります。さらに、近隣の類似物件の賃料相場や市場の動向に関する情報を収集し、貸主に納得してもらえるデータを揃えておくことも効果的です。
方法その2:関連する法律を確認する
借主が賃料交渉を行う際には、関連する法律の理解が欠かせません。
特に重要なのが借地借家法第32条に規定されている賃料増減請求権です。借地借家法では、経済情勢の変化、不動産の価値の変動、租税や負担の増減などに応じて、賃料の増減を合理的に請求できる権利を定めています。例えば、インフレによる物価上昇や周辺地域の再開発など、契約時に予測できなかった社会状況の変化が発生した場合には、賃料の見直しが妥当とされることがあります。
借主が行う賃料交渉時には、法律のポイントを押さえた合理的な理由と根拠を示すことで、貸主とのスムーズな交渉が期待できるでしょう。
方法その3:賃料減額サポートのプロに任せる
テナント賃料交渉には専門的な知識や準備が必要で、借主にとっては手間がかかる作業です。そのため、賃料減額サポートのプロであるコンサルティング会社に依頼することも1つの方法です。
専門家は、市場の賃料相場や法的な知識を駆使し、適正賃料の算出方法に基づいて、明確な根拠を提示することができます。明確な根拠により、貸主との協議サポートをスムーズに進め、妥当な条件での合意を得られる可能性が高まります。賃料交渉に不安を感じる場合や、自社だけでは解決が難しいと感じる場合は、専門家に相談することを検討すると良いでしょう。
外部のコンサルティングを導入することで期待できる効果や導入時の注意点については、次の記事で詳しく解説しています。
テナント賃料の見直しは無料賃料適正診断を活用しよう
借主がテナントの賃料交渉を成功させるためには、賃料の決め方を理解し、正確な情報と知識を持って臨むことが重要です。本記事では、テナント賃料の決め方や相場について詳しく解説しました。特に、現在の賃料が周辺相場や市場価格と乖離している場合には、見直しを検討すると良いでしょう。賃料の適正化には、不動産における専門的な知識と定期的な賃料診断の実施が必要です。
ビズキューブ・コンサルティングでは、コスト削減や経費の見直しを考える借主に向けて賃料適正化コンサルティングを実施しています。不動産コンサルタントならではの視点で、お客様の店舗経営にかかわるコスト削減をサポートします。
周辺の賃料相場と乖離している場合は、賃料適正診断を利用して適正な賃料を把握しておくことが大切です。貸主との円滑な交渉を望む方は、無料賃料適正診断を活用してみましょう。
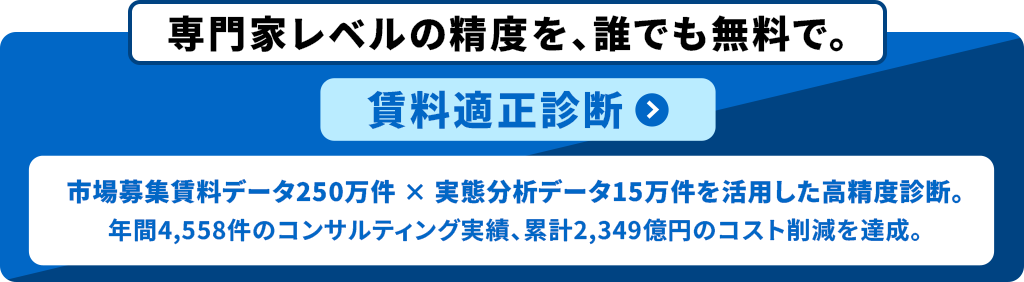
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。














 人気記事ランキング
人気記事ランキング

