年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
テナントの賃料減額を請求できる条件とは?適正化の流れや交渉の注意点もわかりやすく解説

テナント賃料は、店舗やオフィス運営における固定費の中でも大きな割合を占めます。そのため、減額の余地がある場合には、積極的に検討する価値があります。特に、法的な根拠があるケースでは、賃料の見直しが可能です。
以下のような悩みを持つ経営者や店舗責任者の方も少なくないでしょう。
- 賃料を本当に減額できるのか
- 自社の賃料が市場価格と比べて適正かどうか
- 賃料の見直しによってコスト削減を図りたい
本記事では、賃料減額の方法や法的根拠、適正賃料の判断基準について解説し、コスト削減につながる具体的なステップをご紹介します。
賃料減額の基礎知識
賃料増減請求権とは
賃料増減請求権は、賃貸借契約において当事者間の公平性を保つために認められている法的権利です。借主は、経済状況や不動産市場の変動に応じて、賃料の減額を求めることができます。たとえば、市場価格が下落しているにもかかわらず、契約賃料が高止まりしている場合には、合理的な水準への見直しを求めることが可能です。なお、貸主側も増額を請求できるため、双方が公平な条件で契約を維持するための仕組みといえます。
以下では、借主が行使する「賃料減額請求権」について詳しく見ていきます。
賃料減額請求権の法的根拠
賃料減額請求には、以下の法律が関係します。
借地借家法
借地借家法第11条および第32条では、契約締結後に経済状況や物件の状態が大きく変化した場合、賃料の増減を請求できる旨が定められています。これは「事情変更の原則」に基づくもので、予測困難な市場変動や物件の劣化などが該当します。たとえば、地域の不動産相場が急激に下落した場合、契約賃料が市場価格と乖離していると判断されれば、減額交渉の余地が生まれます。
交渉にあたっては、「賃料を下げてほしい」と一方的に申し出るのではなく、具体的な市場データや契約条件の変化を根拠として提示することが、建設的な解決につながります。
以下の記事では、賃料増減請求権について詳しく解説しております。あわせてご参考ください。
賃料の適正価格とは
テナント賃料の適正化は、賃借人と賃貸人の双方にとって公平な契約関係を維持するために重要です。特にテナントでは、賃料が経営に与える影響が大きいため、定期的な見直しが求められます。
テナント賃料に影響する主な要因は、以下の8点です。
| 主な要因 | |
| 設備 | 築年数 |
| 間取り | 立地条件(駅からの距離、商圏など) |
| 物件構造(耐震性、建材など) | 周辺環境、周辺の賃料相場 |
| 自店舗が周囲に与える影響(集客力や騒音など) | 租税公課の増減(固定資産税など) |
特に都市部では、環境の変化が激しく、賃料相場も短期間で変動する傾向があります。契約当初は適正だった賃料も、時間の経過とともに市場価格と乖離することがあります。
そのため、立地や物件条件に見合った賃料かどうかを定期的に確認し、現在の経営状況に適した価格設定を維持することが、コスト管理の観点からも重要です。
賃料減額請求が認められる条件
テナント賃料は、店舗運営における固定費の中でも特に大きな割合を占めるため、可能であれば適正な水準に見直したいと考える方も多いでしょう。賃料減額が認められる可能性がある主な条件は、以下の2つです。
1. 土地・建物の価格が低下した場合
借地借家法では、土地や建物の価格が下落するなど、経済事情が大きく変化した場合に賃料の見直しが可能とされています。賃料の適正化を検討する際には、以下のような経済的要因が考慮されます。
| 経済的要因 | 詳細 |
| 不動産の価格変動 | 地価の上昇・下落、建物の資産価値の変動などが賃料に影響する。 |
| 物価や所得水準の変動 | 消費者物価指数や平均所得の変化により、支払い能力や市場価格が変動する。 |
| 経済活動における制限 | パンデミックや自然災害、行政による営業制限などにより、物件の利用価値が低下する。 |
客観的な指標としては、消費者物価指数や賃料指数などが参考にされることがあり、これらのデータをもとに賃料減額の妥当性が判断されることがあります。なお、これらの判断は契約内容や交渉の状況によって異なるため、個別の事情に応じた対応が求められます。
2. 周辺の賃料相場が低下した場合
周辺の賃料相場が低下した場合、賃料の見直しにつながることがあります。借地借家法に基づく「事情変更の原則」により、契約時と異なる新たな状況が発生した際には、賃料の減額が認められる可能性があります。たとえば、予定されていた地域の再開発が中止された場合などのケースです。また、近隣の賃料相場の下落は、エリアの市場価値が下がっていることを示唆し、賃料減額の請求に有力な根拠となる場合があります。定期的に物件の立地や周辺環境をリサーチし、目指す利益に向けた適正な賃料を再評価することが重要です。
ただし、賃料は物件の個性や契約の特性にも影響されるので、単に周辺の賃料が下落しただけでは、自動的に賃料が下がるわけではないことを理解しておきましょう。
以下の記事では、店舗の賃料相場や適正化に関する問題点について解説しております。あわせてご参考ください。
賃貸借契約書のチェックポイント
テナント賃料の減額交渉を行う前に、まず確認すべきなのが賃貸借契約書の内容です。契約書には、賃料の見直しに関わる重要な条項が含まれていることがあり、交渉の可否や進め方に大きく影響します。
| チェック項目 | 詳細 |
| 賃料不減額特約 | 一定期間、賃料を減額しないとする条項。交渉を拒否される可能性があるが、法的には請求自体は可能。 |
| 自動増額特約 | 期間ごとに賃料を自動的に増額する条項。減額交渉が想定されていないため、難航する可能性がある。 |
| 管理会社の有無 | 交渉相手がオーナーか管理会社かを確認。契約書に記載されている管理会社名をチェック。 |
なお、借地借家法第32条第1項は強行法規とされており、「契約の条件にかかわらず」賃料の増減請求が可能です。つまり、契約書に減額を制限する特約があっても、法的には請求する権利が認められる場合があります。
ただし、特約がある場合は貸主の減額拒否の姿勢が強いことが多く、交渉には慎重な準備が必要です。
また、以下の記事では「賃料減額が認められた判例」について、具体的な事例を交えて詳しく紹介しています。交渉の参考として、ぜひご覧ください。
賃料減額の流れ
賃料適正化の流れは、適切な賃料の設定に必要な手順を踏んで行われます。以下は、賃料減額過程を効率的かつ公正に進めるために重要なステップとなります。
| 項目 | 詳細 |
| 賃料減額サポートの準備 | 賃料の妥当性を裏付けるための情報を収集・整理 |
| 価格と利回りの計算 | 物件の土地および建物の現在価格を評価し、利回りを計算することで、賃料の適正水準を算出 |
| 周辺環境の評価 | 物件周辺の環境変化が経営に与える影響を評価し、賃料設定に反映 |
| 賃料適正診断書の作成 | 調整を求める具体的な内容を記載した賃料適正診断書を作成し、賃借人に提出 |
| 賃料減額サポート内容の準備 | 賃貸人の対応力や立場を理解し、相互の利益を考慮した減額サポート内容を考案 |
| 適切なタイミングでの交渉 | 市場状況や物件状態を踏まえ、機会損失を避けるために適切な時期に賃料減額サポート |
以上の手順を適切に実施することで、賃料減額がスムーズに進行し、双方にとって公平な契約が成立する可能性が高まります。
賃料減額交渉における注意点
賃料減額交渉は賃貸人との信頼関係の上に成り立つため、適切な準備をする必要があります。賃料減額交渉における注意点は次の6つです。
注意点その1:新リース会計により賃料の会計処理が変わる
2027年以降の新リース会計基準導入に伴い、賃料の会計処理に大きな変更が生じる予定です。オペレーティングリースはオフバランスで処理されていましたが、新基準ではオンバランス処理が必要になり、リース資産と負債をバランスシートに計上することが求められます。
新リース会計基準は、リース取引全体に影響を及ぼし、特に不動産賃貸借契約が新たにリース取引の対象となるため、企業の財務報告における透明性が向上します。
そこで、新リース会計基準への変更に適応するためには、賃貸借契約の洗い出しや見直しが重要です。
企業は管理する賃貸借契約の数が増え、経理の負担が増大することが予想されるため、適切な時期に契約内容を確認し、必要に応じて調整を行うことが望ましいです。 新リース会計基準への変更に伴う賃料や賃貸借契約への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
注意点その2:賃貸人との信頼関係を壊さないように配慮する
賃料減額交渉を進める際は、賃貸人との信頼関係を大切にすることが重要です。交渉を始めるにあたり、単に賃料減額を求めるのではなく、公平な賃料で互いに納得できる合意を目指す姿勢が求められます。意見の相違が生じたとしても、脅迫的な言動を避け、冷静で建設的な対話を心がけましょう。
賃貸人との関係への配慮が、長期にわたる良好な関係を築くためには不可欠です。信頼を基にした賃料減額交渉は、双方の理解と尊重を深め、より良い解決策を見つける助けとなります。
注意点その3:賃料減額を希望する理由と根拠を示す
賃料減額の交渉を行う際、賃料減額を希望する理由と根拠を明確に示すことが重要です。周辺の賃料相場との乖離が理由の一つである場合、地域内で類似した物件の最新賃料データや不動産鑑定による適正賃料の評価報告を用意することが効果的です。
現在の賃料が市場価格と比べて不相応に高いことを客観的に示せます。また、経済状況の変化が影響している場合は、消費者物価指数や失業率の推移など、公的機関が公表する経済データを引用することも効果的です。明確な根拠を示すことで賃料減額の必要性に対する説得力が増し、賃料減額交渉を優位に進められます。
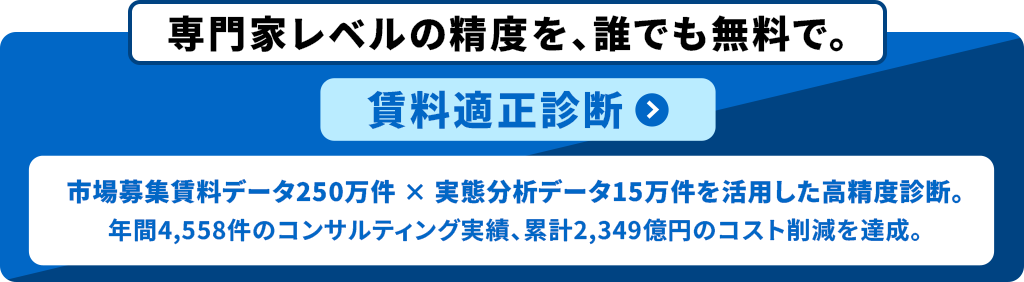
注意点その4:遡っての賃料減額はできない
賃料減額請求においては、遡っての賃料減額を求めることができない点に注意が必要です。賃料の減額請求は、意思表示が相手方に到達した時点からの効果しか持たないため、過去に遡って適用されることはありません。
したがって、賃料が市場価格と大幅に乖離していると感じた場合は、速やかに賃料減額請求権を行使することが重要です。請求のタイミングとしては、契約の更新時が基本ですが、法律上、いつでも行うことができるためです。過去の期間に対する賃料の返還を求めることはできないため、市場動向や自身の賃料状況を常に把握し、適切なタイミングで賃料減額請求権の行使・賃料減額交渉をすることが望ましいです。
注意点その5:賃料減額ができない特約がある
定期借家契約において「賃借人から賃料減額を請求することができない」という特約が設けられている場合、特約は有効とされ、賃料減額が困難になる点に注意が必要です。定期借家契約は更新が行われないため、契約期間中に賃料の再交渉を行うことは通常できません。特約がある場合、借主は契約前に内容をよく理解し、賃料の固定性を受け入れる必要があります。定期借家契約において賃料減額を考える場合は、契約の締結時に可能性を探るか、あるいは再契約時に条件を見直す機会を持つべきです。賃料減額ができないという特約がない場合は、法的に賃料減額請求が可能となることも理解しておくと良いでしょう。
注意点その6:通常の業務と並行する場合は負担が大きい
賃料の適正化交渉を経営層や社内人材が直接行う場合、専門的な知識が求められると同時に、通常業務と並行しての賃料減額交渉が大きな負担になる可能性があります。賃料減額は、市場分析、契約の見直し、法的な側面の理解といった複雑な作業を伴うため、精密なデータ収集と分析を行うには、多くの時間と労力が必要です。賃料減額交渉を社内で行う際には、作業負担を適切に管理し、ミスの発生を防ぐための対策も必要となります。賃料減額交渉は経済的利益をもたらす重要な業務ですが、通常業務がおろそかにならないよう配慮することが求められます。 賃料減額交渉の成功率を高めたい場合は、賃料適正化コンサルティングを活用することが有効です。気になる方は以下の記事をお読みください。
賃料減額のポイントと成功への道筋
賃料減額を検討する際には、市場の状況の変動や物件状況の変化を理解し、適正な価格設定を目指すことが重要です。
本記事では、賃料減額の条件や交渉のポイントについて詳しく解説しました。経営層や店舗責任者が賃料を見直すことで、無理のないコスト削減が可能となり、企業の財務体質を長期的に安定させることにもつながります。
賃料減額を成功させるためには、まず現在の賃料が適正かどうかを客観的に把握することが第一歩です。ビズキューブ・コンサルティングでは、累積35,558件の削減実績をもとに、「賃料適正化コンサルティング」を提供しています。さらに、250万件の市場募集賃料データと15万件の実態分析賃料データを活用し、高精度な「賃料適正価格診断」を無料で提供しています。
賃料減額について検討している方は、まずは無料診断から始めてみてはいかがでしょうか。診断結果は、交渉準備や社内説明資料としても活用できるため、実務面でも大きなメリットがあります。
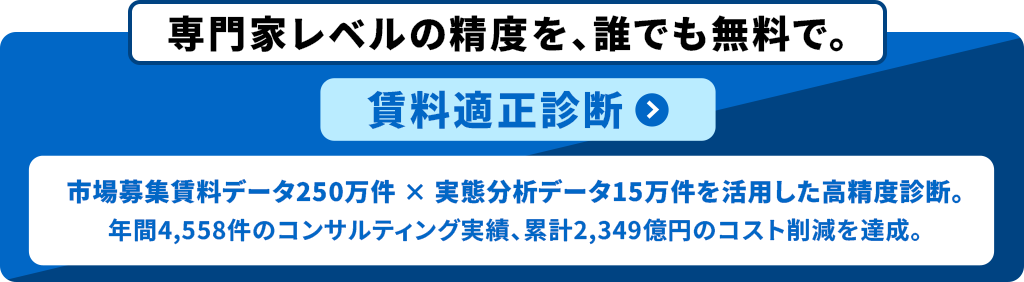

【監修者】幸谷 泰造(弁護士)
東京大学大学院情報理工学系研究科修了。ソニー株式会社で会社員として勤めた後弁護士となり、大手法律事務所で企業法務に従事。一棟アパートを所有する不動産投資家でもあり、不動産に関する知識を有する法律家として不動産に関する法律記事の作成や監修、大手契約書サイトにおいて不動産関連の契約書の監修を行っている。
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。














 人気記事ランキング
人気記事ランキング
