年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する店舗経営
【2025年11月版】店舗の退去費用はいくら?|高額請求を防ぐための契約・工事・交渉ポイント

- 目次
✅ 退去費用で損したくない方は、ぜひお読みください!
「契約書の内容が曖昧で不安…」「原状回復ってどこまで必要?」「工事費が高すぎる気がする…」
そんな疑問を抱える方に向けて、退去費用の全体像と対策を1記事で網羅しました。
特に、指定業者制による高額請求や、一式見積もりの不透明さ、造作譲渡・居抜き退去の判断ポイントなど、店舗退去ならではの注意点を具体的に解説しています。また、成功報酬型の工事費削減コンサルティングなど、初期費用を抑えながら退去コストを最適化できる方法も紹介しています。
店舗・オフィスの退去を検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
店舗の退去費用とは?閉店・移転時に発生するコストの全体像
閉店や移転を決断した際、多くの店舗オーナーが直面するのが「退去費用」という課題です。
原状回復工事や設備撤去に加え、契約解除に伴う違約金、不用品処分など、複数のコストが発生するため、事前に費用の全体像を把握しておくことが、予算管理とトラブル回避の第一歩となります。
特に飲食店・美容室・クリニックなどの業態では、オフィスや居住用物件と比べて、退去費用が高額になる傾向があります。
さらに、契約内容によっては、契約解除時の違約金や解約予告期間の未遵守による追加費用が発生するケースもあります。
たとえば、賃貸借契約書で「6か月前の解約予告」が定められているにもかかわらず、通知が遅れた場合、家賃の追加負担が生じる可能性があります。
このように、退去費用は「工事費」だけでなく、「契約条件」や「スケジュール管理」によっても大きく左右されます。
そのため、設備・契約・スケジュールの3つの視点から総合的に準備を進めることが重要です。
なぜ店舗退去に高額な費用がかかるのか
店舗退去費用が高額になる最大の理由は、原状回復工事の範囲が広く、業種ごとの専門設備が多いことです。
たとえば:
- 飲食店では、厨房設備・グリストラップ・ガス管・給排水設備の撤去が必要
- 美容室では、シャンプー台・専用配管・電気容量の復旧などが発生
- 小売店では、什器・レジカウンター・看板の撤去が中心
- クリニックでは、医療機器やX線室の鉛入り壁材など、特殊設備の処理が必要
加えて、商業施設やビルによっては「スケルトン戻し」が義務付けられており、壁・床・天井をすべて解体する必要があります。
このような工事は数十万円〜数百万円規模の費用がかかることもあり、オフィスや住宅よりも高額になりやすいのが実情です。
▼退去時に発生する主なコスト項目
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 原状回復工事 | 壁・床・天井の撤去、配管・配線の復旧 | スケルトン戻しが必要な場合は高額 |
| 設備撤去 | 厨房機器、シャンプー台、医療機器など | 業種によって専門業者が必要 |
| 外装工事 | 看板撤去、外壁補修 | 高所作業・クレーン作業が発生する場合あり |
| 廃材処分費 | 解体で発生する産業廃棄物の処理 | アスベスト等の特殊廃材は別途費用 |
| 契約関連費用 | 違約金、解約予告違反による追加費用 | 契約書の確認が必須 |
| 不用品処分 | 備品・什器の廃棄または買取 | 買取業者の活用で現金化も可能 |
退去費用は、「設備の種類」「契約条件」「工事業者の選定」によって大きく変動します。
まずは全体像を把握し、どの項目にどれだけの費用がかかる可能性があるのかを整理することが、高額請求を防ぐ第一歩です。
次のセクションでは、居住用物件との違いや、店舗退去ならではの注意点について詳しく解説します。
居住用物件との違い|店舗退去の特徴と注意点
店舗の退去は、居住用物件の退去とは大きく異なります。
原状回復の範囲・契約条件・設備の特殊性・費用構造など、あらゆる面で複雑かつ高額になりやすいため、同じ感覚で進めるとトラブルや予想外の出費につながる可能性があります。
ここでは、店舗退去ならではの特徴と注意点を整理し、スムーズな退去準備に役立つポイントを解説します。
1. 原状回復の範囲が広く、専門工事が必要
居住用物件では、壁紙や床の張り替え、簡単な清掃で済むことが多い一方、店舗ではスケルトン戻しが求められるケースが一般的です。
スケルトン戻しとは、壁・床・天井・設備をすべて撤去し、コンクリートむき出しの状態に戻す工事のこと。これにより、数十万円〜数百万円規模の費用が発生することもあります。
また、飲食店や美容室、クリニックなどでは、厨房設備・給排水・医療機器・専用配管などの撤去・復旧が必要となり、専門業者による対応が不可欠です。
2. 契約条件が複雑で、特約・指定業者制に注意
店舗の賃貸借契約では、特約条項によって借主の原状回復義務が拡大されているケースが多く見られます。
たとえば、経年劣化や通常損耗であっても借主負担とされていたり、設備の新品交換が義務付けられていたりすることがあります。
さらに、指定業者制が導入されている物件では、貸主が指定した業者以外に依頼できないため、相見積もりが取れず、費用が高騰しやすい点にも注意が必要です。
3. 契約解除・解約予告のタイミングが費用に直結
居住用物件では1〜2か月前の退去通知が一般的ですが、店舗契約では3〜6か月前の解約予告が必要とされることが多く、通知が遅れると家賃の追加負担が発生します。
また、契約解除に伴う違約金が発生するケースもあり、契約書の内容を事前に確認しておくことが重要です。
特に、複数年契約や定期借家契約の場合は、途中解約の条件が厳しく設定されていることがあるため、慎重な対応が求められます。
4. 居抜き・造作譲渡の可能性とリスク
店舗退去では、造作譲渡や居抜き退去によって原状回復工事を大幅に削減できる可能性があります。
ただし、造作譲渡を行う場合は、貸主の承諾が必要であり、契約上の制限やトラブルにも注意が必要です。
譲渡価格や引き渡し条件を明確にしないまま進めると、後々のトラブルにつながる恐れがあります。
5. トラブル防止には「証拠保全」がカギ
店舗退去では、写真・動画による記録が非常に重要です。
入居時と退去時の状態を比較できるよう、壁・床・天井・設備・外装などを網羅的に撮影しておくことで、原状回復範囲をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。
店舗退去は、居住用物件とは異なるリスクが存在します。
契約書の確認、業者選定、証拠保全など、事前準備を徹底することで、不要な費用やトラブルを回避することが可能です。
次のセクションでは、原状回復の範囲や経年劣化の判断ポイントについて詳しく解説します。
原状回復の範囲は契約書で決まる|店舗退去時に確認すべきポイント
店舗退去時に「どこまで原状回復が必要なのか」を判断するには、賃貸借契約書の内容を正確に把握することが最も重要です。
居住用物件とは異なり、店舗契約では特約や指定業者制など、借主に不利な条件が設定されているケースも多く、契約書の確認を怠ると、想定外の費用負担につながる可能性があります。
契約書で確認すべき「原状回復義務」の範囲
退去費用を左右する契約条件の中でも、以下の3点は特に注意が必要です。
1. 「スケルトン戻し」義務の有無
「スケルトン戻し」とは、壁・床・天井をすべて撤去し、コンクリートむき出しの状態に戻す工事を指します。
この義務がある場合、解体工事費用が100万円〜数百万円規模になるケースもあり、退去費用の大部分を占める可能性があります。
特に商業施設や大型ビルでは、スケルトン戻しが契約上の必須条件となっているケースが多いため、契約書の該当箇所を必ず確認しましょう。
2. 特約による借主負担の拡大
契約書に「特約」がある場合、本来オーナー負担となる経年劣化や通常損耗まで借主負担にされていることがあります。
例としては、以下のような条項が挙げられます。
- クロスや床材の全面張り替えを借主負担とする
- 設備の新品交換を義務付ける
一般的には、通常損耗はオーナー負担とされますが、店舗契約では特約が優先されるため、内容を細かく確認することが不可欠です。
3. 指定業者制・工事範囲の明記
商業施設やビルでは、貸主が指定する業者しか使えない「指定業者制」が設けられている場合があります。
実際に、相見積もりが取れないことで費用が相場より1.5〜2倍程度高くなる事例もあります。
また、契約書に「工事範囲」が明記されている場合、想定以上の工事を求められる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。契約書の内容次第で、退去費用は大きく変動します。
「スケルトン戻し」「特約」「指定業者制」などの条件を見落とさず、事前に確認・交渉することで、不要な費用負担を回避できる可能性があります。
店舗退去費用の相場と内訳【業種別・坪単価】
店舗退去費用は、業種・立地・契約条件・工事範囲によって大きく変動します。
特に飲食店や美容室、クリニックなどは専門設備が多く、オフィスや小売店よりも高額になりやすい傾向があります。
ここでは、業種別の坪単価相場と、費用を左右する主な要因を整理します。
業種別の退去費用相場(2025年11月時点)
| 業種 | 坪単価の目安 | 特徴・注意点 |
| 飲食店(軽飲食) | 約10万円/坪 | カフェ・軽食店など。厨房設備や給排水設備の撤去が必要。油汚れは少ないが、換気ダクトや電気工事が発生する場合あり。 |
| 飲食店(重飲食) | 約20万円/坪 | 焼肉・ラーメン店など。排気ダクト、防臭・防油設備、グリストラップの撤去や特殊清掃が必要で高額になりやすい。 |
| 美容室・サロン | 約8〜10万円/坪 | シャンプー台や給排水配管の撤去、電気容量の復旧が必要。薬剤汚れがある場合、追加費用が発生することも。 |
| 小売店 | 約5〜8万円/坪 | 什器・棚・レジカウンター・看板の撤去が中心。ロードサイド店舗では大型看板撤去にクレーン作業が必要な場合あり。 |
| オフィス | 約8〜10万円/坪 | 比較的シンプルな内装。間仕切りやカーペット撤去が中心で、飲食店より低コスト。 |
| クリニック | 約8〜15万円/坪 | 医療機器や特殊設備の撤去が必要。X線室などの鉛入り壁材がある場合、追加費用が大きくなる。 |
※上記は目安であり、契約条件や工事範囲によって大きく変動する可能性があります。
▼ポイント
- 商業施設やビルによっては「スケルトン戻し」が必須 → 坪単価が20万円以上になるケースも
- 指定業者制の場合、競争原理が働かず高額化しやすい
原状回復工事の主な項目と費用感
| 項目 | 内容 | 費用目安 | ポイント |
| 解体工事 | 壁・床・天井の撤去、間仕切りの解体 | 40〜100万円程度(坪数や構造による) | スケルトン戻しが必要な場合、100万円以上になることもあります。 |
| 設備撤去 | 厨房機器、給排水設備、ガス管、電気配線の撤去 | 飲食店の場合、50〜150万円が一般的 | ガス閉栓や電気容量の復旧など、専門業者による作業が必須。 |
| 衛生設備 | グリストラップの清掃・撤去、排水管の高圧洗浄 | 5〜15万円程度 | 油汚れや詰まりがひどい場合、追加費用が発生。 |
| 外装工事 | 看板撤去、外壁補修 | 小型看板で数万円、大型看板や高所作業は20〜50万円 | ロードサイド店舗や商業施設では、クレーンや足場設置が必要になるケースも。 |
| 廃材処分費 | 解体で発生する産業廃棄物の処理 | ※廃材の量で確定 | アスベストや特殊廃材が含まれる場合、別途高額請求の可能性あり。 |
テナント退去にかかる違約金
退去費用には、原状回復工事だけでなく、契約解除に伴う違約金が含まれる場合があります。
特に、定期借家契約や複数年契約を締結している場合、契約期間満了前の退去には違約金が発生する可能性があります。
違約金の金額や条件は契約書に明記されていることが多く、以下のようなケースが代表的です。
| 違約金のタイプ | 内容 | 具体例・注意点 |
| 残存期間の賃料相当額 | 契約期間満了前に退去する場合、残り期間分の賃料を請求される | 例:残り6か月 × 月額賃料 → 数十万円〜数百万円の負担になる可能性あり |
| 固定額の違約金 | 契約書に明記された金額を一律で支払う | 例:退去時に一律50万円の違約金が発生する契約など |
| 原状回復義務の強化 | 居抜き・造作譲渡が認められない場合、設備撤去やスケルトン戻しが必須となり、実質的に違約金と同等の工事費が発生 | 例:造作譲渡不可 → 厨房設備・配管撤去で100万円以上の工事費が発生するケースも |
また、解約予告期間の未遵守によって、追加の家賃負担が発生するケースもあります。
たとえば「6か月前までに通知」と定められている契約で、3か月前に通知した場合、残り3か月分の賃料を請求される可能性があります。
退去費用の全体像を把握するには、工事費だけでなく契約解除に伴う金銭的リスクも含めて検討することが重要です。
次のセクションでは、費用を抑えるための具体策について解説します。
原状回復業者の選び方|費用・対応力・交渉力の見極め方
原状回復工事は、退去費用の中でも最も金額が大きくなりやすい項目です。
そのため、業者選びの良し悪しが、最終的なコストやトラブル発生率に直結します。
特に商業施設や大型ビルでは「指定業者制」があるケースも多く、自由に業者を選べない状況でも、交渉力や見積もり精査によって費用を抑える余地は十分にあります。
ここでは、原状回復業者を選ぶ際に確認すべきポイントを整理します。
1. 見積もりの明確さと費用の妥当性
まず確認すべきは、見積もりの内訳が明確かどうかです。
「一式工事」とだけ記載された見積書では、不要な工事が含まれていても気づけず、高額請求につながるリスクがあります。
- 解体工事、設備撤去、廃材処分など、項目ごとの金額が記載されているか
- 相場と比較して妥当な金額か(坪単価や業種別の傾向を参考に)
複数業者から見積もりを取得し、相見積もりによる比較・交渉を行うことで、数十万円〜数百万円の削減につながる可能性があります。
2. 対応力と専門性
業者によって、対応できる工事の範囲や専門性が異なります。
特に以下のような業態では、業種特化の実績がある業者を選ぶことが重要です。
- 飲食店:厨房設備・グリストラップ・排気ダクトの撤去
- 美容室:シャンプー台・給排水配管・電気容量の復旧
- クリニック:医療機器・鉛入り壁材の処理
また、商業施設のルールや管理会社との調整に慣れているかも、スムーズな工事進行に影響します。
3. 交渉力と貸主対応の実績
貸主や管理会社との交渉が必要になる場面では、業者の交渉力や対応経験が費用削減に直結します。
たとえば、以下のような交渉が可能な業者であれば、退去費用の削減が期待できます。
- 指定業者制の中でも、工事内容の見直しや不要項目の削除を提案できる
- 賃貸借契約書を根拠に、借主負担の範囲を適正化できる
- 居抜き退去や造作譲渡の可能性を貸主と調整できる
4. 成功報酬型のコンサルティング活用
原状回復業者の選定に不安がある場合は、第三者によるコンサルティングの活用も有効です。
ビズキューブ・コンサルティングでは、成功報酬型の工事費削減コンサルティングを提供しております。工務実務40年の実績と不動産コンサルティングファームとして20年の実績を基に、不要な工事項目はないのかチェックして原状回復費用を適正価格に正すということを行っております。
過去の支援実績では、最大35%削減したケースもあります。
「原状回復費用が高い気がする…」「見積もりを見たが、適正価格なのか不安がある…」という方は工事費診断をお申込みください。
無料で工事費用が適正価格なのか、チェックします。
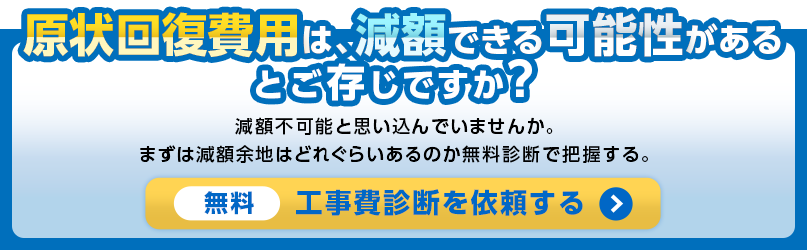
原状回復業者の選定は、退去費用の成否を左右する重要な工程です。
費用・対応力・交渉力の3点を軸に、信頼できる業者またはコンサルティングサービスを活用することで、無駄な出費やトラブルを未然に防ぐことが可能です。
次のセクションでは、退去費用を抑えるための具体策について解説します。
店舗退去費用を抑えるための具体策
店舗退去にかかる費用は、工夫次第で数十万円〜数百万円単位で削減できる可能性があります。
特に、原状回復工事や設備撤去などのコストは、業者選定や交渉方法によって大きく変動するため、事前の準備と戦略的な対応が重要です。
ここでは、実際の削減事例を踏まえながら、退去費用を抑えるための具体的な方法を紹介します。
1. 複数業者の見積もり比較でコスト削減
退去費用を抑える第一歩は、複数の業者から見積もりを取得することです。
同じ工事内容でも、業者によって金額に大きな差が出ることがあり、相見積もりによる比較は必須です。
- 指定業者制の物件でも、他社見積もりを交渉材料として提示できる場合あり
- 「一式見積もり」ではなく、項目ごとの内訳を明示させることで不要な工事を見抜ける
実際に、相見積もりを活用することで、100万円以上の削減に成功した事例もあります。
2. 居抜き退去・後継テナント活用で工事を減らす
後継テナントを見つけて居抜きで引き渡すことで、原状回復工事の大部分を省略できる可能性があります。
特に飲食店や美容室などは、既存設備をそのまま使いたいテナントが多いため、居抜きマッチングサービスや不動産会社の活用が有効です。
- 造作譲渡契約を結ぶことで、設備撤去費用を回避
- 貸主の承諾が必要なため、事前の交渉が重要
ただし、造作譲渡が認められない場合は、原状回復義務が強化され、結果的に高額な工事費が発生する可能性もあるため、契約条件の確認が不可欠です。
3. 不用品は買取業者に依頼して現金化
店舗退去時には、什器・厨房機器・家具などの不用品が大量に発生します。
これらをすべて廃棄すると、処分費用が数万円〜十数万円規模になることもありますが、買取業者に依頼することで現金化できる可能性があります。
- 業務用冷蔵庫・製氷機・レジ・什器などは中古市場で需要あり
- 買取価格がつかない場合でも、無料回収で処分費用を削減できるケースも
複数業者に査定を依頼し、買取・回収の条件を比較することがポイントです。
4. 自分で処分できる備品・設備の見極め方
すべての撤去・処分を業者に任せると費用がかさむため、自分で対応できる範囲を見極めることも重要です。
- 小型什器・家具・家電などは、自治体の粗大ごみ回収やリユースショップで対応可能
- 電気配線・給排水設備など、専門工事が必要なものは業者に任せる
「自分でできること」と「専門業者に任せるべきこと」を切り分けることで、無駄な外注費を抑えることができます。
5. 貸主との交渉で不要な工事を回避する
契約書や特約の内容を踏まえたうえで、貸主との交渉によって不要な工事を回避できるケースもあります。
たとえば、以下のような交渉が有効です。
- 契約書に明記されていないグレードアップ工事の拒否
- LED照明を旧型に戻すなど、意味のない復旧工事の回避
交渉の際は、契約書の文言や過去の使用状況を根拠として提示することで、合理的な判断を引き出しやすくなります。
6. 工事費削減コンサルティングで退去費用を削減
ビズキューブ・コンサルティングが提供する工事費削減コンサルティングでは、指定業者であっても退去費用の削減が可能です。実際に以下のような実績があります。
| 業種 | 坪数 | 当初の見積もり | 削減後の見積もり | 削減額 | 削減率 |
| 大手建設会社 | 店舗98坪 | ¥2,060万 | ¥1,430万 | ¥630万 | 31% |
| 電鉄系管理会社 | 店舗56坪 | ¥890万 | ¥715万 | ¥175万 | 20% |
無料の退去費用診断も実施しており、見積もりが適切であるか、不要な箇所まで対象となっていないか専門家が診断します。成功報酬型なので、まずはお問い合わせだけでも安心してご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
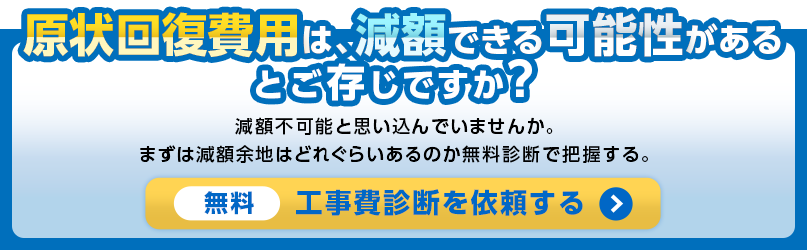
退去費用は、契約条件・工事内容・交渉力・不用品処分方法によって大きく変動します。
適切な業者選定と専門的な支援を活用することで、無駄な出費を防ぎ、コストを最適化することが可能です。
次のセクションでは、退去時に起こりやすいトラブル事例とその防止策について解説します。
店舗ならではの退去トラブル事例と防止策
店舗退去では、契約内容や工事範囲をめぐるトラブルが発生しやすく、知識不足や確認不足が原因で高額請求を受けるケースが少なくありません。
特に、居住用物件とは異なり、店舗契約では特約や指定業者制、造作譲渡の制限など、複雑な条件が絡むため、事前の確認と証拠保全が不可欠です。
ここでは、よくあるトラブル事例とその防止策を整理し、退去時のリスクを最小限に抑えるためのポイントを解説します。
よくあるトラブル例と防止策
| トラブル例 | 内容 | 防止策 |
| 経年劣化まで借主負担にされる | 例:6年以上使用したクロスや床材の全面張り替えを求められる | 契約書の特約を確認し、合理性がない場合は交渉。証拠として使用年数の記録を残す。 |
| グレードアップ工事の押し付け | 例:元の状態より高級な内装材や最新設備への交換を要求される | 原状回復義務の範囲を契約書で確認し、グレードアップは拒否可能。 |
| 不要な復旧工事の追加 | 例:LED照明を旧型蛍光灯に戻すなど、意味のない工事を請求される | 契約書に明記されていない工事は根拠を求め、交渉で削除を提案。 |
| 見積もりが不透明 | 例:「一式工事」とだけ記載され、詳細が不明 | 項目ごとの内訳を明示させ、複数業者で比較。第三者による診断も有効。 |
| 指定業者制で高額請求 | 商業施設やビルで指定業者しか使えず、相場の2〜3倍になることも | 指定業者でも交渉可能。不要項目の削除や費用見直しを提案。 |
トラブル防止のためにできること
1. 契約書・特約の事前確認
退去条件や原状回復義務の範囲は、契約書と特約にすべて記載されています。
退去前に必ず確認し、疑問点があれば貸主や管理会社に問い合わせましょう。
2. 写真・動画による証拠保全
入居時と退去時の状態を比較できるよう、壁・床・天井・設備・外装などを網羅的に撮影しておくことが重要です。
これにより、「破損」か「通常使用による摩耗」かの判断材料となり、不当な請求を防ぐ根拠になります。
3. 見積もりの精査と第三者の活用
「一式見積もり」や不明瞭な工事内容が含まれている場合は、第三者による見積もり診断を活用することで、不要な工事を排除できる可能性があります。
退去時のトラブルは、事前の確認・記録・交渉によって防ぐことが可能です。
専門的な支援を活用することで、安心して退去プロセスを進めることができます。
次のセクションでは、退去までの流れと準備チェックリストを紹介します。
退去までの流れと準備チェックリスト
店舗退去は、計画的に進めることでトラブルや追加費用を防ぐことができます。
特に、契約解除のタイミングや工事スケジュールの管理は、費用と貸主対応に大きく影響するため、早めの準備が重要です。
以下では、一般的な退去準備のタイムラインと、必要書類・確認事項をチェックリスト形式で整理します。
退去準備のタイムライン(目安:6か月前〜当日)
| 時期 | 主な作業内容 |
| 6か月前 | ・オーナーに解約予告を提出(契約で定められた期間を確認)・契約書で「原状回復義務」「スケルトン戻し」「指定業者制」の有無を確認 |
| 3〜4か月前 | ・複数業者から見積もりを取得(相見積もりでコスト比較)・居抜き退去(造作譲渡)の可能性を検討 |
| 2か月前 | ・原状回復業者を決定・工事スケジュールを確定し、ビル管理会社に申請 |
| 1か月前 | ・原状回復工事を開始・貸主と工事内容を再確認(追加工事リスクを回避) |
| 退去当日 | ・工事完了を確認し、写真・動画で記録・鍵の返却、引渡し書類の受領 |
必要書類・連絡事項のチェックリスト
1. 契約書・特約の確認(退去条件を把握)
- 契約書や特約を事前に確認し、「スケルトン戻し」や「指定業者制」の有無をチェック。
- 契約条件によって、工事範囲や依頼先が決まり、不要な工事や高額請求を避けられるかどうかが変わるため、交渉や費用に大きく影響します。
2. 解約通知書(提出期限を守る)
- 契約書で定められた解約予告期間(通常3〜6か月前)を確認し、書面で提出。
- 提出日と受領確認を記録しておくと、後日のトラブル防止になります。
3. 工事見積書・契約書(内訳を明確に)
- 「一式工事」ではなく、解体・設備撤去・廃材処分など項目ごとの金額を明記させる。
- 複数業者の見積もりを比較し、相場感を把握することが重要です。
4. 工事完了報告書(貸主確認用)
- 工事終了後、貸主または管理会社の立ち会い確認を受け、書面で証明を残す。
- 報告書には工事範囲・完了日・写真添付を含めると安心。
5. 鍵の返却確認書
- 返却した鍵の本数・返却日・受領者名を明記。
- 紛失や返却漏れによる追加請求リスクを防ぐため必須。
6. 写真・動画による現状記録(トラブル防止の証拠)
- 入居時と退去時の状態を比較できるように撮影。
- 壁・床・天井・設備・外装など、原状回復の対象箇所を網羅することがポイント。
居抜きテナント特有の退去ポイント
居抜きで入居したテナントが退去する場合、通常の原状回復とは異なる注意点があります。
前テナントの造作を引き継いでいるため、どこまでが自分の負担範囲かが曖昧になりやすく、契約書の確認が特に重要です。
| チェック項目 | 内容 | 注意点・対応策 |
| 造作譲渡契約の内容確認 | 譲渡された設備・内装の所有権がどこにあるかを確認 | 所有権によって撤去義務が変わるため、契約書の記載を精査 |
| 貸主との合意内容の再確認 | 入居時に「原状回復不要」とされていた範囲が変更されていないか確認 | 書面での合意があるかを確認し、口頭のみの合意はリスクあり |
| 後継テナントの居抜き希望確認 | 次のテナントが居抜き希望かどうかを早期に確認 | 居抜きマッチングサービスや不動産会社の活用が有効。早期に動くことで工事費削減につながる可能性あり |
| 設備の状態記録 | 前テナント由来の設備に不具合がある場合、責任の所在が曖昧になりやすい | 写真・動画で記録を残し、退去時のトラブル防止に活用 |
居抜きテナントの退去は、契約・設備・責任範囲の整理がカギです。
曖昧なまま進めると、本来不要な工事や費用を負担するリスクがあるため、早めの確認と交渉が欠かせません。
貸主都合で退去を求められるケースと対応策
通常、店舗の退去は借主(テナント)の都合によって行われますが、貸主側から退去を求められるケースも存在します。
このような状況では、借主にとって予期せぬコストや業務負担が発生する可能性があるため、契約内容の確認と冷静な対応が重要です。
貸主が退去を求める主なケース
| ケース | 内容 | 借主側の注意点 |
| 建物の老朽化・再開発 | 建替えや大規模修繕のため、全テナントに退去を求める | 契約期間中でも退去を求められる可能性あり。契約書の「中途解約条項」や「立退料」規定を確認 |
| 賃料改定・収益改善目的 | 高賃料テナントへの入替を目的に、退去を促す | 賃料交渉の余地がある場合は、賃料適正診断を活用し、継続交渉も検討可能 |
| 契約違反・使用状況の不備 | 用途違反・騒音・衛生面など、契約違反を理由に退去を求める | 指摘内容が契約違反に該当するかを確認。改善提案や交渉の余地がある場合も |
| 定期借家契約の満了 | 契約期間終了に伴い、更新なしで退去を求められる | 定期借家契約は原則更新不可。退去準備を早めに開始し、移転先の検討を進める必要あり |
借主が取るべき対応一覧
| 対応項目 | 内容 | 対応のポイント |
| 契約書の条項を確認する | 「中途解約」「立退き」「更新」などの条項を確認し、貸主の主張が契約に基づいているかを判断 | 契約書の原文を精査し、曖昧な点は貸主に確認。専門家のチェックも有効 |
| 立退料の有無・交渉余地を探る | 再開発や建替えによる退去の場合、立退料(移転費用・営業補償)が発生する可能性あり | 契約書に立退料の記載があるか確認。交渉の余地がある場合は専門家の支援を活用 |
| 賃料交渉による継続の可能性を探る | 賃料改定を目的とした退去促進の場合、賃料適正化診断を活用し、継続交渉を行う | 賃料が相場より高い場合は、診断結果を根拠に交渉。退去回避につながる可能性あり |
契約管理の重要性と外部支援の活用
貸主からの退去要請は、契約管理が不十分な場合に突然発生し、経営判断を迫られる重大な局面となります。
こうした事態に備えるためには、契約書の定期的な見直しや、専門家による契約管理支援が有効です。
ビズキューブ・コンサルティングでは、賃貸借契約書に特化した契約管理ツールや物件管理など、店舗運営をサポートするサービスを多数提供しています。多店舗展開をしているが、管理体制が十分ではなく不安がある…と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社にとって最適な店舗運営を実現できるサービスをご案内いたします。
まとめ|退去費用を「予測・削減・防止」するために
店舗退去は、相場を把握し、契約内容を確認し、計画的に準備することで、無駄なコストやトラブルを防ぐことができます。本記事で解説した重要ポイントを振り返ります。
- 退去費用の相場を把握する
└業種別・坪単価を参考に、予算を事前に立てることが重要です。
└例:飲食店は坪5〜10万円、20坪なら100〜200万円が目安。 - 契約書とガイドラインを確認する
└「スケルトン戻し」義務や特約の有無を必ずチェック。 - 複数見積もりと交渉で削減する
└相見積もりで数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。
└実例では、1,000万円超の見積もりが半額以下になったケースも。 - トラブル防止策を徹底する
└写真・動画で証拠を残し、不要な工事やグレードアップ要求を拒否。
└見積もりは「一式」ではなく、項目ごとの金額を明示させることがポイント。
退去は経営判断の大きな節目です。「知らなかった」で損をしないために、今から準備を始めましょう。
賃料によるコスト削減は専門家に相談を
退去費用の削減だけでなく、今後の店舗運営におけるコスト最適化も重要です。特に賃料の見直しは、継続的な経費削減につながります。たとえば、数店舗を運営している場合、1店舗あたり月数万円の賃料削減でも、年間で数百万円規模の改善につながります。
実際、ビズキューブ・コンサルティングは、
- 累計50,000件以上のコンサルティング実績
- 平均減額率16.2%、成功率64.6%
を誇り、累計削減金額2,349億円の実績があります。
賃料削減を実施することで、店舗はコスト最適化を加速できます。
まずは無料相談で、退去費用と賃料の両方を削減する方法を確認してみましょう。
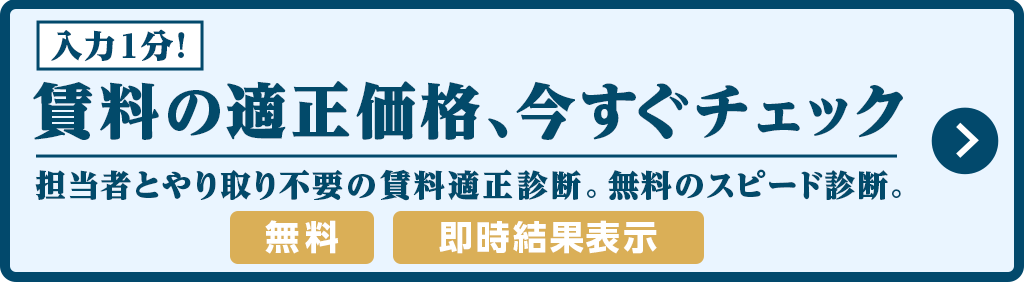
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。










 人気記事ランキング
人気記事ランキング

