年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認するコスト関連
賃料に消費税はかかる?テナントで課税対象となる費用を解説
で課税される主な費用.jpg)
- 目次
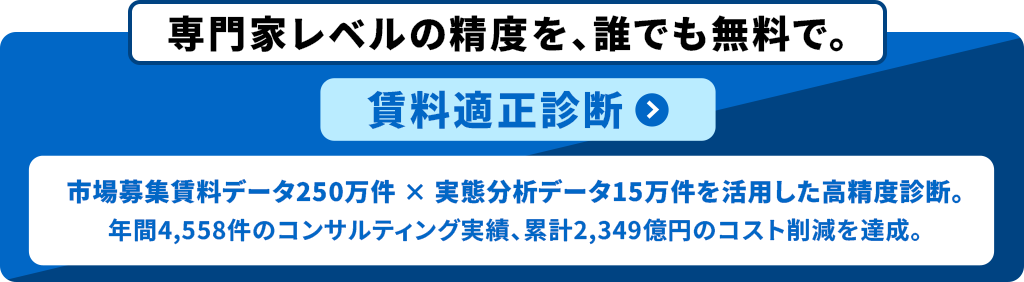
モノを購入する際は、当然のように消費税を支払いますが、賃料の消費税について考える機会はあまりないかもしれません。
しかし賃料は企業経営で必要な固定費の中でも多くの割合を占めるため、金額だけでなく消費税の有無や税率についても確認しておくことが重要です。
また賃料だけでなく、テナント(事務所・店舗)を借りる際に課税される費用についても解説していきます。
テナントを借りるときの賃料に消費税はかかる?
事業利用を目的としてテナントを借りる場合、支払う賃料に消費税は発生するのでしょうか。
テナントは、一般的な住宅用の物件と比べて賃料が高い傾向にあるため、事前に把握しておくことが望ましいです。。
テナントとは?
テナントとは、事務所や店舗などビジネスを行う場所として貸し出される物件、またはそれらを借り受ける借主のことを指します。居住用賃貸物件との違いは、個人と法人のどちらが借りるのかではなく、物件の使用用途にあります。
住居用の場合、借主自身が暮らす目的で物件を利用するのが基本です。
一方、事業用の場合は事業者がビジネス利用を目的として物件を借りるため、その用途はさまざまです。
一戸建てを借りて事務所や店舗として利用したり、アパートの部屋を借りて一人暮らし用の社宅にしたりするケースが考えられます。
また、テナントは、居住用と比べて賃料や初期費用が高い傾向にあります。
事業用の場合、利用者が多く、居住用と比較して建物が傷みやすいとされるためです。
テナントの初期費用には、前家賃、敷金、礼金、仲介手数料などが含まれます。
賃料に消費税はかかる?
テナントの賃料には消費税が課されます。テナントの貸付によって生じる賃料は、事業の対価とみなされるため、消費税の適用範囲に含まれるのです。消費税の税率は、2019年(令和元年)10月1日に8%から10%に変更されました。
なお、居住用賃貸物件では、家賃に消費税は課されません。居住用賃貸物件の貸付は非課税取引と扱われるためです。
ただし、貸付期間が1カ月未満のケースや、旅館業での利用とみなされる場合は課税されます。例えば、ウィークリーマンションの賃貸や民泊を営む場合などが該当します。
また、上記の内容は家賃と合わせて支払う管理費や共益費、土地部分を賃貸する際の地代についても同様です。
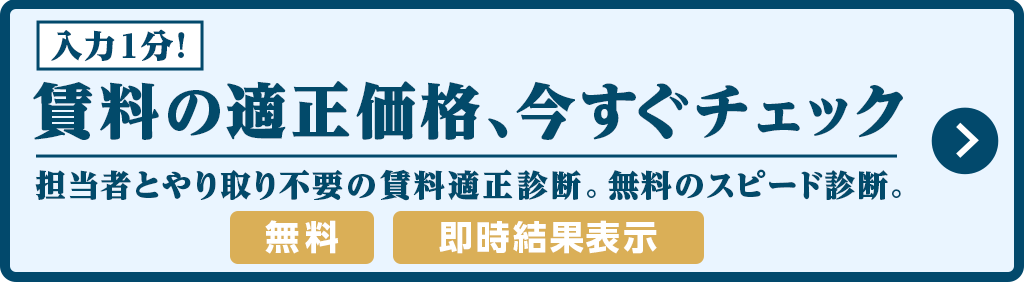
テナントで賃料同様に消費税がかかる費用
テナントを借りる際、貸主(大家さん、家主)や不動産会社に支払う費用は賃料だけではありません。
こちらでは、項目別に消費税の有無について解説します。
1. 前賃料
前賃料とは、契約開始前にあらかじめ支払う賃料のことです。通常は賃貸借契約の締結時に、翌月分の賃料などとして支払われます。前賃料は将来の利用に対する対価として位置づけられるため、通常の賃料と同様に消費税が課税されます。また、支払い時期が異なるだけで性質は賃料と同一であるため、課税要件を満たします。
2. 礼金
礼金は貸主に対するお礼の意味合いで支払う費用です。
契約終了により返還されるお金は課税対象になりませんが、礼金は退去時に返還されないことから、「資産の譲渡等の対価」と見なされ消費税が課されます。
ただし、居住用の場合は非課税となり、消費税はかかりません。
【出典】「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
3. 共益費・管理費
共益費や管理費は、ビルや施設の共有部分の維持管理費用を負担するために支払うものです。たとえば、エレベーターや廊下の清掃、電気代などが含まれます。これらの費用は、借主がサービスを受ける対価としての性格があるため、消費税が課税されます。契約書に明記された額が課税対象となるため、金額を確認することが重要です。
4. 敷金、保証金
敷金とは、賃料の滞納や、退去時の修繕費用に備えて貸主に預けておくお金のこと。
保証金も敷金と似た意味合いのお金で、主に関西地方で使用されています。
事業用の場合、退去時に返還されるときは非課税、返還されないケースでは課税対象となります。
居住用の場合はいずれも非課税です。
5. 更新料
更新料は賃貸借契約を更新する際に貸主に対して支払う費用です。
事業用の場合は課税され、居住用は非課税となります。
また、事務手続きの対価として仲介の不動産会社に支払う「更新手数料」にも消費税がかかります。
更新手数料は、事業用・居住用いずれも課税されるのがポイントです。
6. 仲介手数料
仲介手数料とは、賃貸借契約を仲介する不動産会社に支払うお金です。
仲介手数料は不動産会社が営む仲介業の対価という性質を持つため、事業用・居住用に関係なく課税されます。
7. 駐車場代
駐車場代については、事業用・居住用いずれも基本的には課税されます。
ただし、駐車場付き物件のように、家賃に施設利用料が含まれている場合は課税されません。
テナントにおける費用で、課税・非課税を注意すべき点

テナントにおける費用で課税か非課税かで注意すべき点は、以下の3つです。
1. 【課税対象】契約終了後の割増賃料
契約期間終了後も物件を使用し続ける場合、貸主が定めた割増賃料が発生することがあります。この割増賃料は、通常の賃料と同じく物件使用に対する対価とみなされるため、消費税が課税されます。例えば、契約更新を行わずに物件を使用し続けた際の割増賃料がこれに該当します。このようなケースでは、契約書に明記された割増率や条件に従い課税対象となるため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。
2. 【課税対象】敷金・保証金の償却分
敷金や保証金そのものは非課税ですが、契約時に償却分が設定されている場合、その償却分には消費税が課税されます。償却とは、敷金や保証金の一部を退去時に返還せず、貸主が手元に残すことを指します。この償却分は、実質的に賃料やサービスの対価として扱われるため課税対象となります。特に契約書で償却条件が明記されている場合には、消費税が加算される金額を把握しておくことが重要です。
3. 【非課税対象】中途解約時の違約金
中途解約時に発生する違約金は、契約期間内に解約することで貸主に生じる損害を補填するための金銭であり、「損害賠償」としての性質を持ちます。このため、賃料やサービスの提供に対する対価ではなく、消費税の課税対象にはなりません。ただし、契約書に記載される違約金の名目や内容が「未払賃料」などとされる場合には課税対象となる可能性もあるため、契約条件の確認が重要です。
テナントの修繕積立金の消費税の扱い
テナントによっては、毎月修繕積立金を支払う場合があります。この修繕積立金は、将来的な建物の修繕費用に充てるために積み立てられるものですが、原則として消費税は課税されません。
修繕積立金が非課税となるのは、管理組合が区分所有者から集めたお金を、将来の修繕工事のために保管しているという性質があるからです。つまり、管理組合がサービスを提供しているわけではないため、消費税は課税されません。
インボイス制度とテナント賃料
2023年10月から始まったインボイス制度は、テナント賃料にも影響があります。制度の概要を理解し、適切に対応することが重要です。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。登録を受けた事業者が発行するインボイス(適格請求書)の保存が、仕入税額控除の要件となります。
インボイス制度をわかりやすく解説した記事はこちら
テナント賃料におけるインボイスの必要性
インボイス制度では、適格請求書発行事業者のみが仕入税額控除を受けることが可能です。テナント賃料に関しても、貸主が適格請求書発行事業者であるかを確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
テナントを借りる事業者は、賃料にかかる消費税を仕入税額控除することで、納税額を減らすことができます。そのためには、貸主からインボイスを発行してもらう必要があります。
仕入税額控除の条件
仕入税額控除を受けるには、貸主がインボイス制度に登録している事業者であることが必要です。また、受け取ったインボイスは、適切に保存する必要があります。
貸主がインボイス制度に登録しているかどうかは、契約時に確認しておくことが重要です。登録事業者であれば、インボイスを発行してもらうことができます。
免税事業者の場合のリスク
貸主が免税事業者の場合、インボイスを発行してもらえません。この場合、借主は仕入税額控除が受けられないため、実質的な負担が増える可能性もあります
テナントの賃料に関してよくある疑問
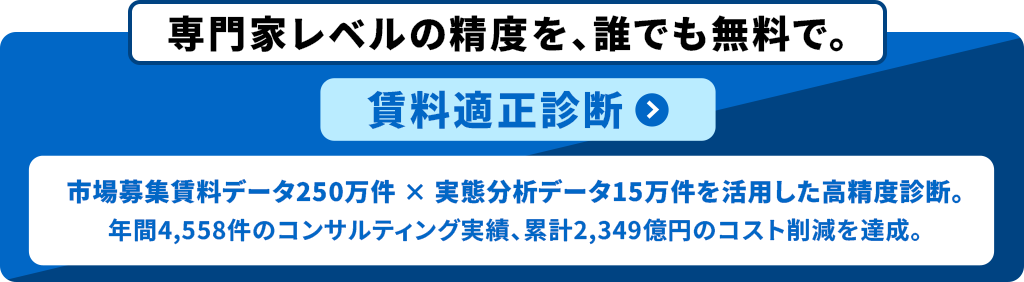
賃貸物件を事業用として借りると、賃料の支払いに税金が発生しますが、実際は事業用かどうか判断が難しいケースも少なくありません。ここでは、2つのケースについて確認します。
住居と兼用の場合、賃料に消費税はかかる?
両者が明確に区分できる場合、事業用の部分のみ課税されるのが基本です。
例えば、1階が飲食店の店舗で2階が住居の場合、店舗部分は課税され住宅部分は非課税対象となります。
一方、両者が明確に分かれておらず、主に住居として用いられる場合は非課税となることが一般的です。
具体的には、貸主が住宅兼事務所としての使用を認めていて、居住用賃貸物件として契約していれば非課税となります。
ただし、事前に居住用として契約した賃貸物件を、後から事業用として利用するのは契約違反です。
違約金の支払い、契約解除などのペナルティーを課されるおそれがあるため注意しましょう。
居住用から事業用に変更する際は、新たに契約書を交わす必要があります。
会社が借り上げた社宅・従業員寮は、家賃に消費税がかかる?
社宅や従業員寮は、利用目的が従業員の居住用のため、会社が貸主に支払う家賃に消費税はかかりません。
会社が従業員に有料で住まいを提供する場合も、同様の理由で非課税となります。
消費税率の変動と賃料への影響
過去の消費税率引き上げ時には、賃料にも様々な影響がありました。また、将来的な税率変動の可能性も考慮し、常に注意しておく必要があります。
過去の消費税率引き上げ時の経過措置
過去の消費税率引き上げ時には、多くの場合、経過措置が設けられました。例えば、2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられた際、テナントの賃貸借契約においては、契約時期によって適用される税率が異なるケースが見られました。
具体的には、2019年9月30日までに締結された契約で、かつ賃料の支払い期日が2019年10月1日以降となる場合でも、一定の条件を満たせば旧税率の8%が適用される経過措置が設けられました。これは、急激な負担増を避けるための措置でしたが、契約内容や支払い期日によって適用される税率が異なるため、混乱が生じることもありました。
参考:平成31年10月1日以以後適応する消 費 税 率 等 に 関 す る 経 過 措 置(国税庁)
今後の消費税率変動の可能性と影響
将来的に消費税率が変動した場合、テナント賃料にも影響が出る可能性があります。例えば、消費税率が再び引き上げられた場合、貸主は賃料に上乗せして消費税を請求する可能性も考えられます。
また、消費税率の変動は、契約更新のタイミングで賃料を見直す要因となることもあります。貸主は、消費税率の変動を理由に賃料の値上げを要求する可能性があり、借主は、賃料交渉を余儀なくされることも考えられます。
そのため、テナントを借りる際には、契約期間や更新時期だけでなく、消費税率の変動が賃料にどのような影響を与えるのかについても、事前に確認しておくことが重要です。契約書の内容をよく確認し、将来的な税率変動リスクを考慮した上で、契約を進めるようにしましょう。
消費税がかかるテナント賃料のインボイス制度対応は終わりましたか?
テナントを借りる際に必要となる、賃料をはじめとした費用に消費税が生じるかどうかについてお伝えしました。
消費税の有無は、選択した建物の種類や借主の性質ではなく、物件の使い道が関係します。
一部例外はあるものの、事業用であれば課税対象、居住用の場合は非課税となります。
2023年10月からはインボイス制度が開始されます。課税対象であるテナント賃料も例外ではありません。
モノを購入する際の支払いとは異なることが多い賃料の支払い。インボイス制度への対応も異なるケースがあります。
「請求書を交付しないのだが、どう対応すれば良いか?」「賃貸借契約書の更新は必要なのか?」など、対応に疑問がある際は、ビズキューブ・コンサルティング株式会社にお気軽にご相談ください。
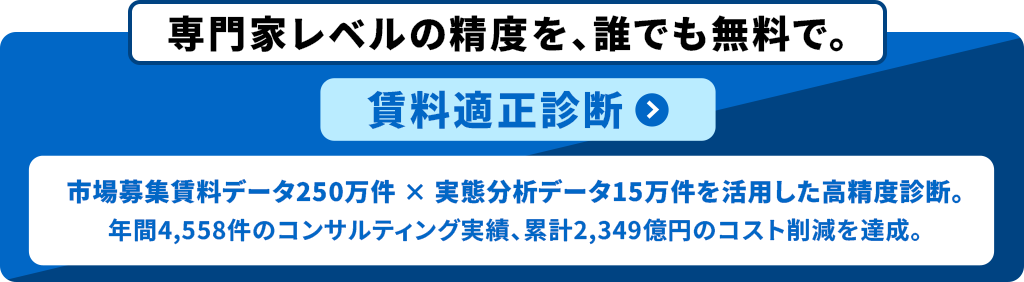
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。





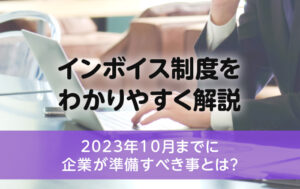
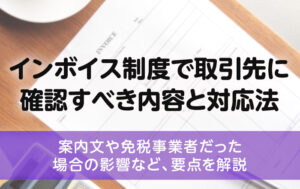






 人気記事ランキング
人気記事ランキング

