年間約5,000件実施されている
3分で完了する『賃料適正診断』
年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?
成功事例を確認する店舗経営
店舗の契約更新で損しないためには?更新料の相場と注意すべき手続き・交渉ポイント

- 目次
契約更新とは?基本の仕組みと流れ
店舗やテナントの契約更新とは、賃貸借契約の満了時に、貸主(オーナー)と借主(店舗経営者)が再度契約を結ぶ手続きのことです。
この更新手続きは、店舗運営を継続するうえで非常に重要なポイントであり、条件を正しく理解していないと、更新料の負担増や契約条件の不利な変更といったトラブルにつながる可能性があります。
本記事は普通借家契約を前提に解説します。定期借家契約には更新制度がなく、満了で契約は終了するためです。
契約更新における普通借家契約と定期借家契約の違い
| 契約形態 | 詳細 |
| 普通借家契約 | 更新制度あり。右記3形態(法定・合意・自動)で継続することがあります。 |
| 定期借家契約 | 期間満了で終了。継続する場合は再契約(新規契約)の可否や条件を別途協議します。 |
普通借家契約の契約更新の形態
普通借家契約の更新は、実務上次のいずれかで成立します。
| 更新形態 | 詳細 |
| 法定更新 | 借地借家法第26条1項に基づく更新形態です。建物賃貸借契約に期間の定めがある場合、契約満了の1年前から6か月前までの間に、貸主または借主が「更新しない旨」または「条件を変更しなければ更新しない旨」の通知をしなかったときは、契約は従前と同一の条件で更新されたものとみなされます。ただし、更新後の契約期間は「定めがないもの」とされます。 |
| 合意更新 | 満了の前後で、貸主と借主が賃料・期間・更新料・特約等に合意し、契約書や覚書で明確化します。 条件変更を伴う場合は、この合意更新で取り扱われることが一般的です。 |
| 自動更新(契約条項による更新) | 契約書に自動更新条項がある場合、当事者からの所定の通知がなければ、従前条件で更新される運用です。 法的な位置づけとしては、あらかじめ合意された更新方式(合意更新の一形態)と理解されることが多く、実務上の便宜から独立して説明することがあります。 |
普通借家契約では、必ずしも更新手続きが必要なわけではありません。法定更新によって契約が継続する場合もあります。ただし、貸主から更新条件の案内が届いた場合は、合意更新の局面として条件を確認し、必要に応じて交渉や文書化を進めると安心です。
合意更新を行う場合の準備時期(任意の目安)
普通借家契約では、法定更新や自動更新により手続きなく継続することがあります。一方、賃料や更新料、契約期間などを見直したいときは、満了の3〜6か月前から現行条項の整理と条件提示の打診を始め、2〜3か月前に条件協議・対案提示、1か月前に合意内容を文書化し、更新時に精算する流れが目安になります。実際の期日や必要書類は契約書の定めと貸主の運用により異なるため、ご自身の契約条項で必ず確認してください。
更新時に確認すべき契約書の条項
契約更新の際は、必ず契約書の各条項を確認することが欠かせません。特に注目すべき条項は以下の4点です。
- 賃料の設定:
更新後の賃料が据え置きなのか、相場に応じて改定されるのかを確認してください。例えば、「更新時に賃料を再協議する」と記載されていれば、貸主から値上げ提案が来る可能性があります。周辺の賃料相場を調べ、根拠を持って交渉できるよう準備することが重要です。 - 更新料・事務手数料:
更新料が「賃料の1か月分」なのか「固定額(例:10万円)」なのか、事務手数料が「3万円」など明記されているかを確認しましょう。 - 更新の条件:
更新後の契約期間が「2年」なのか「1年ごとに自動更新」なのか、また「用途変更禁止」「営業時間制限」などの特約が追加されていないかを必ず確認してください。特約は後々トラブルになりやすいため、見落としは禁物です。 - 解約についての条項:
解約予告期間が「6か月前」なのか「3か月前」なのか、違約金が「残存期間の賃料相当額」なのか「固定額」なのかを確認しましょう。予告期間を守らないと自動更新されるケースもあるため、スケジュール管理が欠かせません。
これらを事前に確認しておくことで、更新料や契約条件の不明点をなくし、予期せぬコストやトラブルを防げます。その結果、更新前の不安を解消し、安心して手続きを進められます。契約書の内容を十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することも重要です。
また、以下の記事では、賃料相場の調査方法について解説しております。ぜひ参考にしてください。
契約更新の仕組みと注意点
店舗賃貸契約における契約期間や更新の仕組みは、店舗運営の安定性に大きく関わります。契約満了時に適切な対応を取らない場合、契約が意図せず更新されたり、条件変更の機会を逃すなどのトラブルが生じる可能性があります。こうしたリスクを避けるためには、契約期間の基本的な構造と、更新の成立条件・注意点を事前に理解しておくことが重要です。
店舗賃貸契約の一般的な期間
店舗賃貸契約の期間は、契約形態や地域によって異なりますが、一般的には1年から2年が多く見られます。
- 短期契約(1〜2年)
新規出店やテストマーケットに適しており、立地や顧客層を試す際に有効です。特に初出店の場合、長期契約はリスクが高いため、短期契約を選ぶケースが多くあります。 - 中長期の契約(3年〜5年)
安定したビジネス運営を目指す店舗オーナーに向いています。顧客基盤を築き、長期的な販売戦略を実行する際に有効です。
契約更新の成立条件と形態別の注意点
以下では、代表的な更新形態ごとに、契約更新が成立する典型的な要件と、借主が意識すべき注意点をまとめした。
| 更新形態 | 成立の典型要件 | 必要手続き | 起こりやすいリスク | 借主が意識したいこと |
| 法定更新 | 契約満了の1年前から6か月前までの間に、貸主または借主が「更新しない旨」または「条件を変更しなければ更新しない旨」の通知をしなかった場合 | 通知がなければ自動的に更新される | 契約条件の変更には別途協議・合意が必要。当面は従前条件が継続される | 更新自体は途切れにくいが、条件変更には合意手続きが必須。貸主との協議が必要 |
| 自動更新 | 契約書に自動更新条項があり、当事者から所定の異議・解約通知がない場合 | 通知不要(契約条項に従って自動的に更新) | 異議通知期限を逃すと、従前条件のまま継続される可能性がある | 契約書に記載された通知期限や通知方法(書面/メールなど)を事前に確認しておく |
| 合意更新 | 賃料・契約期間・更新料・特約などについて、貸主と借主が合意する場合 | 覚書や更新契約書などで文書化するのが一般的 | 合意が満了までにまとまらない場合、自動更新条項がある契約はその条項に従って更新される。条項がない場合は法定更新(借地借家法第26条)となる | 早めに協議を開始し、対案の準備・契約締結・精算までの流れを整理しておくことが望ましい |
このように、契約更新の成立にはそれぞれ異なる条件があり、借主側が事前に契約内容を確認し、更新時期に向けた準備を進めることで、不要なトラブルを回避しやすくなります。
更新拒否の条件と正当事由
契約更新に際し、貸主が更新を拒否する場合には、正当事由が必要です。正当事由とは、貸主が更新を拒否するための合理的な理由を指します。主な正当事由は以下の通りです。
- 契約違反:借主が契約条件に違反している場合、貸主は更新を拒否することができます。例として、賃料の未払い、施設の無断改造などが挙げられます。
- 貸主の使用目的: 貸主自身が店舗を使用したい場合、または他の借主に貸したい場合も、更新拒否の理由となることがあります。
- 市場環境の変化: 地域の市場環境が変化した結果、貸主が契約条件を見直す必要が生じて更新を拒否する場合も、正当事由とされることがあります。ただし、市場環境の変化のみでは正当事由として認められにくく、他の事情と合わせて総合的に判断される傾向があります。
正当事由を理解し、貸主と早めに協議することで、トラブルを回避できます。
更新料・事務手数料の相場と交渉術
店舗の契約更新に伴う更新料や事務手数料は、借主(店舗経営者)にとっても貸主にとっても重要な要素です。これらの費用の相場を理解し、適切に交渉することで、無駄なコストを削減し、スムーズな契約更新を実現できます。
更新料の相場
更新料は、一般的に賃料の1〜2か月分が相場とされています。
例えば、賃料が10万円の場合、更新料は10万円〜20万円程度になることがあります。ただし、更新料の金額は地域・物件の種類・貸主の方針によって異なります。そのため、周辺の市場相場を調査し、競合店舗の条件を把握することが重要です。
更新事務手数料の有無と相場
契約更新時には、更新事務手数料が発生する場合があります。これは、契約書の作成や事務処理にかかる費用をカバーするものです。更新事務手数料の相場は1万円〜5万円程度が一般的ですが、貸主の方針や契約内容によって異なるため、事前に確認が必要です。

注意すべきポイント
- 二重負担の有無:更新料(家賃1か月分など)と更新事務手数料が両方請求されるケースもあり、合計額が大きくなることがあります。予算に影響するため、事前に確認しておきましょう。
- 契約書への明記:判例上、契約書に明記されていない費用を請求されるのは妥当性を欠く可能性があります。更新事務手数料の有無や金額は契約書に記載されていることが多いため、必ず確認を。不要な費用を避けるためにも、交渉の余地があるかどうかを確認することが大切です。
更新料・手数料は交渉できる?成功のポイント
更新料や事務手数料は、貸主と借主の合意に基づく費用です。そのため、交渉の余地があります。成功のポイントは以下のとおりです。
- 相場を把握する
店舗契約の更新交渉を有利に進めるには、まず更新料や事務手数料の相場を把握しましょう。
不動産ポータル(例:「飲食店ドットコム」「テナントショップ」)で条件を入力し、掲載物件の更新料を比較すれば大まかな相場がつかめます。掲載がない場合は不動産会社に直接確認するのが有効です。こうして得た情報をもとに「他物件では1か月分なので同条件でお願いしたい」と根拠を示せば、交渉がしやすくなります。 - 柔軟な提案をする
交渉では、単に「更新料を下げてください」と言うだけではなく、貸主にとってもメリットのある提案をすることが重要です。例えば、「更新料を減額する代わりに契約期間を2年から3年に延長します」と提案すれば、貸主は長期的な安定収入を得られるため、交渉が成立しやすくなります。こうした「条件の交換」は、双方にとって納得感のある解決策になります。 - 継続意向を伝える
貸主は、安定した入居者を求めています。そのため、「今後も長くこの店舗を運営したい」「地域に根ざして営業を続けたい」という意思をしっかり伝えることが大切です。例えば、「この立地で5年以上営業しており、今後も継続する予定です」と具体的に話すと、貸主は安心感を持ち、更新料や条件の交渉に柔軟になる可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングでは、賃料減額サポートを行う際に、更新料の減額も併せて支援しています。専門家の知見を活用することで、交渉の成功率を高め、より有利な条件で契約を更新できる可能性があります。
賃料削減は更新時がチャンス
契約更新時は、賃料の削減を狙う絶好のタイミングです。
貸主としても、新しい借主を探す広告費や仲介手数料、空室期間の損失などを避けたいという思惑がございます。
また、契約書を作り直すこのタイミングは、条件を見直す自然な機会でもあります。さらに、市場の賃料相場と現在の賃料に乖離がある場合、その差を是正する根拠として交渉を持ちかけやすいのも更新時の特徴です。
賃料の減額交渉を有利に進めるためには、『賃料適正レポート』を用意することが効果的です。貸主に対して「今の賃料が適正かどうか」を客観的に示すことができ、交渉の説得力が大幅に高まります。
ビズキューブ・コンサルティングでは、業界最多の15万件以上の実態分析賃料データを基に、適正賃料を算出する『賃料適正診断サービス』を提供しています。診断結果は無料で受け取ることができますため、現在の賃料が適正かどうかを確認したい方は、ぜひお試しください。
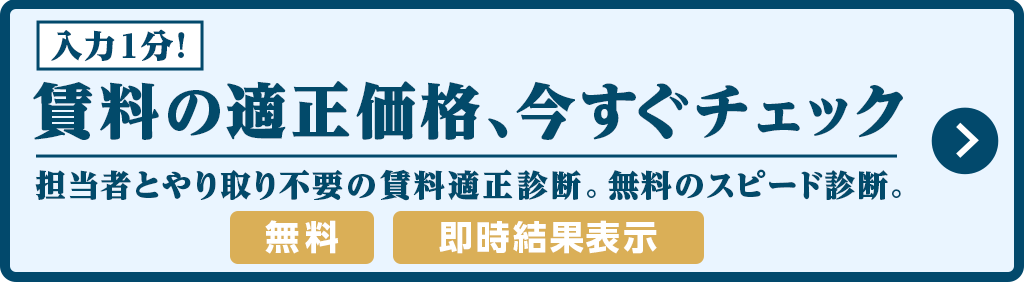
契約更新しない場合の選択肢と手続き
店舗賃貸契約を更新しない場合は、適切な手順を踏むことでトラブルを避け、スムーズな退去を実現できます。ここでは、解約予告、違約金、原状回復義務について詳しく解説します。
解約予告の期限
店舗を退去する際は、契約形態に応じて適切なタイミングで解約の意思を通知する必要があります。まず、契約期間中に退去する場合(中途解約)は、契約書に定められた予告期間(一般的には3〜6か月前)までに貸主へ通知する必要があります。予告期間を守らないと、違約金が発生する可能性があります。
一方、契約満了時に更新せず退去する場合は、契約書に自動更新条項がある場合、所定の期限内(通常は1〜3か月前)に更新拒絶の意思を通知しないと、契約が自動的に更新されてしまうことがあります。
いずれの場合も、通知は書面で行い、コピーを保管しておくことが望ましいです。書面を残すことで、後々のトラブル防止に役立ちます。また、解約予告の際には、貸主としっかりコミュニケーションを取り、信頼関係を損なわないことも重要です。
違約金の有無と計算方法
契約更新を行わず解約する場合、違約金が発生するケースがあります。違約金は契約書に明記されていることが多く、未経過の賃料を基準に計算されるのが一般的です。例えば、契約満了まで残り3か月ある場合、その期間の賃料を違約金として請求される可能性があります。
そのため、契約書を事前に確認し、違約金の有無や計算方法を把握しておくことが重要です。違約金が発生する場合は、予算に計上し、経営計画に反映させましょう。
原状回復義務と退去費用の関係
退去時には、原状回復義務が発生します。これは、借りた店舗を契約時の状態に戻す義務で、内装や設備の撤去、修理が含まれます。原状回復費用は、貸主と借主の間でトラブルになりやすい項目です。契約書に記載されている内容を必ず確認し、退去時には貸主と立会いを行い、現状を記録しておくことが重要です。
更新しない場合のスケジュールとやることリスト
更新しない場合は、計画的な準備が成功のカギです。以下の流れを意識しましょう。
| やること | 詳細 |
| 解約予告の通知 | 契約満了の3〜6か月前に解約通知を貸主に送付します。この際、書面で行うことを忘れずに。 |
| 契約内容の確認 | 違約金の有無や、原状回復義務の内容を契約書で確認します。 |
| 退出日を設定 | 貸主と退出日を調整し、合意を得ます。 |
| 原状回復計画の策定 | 内装や設備の原状回復計画を立て、必要な業者を手配します。契約書に指定業者の記載がある場合は、その条件を必ず確認してください。 |
| 退去立会の準備 | 退去時に貸主と立会いを行う日程を確保し、その際の確認事項を整理しておきます。 |
| 最終清掃と整理 | 退去前に店舗を清掃し、不要物品の整理を行います。 |
これらの手順を踏むことで、契約更新をしない場合でもスムーズな退去が可能になります。適切な準備を行い、トラブルを回避しましょう。
【経理向け】更新料の税務・会計処理について
店舗の賃貸契約における更新料の取り扱いは、税務や会計においても重要なポイントです。ここでは、消費税の課税可否、勘定科目の選定、仕訳例、決算・月次処理の注意点について解説します。
更新料に消費税はかかる?課税・非課税の判断
更新料は、原則として消費税の課税対象です。これは、店舗賃貸契約がサービスの提供とみなされ、その対価としての更新料に消費税が適用されるためです。
ただし、契約内容によっては例外があります。例えば、更新料がサービスの対価と認められない特殊なケースでは、非課税となる場合もあります。したがって、契約書の記載内容を確認し、課税・非課税を判断することが重要です。
勘定科目の選び方
更新料や更新手数料を会計処理する際は、契約の性質と企業の会計方針に応じて勘定科目を選定します。
- 長期前払費用
更新料が将来の使用に対する対価とみなされる場合、長期前払費用として資産計上し、契約期間に応じて費用化します。 - 地代家賃
更新料を家賃の一部とみなす場合、地代家賃として直接費用計上します。
決算・月次処理での注意点
賃貸契約に関連する会計処理は、決算や月次処理においても重要なポイントです。処理を誤ると、財務諸表の信頼性が損なわれたり、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。以下の点に注意しましょう。
- タイムリーな処理
更新料や手数料が発生した時点で迅速に処理することが重要です。処理が遅れると、月次決算で正確な損益が把握できず、経営判断を誤る可能性があります。 - 勘定科目の確認
更新料を「長期前払費用」として資産計上するのか、「地代家賃」として費用計上するのかは、契約内容や会計方針によって異なります。誤った科目を使用すると、決算書の信頼性が低下し、監査や税務調査で修正を求められることがあります。必要に応じて、専門家の意見を取り入れましょう。 - 消費税の適用状況の確認
更新料は原則課税対象ですが、契約内容によっては例外もあります。消費税の計算を誤ると、追徴課税やペナルティのリスクがあるため、最新の税制やガイドラインを常に確認してください。
これらのポイントを押さえておくことで、財務状況を正確に把握し、税務リスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
店舗の契約更新は、店舗運営を継続するうえで非常に重要な手続きです。更新料や賃料、契約条件を正しく理解し、早めに準備を進めることで、無駄なコストやトラブルを防ぐことができます。特に、契約書や更新料、更新事務手数料の確認、また場合によっては更新料の交渉準備は欠かせません。また更新しない場合も、解約予告の期限、違約金、原状回復義務を把握し、計画的に退去準備を進めることが重要です。
さらに、更新時は更新料や賃料の見直しができる絶好のタイミングです。相場情報や適正賃料レポートを活用し、貸主にとってもメリットのある提案を行うことで、交渉を有利に進められます。必要に応じて、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
賃料削減サポートならビズキューブ・コンサルティングにお任せ
ビズキューブ・コンサルティングは、日本で初めて賃料適正化サービスを開始した企業として、2001年の創業以来、累計35,558件の削減実績と2,349億円の賃料削減を達成してきました。
当社の強みは、貸主と良好な関係維持を重視したコンサルティング、全国対応が可能な業界最大規模のサポート体制、そして不動産鑑定士や経験豊富なコンサルタントによる専任チームです。
賃料は、店舗運営における固定費の中で最も大きな割合を占めるコストです。売上が変動しても賃料は毎月発生するため、賃料を適正化することは利益率の改善に直結します。特に、景気変動や市場相場の下落により、契約当初の賃料が現在の相場より高いケースは少なくありません。
さらに、契約更新時は条件を見直す自然なタイミングです。この機会に賃料を適正化することで、長期的な経営リスクを軽減し、無駄な固定費を削減できます。逆に、見直しをしないまま更新すると、不必要なコストを払い続けることになり、利益を圧迫する原因となります。
まずは「適正賃料診断」から始めてみませんか? 今の賃料が適正かどうかを無料で診断いたします。
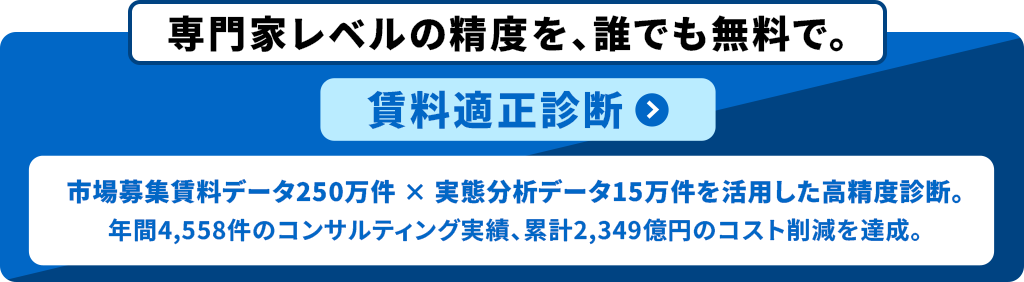
払いすぎている賃料、放置していませんか?
実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。
その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、
これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。
まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?
診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。












 人気記事ランキング
人気記事ランキング

